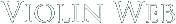不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[49223]
ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2014年11月30日 10:31
投稿者:晋作(ID:ElA0IjU)
ビソロッティ(FB)って箱を閉じてからパフリング入れる(削る)という17~18世紀のクレモナの製作マナーを守ってる数少ない製作家だそうです。
モラッシ(GBM)は外枠式で作ったり、一時期から中国製ホワイトバイオリンを仕入れて塗装だけクレモナで行うという話もあり、これが本当だったら酷い話。
某バイオリン販売の老舗では1985年以前のモラッシの価格はプレミアついて高いのですが最近のものはそれより安い価格ですね。
それでも他の製作家よりは高いのですが、外枠式手抜きバイオリン(本人は外枠式も伝統的な製作方法と主張してる様ですが)や中国で製作されたものに対して払う金額じゃないですね。
モラッシ(GBM)は外枠式で作ったり、一時期から中国製ホワイトバイオリンを仕入れて塗装だけクレモナで行うという話もあり、これが本当だったら酷い話。
某バイオリン販売の老舗では1985年以前のモラッシの価格はプレミアついて高いのですが最近のものはそれより安い価格ですね。
それでも他の製作家よりは高いのですが、外枠式手抜きバイオリン(本人は外枠式も伝統的な製作方法と主張してる様ですが)や中国で製作されたものに対して払う金額じゃないですね。
ヴァイオリン掲示板に戻る
16 / 16 ページ [ 157コメント ]
[55831]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年04月28日 10:52
投稿者:マルコムX(ID:EChYICc)
製作家の名前を並べたからって、音痴がヴァイオリンを弾けるようになるってものでもないぜ
オールド楽器は歳月によって作られるので、新作で再現するのは無理
仮に再現できるとしても、製作技術のブラッシュアップではなく、新しい科学技術みたいなのが必要
そもそも、ストラドが有名なのはヒル商会の陰謀のおかげなので、楽器として最も優れているからというわけでもない
ストラドの形状を元に楽器を作るのではなく、仮にクローンのようにストラドを複製できたとしても、それ本当に欲しいの?
多くの人はストラドのネームバリューや値段に価値を見出しているだけではないの?
自分の中にストラドを元にした形状の楽器の理想やイメージの音があるなら、ストラドモデルの楽器を色々と試してみればいいと思うけど、オールドの再現は無理でしょ
オールド楽器は歳月によって作られるので、新作で再現するのは無理
仮に再現できるとしても、製作技術のブラッシュアップではなく、新しい科学技術みたいなのが必要
そもそも、ストラドが有名なのはヒル商会の陰謀のおかげなので、楽器として最も優れているからというわけでもない
ストラドの形状を元に楽器を作るのではなく、仮にクローンのようにストラドを複製できたとしても、それ本当に欲しいの?
多くの人はストラドのネームバリューや値段に価値を見出しているだけではないの?
自分の中にストラドを元にした形状の楽器の理想やイメージの音があるなら、ストラドモデルの楽器を色々と試してみればいいと思うけど、オールドの再現は無理でしょ
[55832]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年04月28日 15:22
投稿者:松毬(ID:NjEYhpY)
君自身のことは良く分かった。ありがとねー
ただなぁ、
・無理かどうか決めるのは私でも君でもなく、それに関わる作家たちの取り組みだから❗周りは気長に待つしかないだろう。私も新しい科学技術が使われるだろうと思う
・クローンレプリカなら欲しい‼️沢山欲しい人がいるでしょう。今までは諦めて偽物モデル買ってきた訳で、それが無くなるのは大革命だよ❗
・今の楽器より悪くても、ストラドやオールドを知るのに、本物を買ったり借りたりしなくて良いからね。助かる❗
また、ストラドはただの楽器だったと解るだけかも知れないが、それならそれで良いじゃないか?
ストラド伝説の始まりは、確かにパリでしょう。ビオッティが、師匠の演奏旅行に付いてロシアに行き、エカテリーナからストラドをもらったのが始まり。
演奏旅行で、ビオッティがデビューして、パリに留まり、最初のバロック仕様のままストラドを弾いたでしょう。
不思議なことに、この楽器をビオッティは手放しており、また、この楽器を誰がモダンに改良したか?不明のまま。また、確かに、ビオッティはモダン楽器も弾くですが、最初に誰から手に入れたのかも不明です。
この傍らに、パノルモが改良したのだろうとされ、または、パリの作家、ルポー、ガン、コリカー、アルデリック、ピクらがバロックをモダンに改良したことで知られ、彼らもストラドに着目してコピーします。また、彼らの製作はガン・ベルナルデルが伝えます。
これを追いかけたビヨームも、モダンへの改良とストラドらのコピーで名を挙げ、ビヨームはハーンが使って親しまれていますね。
ビヨームを追い駆けたのがヒルです
ただなぁ、
・無理かどうか決めるのは私でも君でもなく、それに関わる作家たちの取り組みだから❗周りは気長に待つしかないだろう。私も新しい科学技術が使われるだろうと思う
・クローンレプリカなら欲しい‼️沢山欲しい人がいるでしょう。今までは諦めて偽物モデル買ってきた訳で、それが無くなるのは大革命だよ❗
・今の楽器より悪くても、ストラドやオールドを知るのに、本物を買ったり借りたりしなくて良いからね。助かる❗
また、ストラドはただの楽器だったと解るだけかも知れないが、それならそれで良いじゃないか?
ストラド伝説の始まりは、確かにパリでしょう。ビオッティが、師匠の演奏旅行に付いてロシアに行き、エカテリーナからストラドをもらったのが始まり。
演奏旅行で、ビオッティがデビューして、パリに留まり、最初のバロック仕様のままストラドを弾いたでしょう。
不思議なことに、この楽器をビオッティは手放しており、また、この楽器を誰がモダンに改良したか?不明のまま。また、確かに、ビオッティはモダン楽器も弾くですが、最初に誰から手に入れたのかも不明です。
この傍らに、パノルモが改良したのだろうとされ、または、パリの作家、ルポー、ガン、コリカー、アルデリック、ピクらがバロックをモダンに改良したことで知られ、彼らもストラドに着目してコピーします。また、彼らの製作はガン・ベルナルデルが伝えます。
これを追いかけたビヨームも、モダンへの改良とストラドらのコピーで名を挙げ、ビヨームはハーンが使って親しまれていますね。
ビヨームを追い駆けたのがヒルです
[55834]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年04月29日 15:41
投稿者:松毬(ID:ExE1UFI)
モダン楽器の普及と共にストラドは伝説化したのでしょう。また、ビヨームも、タリシオもストラド伝説に拍車をかけた者でもあり、次の逸話が有名です
「
ミラノのタリシオが、イタリア各地から名品だが型遅れとなったバロックのバイオリンを回収して、パリに運びます。パリではビヨームが買い、新型のモダン楽器に改良(オールド)して高値で売りました 。
ビヨームは、手元のオールドをコピーして、本物と見紛うばかりのレプリカを作り、大変出来が良かったレプリカをパガーニに見せたようです。この楽器は弟子のシボリに渡りました。
タリシオが亡くなった時、メシアを発見するのはビヨームでした
」
ビヨームは、ビヨームが雇った優秀な職人にビヨームの楽器、約3000挺以上を量産させましたが、当時は、オールドが売れたようで新品が売れず、売るために安くしたでしょう。
これはビヨームに続くヒル商会ではあからさまに同じことが起きたようで、新作モダンよりオールドが選ばれした。
しかし、現在、ビヨームはハーンも使います
一方で、イタリアは、フレンチに対してモダン化が遅れてしまいました。タリシオが亡くなった頃にはバロックからモダンへ製作スタイルを転向しますが、それでも世界的には当時新作のイタリアモダンは支持され続けて現在があります。現在の新作G.B.MやF.M.Bにたどり着ます。
ハーンが、手工品とは言え量産楽器を使ったのにはショッキングな印象があります
イタリアモダンが支持された背景には、ストラド伝説を加えたミラノのタリシオの存在があったでしょう。しかし、19世紀後半の新作モダンでも、パリの作家よりもミラノやトリノの作家が選ばれたのが事実で、ガダニーニ一族やロッカなどは有名です。
箱作りではストラドを真似たパリよりもストラドからの伝統が伝わるミラノなどイタリアに分があったようです。このような流れはバイオリンと言えばイタリアンとの大局を決めたでしょう。オールドもモダンもイタリアンといわれ、新作に至っても同様です
また、経年効果の影響は大きく、新作よりモダン、それよりオールドへと音が良くなるだけでなく、骨董価値も高めます。加えて、古くなるほど数が少なくなり、また、エピソードが附加して骨董価値を更に高めます。
数が少なく高価で音が良いオールドを頂点に、モダン、そして数が多い新作を底辺にピラミッド構造ができます。この中で楽器を選ぶことになり、目的や経済力、技量などにより振り分けされ、名奏者ほど良い楽器が使える傾向にありますますが、それでもストラドなどの必ず良い楽器を使えるとは限りません。奏者の中には経済的理由からモダンではなく新作を選ぶ場合もありますし、また、音が悪いモダンより音の良い新作なら新作が選ばれることもあるでしょう
現在のビヨームは名器のようになるのか?それよりもハーンは名奏者ゆえに筆を選ばずなのか?判然とはしていません。名奏者ともなればストラドなどオールドも手にし易いので、後者か?のような感じですが、、、
複雑な振動現象は、動的性能(ダイナミックス)論が必須で、バイオリンでは奏者やホールを合わせたダイナミスクスを解くことになるでしょう。
特に、90%以上は腕といわれ、楽器は残り5%か10%もあるかどうかの世界の中では、楽器違いでの差は更に小さいでしょう。ですが、その小さな差でも奏者は、違いを感じてより良い楽器を求めることは常にある欲求と思います
奏者のダイナミスクスと言うとピン来ませんが、運動理論だけでなく耳や脳、記憶、感情の働きも科学的な解明が進んでおり、すべて解明された後はモデル化できるでしょう。ダイナミスクスも経年効果も科学的に分析できる時代になったように感じます。
この辺りも明らかになれば、ストラドの新品状態も、新作のストラドも、ストラドを越えた未来の新作も登場することでしょう
「
ミラノのタリシオが、イタリア各地から名品だが型遅れとなったバロックのバイオリンを回収して、パリに運びます。パリではビヨームが買い、新型のモダン楽器に改良(オールド)して高値で売りました 。
ビヨームは、手元のオールドをコピーして、本物と見紛うばかりのレプリカを作り、大変出来が良かったレプリカをパガーニに見せたようです。この楽器は弟子のシボリに渡りました。
タリシオが亡くなった時、メシアを発見するのはビヨームでした
」
ビヨームは、ビヨームが雇った優秀な職人にビヨームの楽器、約3000挺以上を量産させましたが、当時は、オールドが売れたようで新品が売れず、売るために安くしたでしょう。
これはビヨームに続くヒル商会ではあからさまに同じことが起きたようで、新作モダンよりオールドが選ばれした。
しかし、現在、ビヨームはハーンも使います
一方で、イタリアは、フレンチに対してモダン化が遅れてしまいました。タリシオが亡くなった頃にはバロックからモダンへ製作スタイルを転向しますが、それでも世界的には当時新作のイタリアモダンは支持され続けて現在があります。現在の新作G.B.MやF.M.Bにたどり着ます。
ハーンが、手工品とは言え量産楽器を使ったのにはショッキングな印象があります
イタリアモダンが支持された背景には、ストラド伝説を加えたミラノのタリシオの存在があったでしょう。しかし、19世紀後半の新作モダンでも、パリの作家よりもミラノやトリノの作家が選ばれたのが事実で、ガダニーニ一族やロッカなどは有名です。
箱作りではストラドを真似たパリよりもストラドからの伝統が伝わるミラノなどイタリアに分があったようです。このような流れはバイオリンと言えばイタリアンとの大局を決めたでしょう。オールドもモダンもイタリアンといわれ、新作に至っても同様です
また、経年効果の影響は大きく、新作よりモダン、それよりオールドへと音が良くなるだけでなく、骨董価値も高めます。加えて、古くなるほど数が少なくなり、また、エピソードが附加して骨董価値を更に高めます。
数が少なく高価で音が良いオールドを頂点に、モダン、そして数が多い新作を底辺にピラミッド構造ができます。この中で楽器を選ぶことになり、目的や経済力、技量などにより振り分けされ、名奏者ほど良い楽器が使える傾向にありますますが、それでもストラドなどの必ず良い楽器を使えるとは限りません。奏者の中には経済的理由からモダンではなく新作を選ぶ場合もありますし、また、音が悪いモダンより音の良い新作なら新作が選ばれることもあるでしょう
現在のビヨームは名器のようになるのか?それよりもハーンは名奏者ゆえに筆を選ばずなのか?判然とはしていません。名奏者ともなればストラドなどオールドも手にし易いので、後者か?のような感じですが、、、
複雑な振動現象は、動的性能(ダイナミックス)論が必須で、バイオリンでは奏者やホールを合わせたダイナミスクスを解くことになるでしょう。
特に、90%以上は腕といわれ、楽器は残り5%か10%もあるかどうかの世界の中では、楽器違いでの差は更に小さいでしょう。ですが、その小さな差でも奏者は、違いを感じてより良い楽器を求めることは常にある欲求と思います
奏者のダイナミスクスと言うとピン来ませんが、運動理論だけでなく耳や脳、記憶、感情の働きも科学的な解明が進んでおり、すべて解明された後はモデル化できるでしょう。ダイナミスクスも経年効果も科学的に分析できる時代になったように感じます。
この辺りも明らかになれば、ストラドの新品状態も、新作のストラドも、ストラドを越えた未来の新作も登場することでしょう
[55836]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年04月29日 22:23
投稿者:アーン(ID:JSFGKAU)
国内外、ある程度名の知れた製作者のブログや投稿記事を探すと、どこかにこういう言い回しが見付けられますね。
「普通の製法で作られたバイオリンが300年経過すれば今のストラドやガルネリと何ら大差ない」と。
ある意味、これが楽器の原理であり、それ以上は「誰が作ったか」ではなく「誰が弾き込んだか」といった四次元的要素の問題になってくるのだと思ってます。
パガニーニの愛用したカノンは、の「準備が出来ていなかった」の言葉に代表されるように、使用を許された演奏者の感想は見てると共通点があるように感じられます。
ストラディバリウスも同じように弾き込み不足で良さが感じられない個体も沢山ある事と思います。
歴代の巨匠で、コロコロとストラディバリウスの別個体に変えるような方も少なくありませんが、ストラディバリウスが必ずしも素晴らしいとは結論付けられない何よりの証拠だと思いますね。本当に素晴らしい個体ならそれを生涯使い続けますからね。
そういう着眼点から見ると、そろそろクレモナの作者に序列を着けて販売する新作ビジネスモデルもそろそろ限界を迎えると思いますし、何らかのコンクールで複数入賞した職人が歳重ねてれば皆巨匠と呼ばれるような時代に足を突っ込みつつあるんでないかなーなんて思ってます。
「普通の製法で作られたバイオリンが300年経過すれば今のストラドやガルネリと何ら大差ない」と。
ある意味、これが楽器の原理であり、それ以上は「誰が作ったか」ではなく「誰が弾き込んだか」といった四次元的要素の問題になってくるのだと思ってます。
パガニーニの愛用したカノンは、の「準備が出来ていなかった」の言葉に代表されるように、使用を許された演奏者の感想は見てると共通点があるように感じられます。
ストラディバリウスも同じように弾き込み不足で良さが感じられない個体も沢山ある事と思います。
歴代の巨匠で、コロコロとストラディバリウスの別個体に変えるような方も少なくありませんが、ストラディバリウスが必ずしも素晴らしいとは結論付けられない何よりの証拠だと思いますね。本当に素晴らしい個体ならそれを生涯使い続けますからね。
そういう着眼点から見ると、そろそろクレモナの作者に序列を着けて販売する新作ビジネスモデルもそろそろ限界を迎えると思いますし、何らかのコンクールで複数入賞した職人が歳重ねてれば皆巨匠と呼ばれるような時代に足を突っ込みつつあるんでないかなーなんて思ってます。
[55841]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年04月30日 17:34
投稿者:松毬(ID:OJhjdiA)
これ ⬇️ 読んでみた。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ストラディバリウス#技術的知見
色んな断片では解っても、筋立ては解ってないようですね。文章自体もこんがらがっており意味が通りません。むしろ、引用元の記事[15][17]
の方面白い
モダン化でストラドに脚光があたるまで、バロック楽器ではストラドよりアマティの評価が高く名器とされる時代ですね。ストラディバリは、バロックの音量を上げるためにアーチを下げるなど試みていたようで、少し板を厚くしたようです。
それでも、モダンよりストラドは強度が低いようです。堀さんの楽器、ストラドの音を写すかの様に板厚を写したなら、モダンや新作よりも薄い板になったでしょうね?興味深いところです
また、ビヨームが同じ考えなら、板の化学処理問題ありますが既にビヨーム ≒ ストラド でも良いハズですが、実態は如何にか?これも興味深いです
以前からいわれる様に、モダンは板が厚いようです。板が厚くても良く鳴って、甘く綺麗な音なら良い楽器でしょう。ミラノのモダン作家が、厚い板でも鳴って綺麗な音の楽器にしたなら革新的です。
ストラドと木材強度が同じくらいのモダンって、どのモダンでしょうね。音的にはストラドを越えてるようなハズですが、、、ブラインドテストと一致するのでしょうか???
もし、この通りなら、新作G.B.M.やF.M.Bでも、アト100年ほどもすればストラド並み以上の楽器が出てきますね?
ですが、モダンは大局的にまだ音が固いとも思いますが、、、
引用[15]
https://globe.asahi.com/article/14779238
「ストラディバリウスを再現する堀酉基さん 一流演奏家を魅了する究極の「写し」」『朝日新聞Globe+』2023年1月7日。オリジナルの2023年1月6日時点におけるアーカイブ。
引用[17]
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202105252
“Materials Engineering of Violin Soundboards by Stradivari and Guarneri”. onlinelibrary.wiley.com. onlinelibrary.wiley.com. 2021年8月17日閲覧。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ストラディバリウス#技術的知見
色んな断片では解っても、筋立ては解ってないようですね。文章自体もこんがらがっており意味が通りません。むしろ、引用元の記事[15][17]
[17]
うれしいです
投稿日時:2001年03月23日 00:03
投稿者:piano(ID:JwhoQ1A)
ヴァイオリンホームページがなくなって残念に思っていましたが,
装いも新たに再開され,うれしいです。覚えてらっしゃらないかもしれませんが,子供二人のヴァイオリン練習に悩みながら、楽しみながら
付き合っている一母親です。
これからもよろしくお願いいたします。
装いも新たに再開され,うれしいです。覚えてらっしゃらないかもしれませんが,子供二人のヴァイオリン練習に悩みながら、楽しみながら
付き合っている一母親です。
これからもよろしくお願いいたします。
モダン化でストラドに脚光があたるまで、バロック楽器ではストラドよりアマティの評価が高く名器とされる時代ですね。ストラディバリは、バロックの音量を上げるためにアーチを下げるなど試みていたようで、少し板を厚くしたようです。
それでも、モダンよりストラドは強度が低いようです。堀さんの楽器、ストラドの音を写すかの様に板厚を写したなら、モダンや新作よりも薄い板になったでしょうね?興味深いところです
また、ビヨームが同じ考えなら、板の化学処理問題ありますが既にビヨーム ≒ ストラド でも良いハズですが、実態は如何にか?これも興味深いです
以前からいわれる様に、モダンは板が厚いようです。板が厚くても良く鳴って、甘く綺麗な音なら良い楽器でしょう。ミラノのモダン作家が、厚い板でも鳴って綺麗な音の楽器にしたなら革新的です。
ストラドと木材強度が同じくらいのモダンって、どのモダンでしょうね。音的にはストラドを越えてるようなハズですが、、、ブラインドテストと一致するのでしょうか???
もし、この通りなら、新作G.B.M.やF.M.Bでも、アト100年ほどもすればストラド並み以上の楽器が出てきますね?
ですが、モダンは大局的にまだ音が固いとも思いますが、、、
引用[15]
https://globe.asahi.com/article/14779238
「ストラディバリウスを再現する堀酉基さん 一流演奏家を魅了する究極の「写し」」『朝日新聞Globe+』2023年1月7日。オリジナルの2023年1月6日時点におけるアーカイブ。
引用[17]
[17]
うれしいです
投稿日時:2001年03月23日 00:03
投稿者:piano(ID:JwhoQ1A)
ヴァイオリンホームページがなくなって残念に思っていましたが,
装いも新たに再開され,うれしいです。覚えてらっしゃらないかもしれませんが,子供二人のヴァイオリン練習に悩みながら、楽しみながら
付き合っている一母親です。
これからもよろしくお願いいたします。
装いも新たに再開され,うれしいです。覚えてらっしゃらないかもしれませんが,子供二人のヴァイオリン練習に悩みながら、楽しみながら
付き合っている一母親です。
これからもよろしくお願いいたします。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202105252
“Materials Engineering of Violin Soundboards by Stradivari and Guarneri”. onlinelibrary.wiley.com. onlinelibrary.wiley.com. 2021年8月17日閲覧。
[55867]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年05月08日 15:01
投稿者:通りすがり(ID:QXZCEhM)
asdfさん
オールドが商業上の成功に必須とは思いません。ただ、興行の観点から、コンクールの経歴やら師匠筋やらアピールしたくなるのが人情だと思いますし、その一つの大きな要素がオールドの名器なんだと考えています。
クラシックやバイオリンに全く詳しくない人でも「ストラディバリウス」は伝説的な名器で超高額なすごい楽器で凄い人しか手にできないといったような謎の刷り込みが行われているのを時々感じます。
バイオリニスト(または所属事務所?)が広く一般に訴求しようと考えた時、名器に手を出すのは自然な発想なのかなと。
モダンに優れた楽器があり、ものによってはオールドよりも良い性能な個体があることも全く否定しません。普通にあり得ると思っています。
オールドが商業上の成功に必須とは思いません。ただ、興行の観点から、コンクールの経歴やら師匠筋やらアピールしたくなるのが人情だと思いますし、その一つの大きな要素がオールドの名器なんだと考えています。
クラシックやバイオリンに全く詳しくない人でも「ストラディバリウス」は伝説的な名器で超高額なすごい楽器で凄い人しか手にできないといったような謎の刷り込みが行われているのを時々感じます。
バイオリニスト(または所属事務所?)が広く一般に訴求しようと考えた時、名器に手を出すのは自然な発想なのかなと。
モダンに優れた楽器があり、ものによってはオールドよりも良い性能な個体があることも全く否定しません。普通にあり得ると思っています。
[55894]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年05月13日 22:23
投稿者:asdf(ID:EZchBjE)
通りすがり 様
若い楽器は、楽器が教えてくれないので自分で音を作らないといけない気がします。たくさんの美しい音が頭に入っていないとだめなのでしょう。良い音のイメージがあれば、あとは技術でなんとかそれを再現できる。むしろ若いほうが、どうしても少しの荒さは消せませんが機能性が高いので、その点で有利なのかもしれません。若い楽器は弾いていて楽しくないと思いますが、よい音楽的思い出があれば良い演奏ができるのでしょう。以下の面白いショートビデオでは Hahn 以外の人の演奏楽器は作者がみな同じマエストロではないかと思います。どうでしょうか? もちろん、Hahn のは Vuillaume;
youtube.com/shorts/-hD6ookmwno
弓も Hahn のは Sartory や Ouchard など20世紀もので、ほかの人はみなもっと素晴らしいのを使っているはずです。
若い楽器は、楽器が教えてくれないので自分で音を作らないといけない気がします。たくさんの美しい音が頭に入っていないとだめなのでしょう。良い音のイメージがあれば、あとは技術でなんとかそれを再現できる。むしろ若いほうが、どうしても少しの荒さは消せませんが機能性が高いので、その点で有利なのかもしれません。若い楽器は弾いていて楽しくないと思いますが、よい音楽的思い出があれば良い演奏ができるのでしょう。以下の面白いショートビデオでは Hahn 以外の人の演奏楽器は作者がみな同じマエストロではないかと思います。どうでしょうか? もちろん、Hahn のは Vuillaume;
youtube.com/shorts/-hD6ookmwno
弓も Hahn のは Sartory や Ouchard など20世紀もので、ほかの人はみなもっと素晴らしいのを使っているはずです。
[55902]
Re: ビソロッティとモラッシ【雑談です】
投稿日時:2025年05月15日 22:57
投稿者:通りすがり(ID:QlEWhYI)
asdfさん
全体的に同意です。
若い人にもいろんな良い楽器を試すチャンスが広まるといいなとも思っています。実家がよっぽど裕福でないと所謂名器は所有出来ないですよね。。
リンク頂いた動画を拝見しました。
どの楽器も素晴らしく、奏者の技量も世界トップレベルということで、演奏する人の個性が出てるのかなぁという印象です。
逆に演奏方法で私個人の好き嫌いは出ますが、なんの権威もない私の好みなので、その程度の話かなとも。
全体的に同意です。
若い人にもいろんな良い楽器を試すチャンスが広まるといいなとも思っています。実家がよっぽど裕福でないと所謂名器は所有出来ないですよね。。
リンク頂いた動画を拝見しました。
どの楽器も素晴らしく、奏者の技量も世界トップレベルということで、演奏する人の個性が出てるのかなぁという印象です。
逆に演奏方法で私個人の好き嫌いは出ますが、なんの権威もない私の好みなので、その程度の話かなとも。
ヴァイオリン掲示板に戻る
16 / 16 ページ [ 157コメント ]