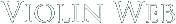不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[56314]
音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 11:39
投稿者:レモン娘(ID:KHFoB5Y)
大学生になってからバイオリンを始めた、所謂レイトスターターです。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
ヴァイオリン掲示板に戻る
2 / 4 ページ [ 32コメント ]
【ご参考】
[56333]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月12日 07:45
投稿者:pochi(ID:InIHgiU)
[56327]
松毬氏、
>※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから
-------440Hz付近の「A」です。
[56327]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月10日 04:47
投稿者:松毬(ID:F5BiETU)
※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから殆んど無関係に近い音で、微妙なニュアンスでアピールしたストーリーになってるんじゃないかなぁぁ。 なので本筋から外れています
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
>※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから
-------440Hz付近の「A」です。
[56339]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月13日 04:45
投稿者:松毬(ID:MpV0BwA)
※.書かれた通り、これは確かに難しいと思う。
同音が分るか分からないか?ってレモン娘様への教え「少しでも狂うと唸りが出ます。←これが音で解る必要がある」としているね。 だけど、唸りが殆んど無いこの「youtu.be/zieY5fVldeE?t=252[56325]
」Aみたいなのをもって、音程ズレてる云々と言っても、なんだか話が外れてくるじゃん。 ちょっと酷ですよね、レモン娘様に。
唸りなくても分るんだぁ、ってレモン娘様にアピールしたかったことは周りからも分りますが、、ここは、ズレたAなら、Aの唸りを聴かる場面でしょう
因みに、ピアニカのA、って一般的に442Hzで発売されてるんじゃないの? これ[ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32]
同音が分るか分からないか?ってレモン娘様への教え「少しでも狂うと唸りが出ます。←これが音で解る必要がある」としているね。 だけど、唸りが殆んど無いこの「youtu.be/zieY5fVldeE?t=252[56325]
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
唸りなくても分るんだぁ、ってレモン娘様にアピールしたかったことは周りからも分りますが、、ここは、ズレたAなら、Aの唸りを聴かる場面でしょう
因みに、ピアニカのA、って一般的に442Hzで発売されてるんじゃないの? これ[ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32]
[56345]
ピアニカのピッチと音程について
投稿日時:2025年11月13日 11:33
投稿者:おさむ(ID:IHAwABM)
ピアニカのピッチは442Hzのはずですが、実際に聴いてみると443Hzだったりします。温度変化で金属のリードが膨張収縮するからです。
ピアノと同じ鍵盤楽器だからといってピアニカに正確なピッチや音程を期待してはいけません。
ピッチや音程についてはpochiさんの解説が正確です。私はピアノ調律師でピッチや音程の専門家ですが、その私の目で見てpochiさんがピッチや音程で間違った発言をしたことはありません。
ピアノと同じ鍵盤楽器だからといってピアニカに正確なピッチや音程を期待してはいけません。
ピッチや音程についてはpochiさんの解説が正確です。私はピアノ調律師でピッチや音程の専門家ですが、その私の目で見てpochiさんがピッチや音程で間違った発言をしたことはありません。
[56346]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月13日 13:02
投稿者:松毬(ID:ODcmGHU)
※.440Hz[56333]
って言っているから、だいぶ話は違うみたい。
オーボエは、事前にチューニングメータで442Hzや443に合わせますね。 ピアニカの442Hzや443なら、協和するか1Hzくらいで唸ってるでしょう。 Aみたいなの440Hzでも、2~3Hzで唸るハズかぁ
それに、この[56170]
一つ前の投稿でも変なこと言ってたんですよ。 (同じ様に同音が分らないとか音痴だとか何とか言ってて誹謗中傷か名誉棄損かに当たったのか今はいつものように削除されてますね。)
この講師の方 youtu.be/HrHZjzXRSK4?t=322 、別に音感が悪い訳ではなく、この後のAを高く合わせるって言ってます。 これを取り上げて「(ピアノに比べて)明らかにAが高い、同音が分っていないとかレイトは直らない証拠ですとか何とか云々」とオウム返して取り上げただけでなく避難していた様に記憶しています。 更にこの後Gでは、この講師の方が言う通りピアノのGと大体合っているにも関わらずです。
音を聴いた感じがしなくて何をお考えになってんだろっ、って思っちゃいましたけどね
[56333]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月12日 07:45
投稿者:pochi(ID:InIHgiU)
[56327] 松毬氏、
>※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから
-------440Hz付近の「A」です。
>※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから
-------440Hz付近の「A」です。
オーボエは、事前にチューニングメータで442Hzや443に合わせますね。 ピアニカの442Hzや443なら、協和するか1Hzくらいで唸ってるでしょう。 Aみたいなの440Hzでも、2~3Hzで唸るハズかぁ
それに、この[56170]
[56170]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2025年09月24日 10:20
投稿者:松毬(ID:IzUENAk)
「ピアノで音を取るのだそうですが、ヴァイオリンがピアノよりも明らかに高い。」
その通りにして、Aは443Hz位に合わせるのです。 流行ともいえるのですがそれより高くも同音にすることもあって、ただ同音では古いスタイルとも言え、ここでは同音が解らないからではありません
ただ、この講師の方は、いくつか説明に悪い点が散見されて、上の点を唐突に持ち出したことの他、音程が悪くピアノの音程は分るけどバイオリンでは、、、と、、しかし、それをピアノの音で直して頂いて良くなったとか、同じ様に子供を指導して音程が良くて褒められたとか等、頓珍漢な話をしています。
(これだと、ベースにした平均律の方を先に直された、って話していて、その次のバイオリンの話を欠落させています)
これを「実際に合っていないのは決定的で、同音が解らない事になります。」と言えば、論理の裏で云えても、論理の裏では真理そのものは表しません。(裁判で言えば、請求棄却です😊)
なお、音は耳で聴く物理現象は、その通りです。
ですが、音が色で見えるとかを、説明するのも科学であり、同様に目で見える様にすることも科学なのです。 同様にSNSでも、音を定量的に表わすることを考えて頂きたいです
その通りにして、Aは443Hz位に合わせるのです。 流行ともいえるのですがそれより高くも同音にすることもあって、ただ同音では古いスタイルとも言え、ここでは同音が解らないからではありません
ただ、この講師の方は、いくつか説明に悪い点が散見されて、上の点を唐突に持ち出したことの他、音程が悪くピアノの音程は分るけどバイオリンでは、、、と、、しかし、それをピアノの音で直して頂いて良くなったとか、同じ様に子供を指導して音程が良くて褒められたとか等、頓珍漢な話をしています。
(これだと、ベースにした平均律の方を先に直された、って話していて、その次のバイオリンの話を欠落させています)
これを「実際に合っていないのは決定的で、同音が解らない事になります。」と言えば、論理の裏で云えても、論理の裏では真理そのものは表しません。(裁判で言えば、請求棄却です😊)
なお、音は耳で聴く物理現象は、その通りです。
ですが、音が色で見えるとかを、説明するのも科学であり、同様に目で見える様にすることも科学なのです。 同様にSNSでも、音を定量的に表わすることを考えて頂きたいです
この講師の方 youtu.be/HrHZjzXRSK4?t=322 、別に音感が悪い訳ではなく、この後のAを高く合わせるって言ってます。 これを取り上げて「(ピアノに比べて)明らかにAが高い、同音が分っていないとかレイトは直らない証拠ですとか何とか云々」とオウム返して取り上げただけでなく避難していた様に記憶しています。 更にこの後Gでは、この講師の方が言う通りピアノのGと大体合っているにも関わらずです。
音を聴いた感じがしなくて何をお考えになってんだろっ、って思っちゃいましたけどね
[56347]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月13日 16:30
投稿者:pochi(ID:JzdhGHU)
レモン娘氏、
ガット弦の方が分かり易いのなら、
「ヴィオリーノ」
https://i-love-strings.com/?pid=61219565
を使ってみましょう。
音色は、
「オイドクサの複雑な倍音を削ぎ落とした」
「ヤスモンのオイドクサ」
の様な音です。
耐久性にも勝れています。
駒寄りが弾けないとロクな音にはならないので、良い運弓法獲得に都合が良い弦です。
お値段高めですが、お値段の分位は「ドミナント」寄りも音色的耐久性に勝れています。
激しく弾いても3ヶ月程度は保ちます。
「ドミナント」は発音が俊敏で大音量で非常に良い弦なのですが、
「劣化したら発音が悪くなる」
「弓で弦を押さえ付けてもある程度は鳴る」
「劣化ポイントが分かりにくい」
結果、
「押さえ付けて弾く悪い癖が付き易い」
からお勧め出来ません。
E線は何でも良いのですが、
「e01」
https://i-love-strings.com/?pid=13960104
錫メッキでメッキが剥げて来たら替え時で、解り易いからお勧めしています。
===============
オーケストラの基準音でAがEに聴こえる人は厳しいでしょう。(ピリオド調弦ではなく現代調弦と言う意味で)440Hz付近のAは、442Hzであろうが443Hzであろうが、Eには聴こえません。
実践的には、
オーケストラのピアニカ(ピアノでも)にオーボエが基準音で、チューニングの為に合わせるのならピッタリ合わせます。
オーボエの音に対してコンサートマスターは、
「オーボエ」≦「コンサートマスター」
で合わせます。
木管は舞台照明で上がり気味、弦は下がり気味だからです。
一方、
ソリストの音程は結構勝手なものです。
「ハイフェッツ」は調弦が高かった事で有名ですね。例は幾らでもあります。と言うか、誰でも知っています。
歴史的録音です。
https://youtu.be/s1vVlMp2YTA
ピアノ伴奏に対してあまりにも高い。
「レオポルド・アウアー」(1845~1930年)
https://youtu.be/3SftFjZvOrM
「カール・ズスケ」(1934~)
自身の調弦に対して音程が高い。室内楽でも有名な人で、合奏の中では音程が高かったりしません。
私は子供の頃には母に調弦して貰っていたから、指導を受けた事は無いのですが、先生によっては、弟子の調弦を三度程度緩めて、
「調弦し直しなさい」
とするイジメの様な指導をする先生もいます。
ガット弦の方が分かり易いのなら、
「ヴィオリーノ」
https://i-love-strings.com/?pid=61219565
を使ってみましょう。
音色は、
「オイドクサの複雑な倍音を削ぎ落とした」
「ヤスモンのオイドクサ」
の様な音です。
耐久性にも勝れています。
駒寄りが弾けないとロクな音にはならないので、良い運弓法獲得に都合が良い弦です。
お値段高めですが、お値段の分位は「ドミナント」寄りも音色的耐久性に勝れています。
激しく弾いても3ヶ月程度は保ちます。
「ドミナント」は発音が俊敏で大音量で非常に良い弦なのですが、
「劣化したら発音が悪くなる」
「弓で弦を押さえ付けてもある程度は鳴る」
「劣化ポイントが分かりにくい」
結果、
「押さえ付けて弾く悪い癖が付き易い」
からお勧め出来ません。
E線は何でも良いのですが、
「e01」
https://i-love-strings.com/?pid=13960104
錫メッキでメッキが剥げて来たら替え時で、解り易いからお勧めしています。
===============
オーケストラの基準音でAがEに聴こえる人は厳しいでしょう。(ピリオド調弦ではなく現代調弦と言う意味で)440Hz付近のAは、442Hzであろうが443Hzであろうが、Eには聴こえません。
実践的には、
オーケストラのピアニカ(ピアノでも)にオーボエが基準音で、チューニングの為に合わせるのならピッタリ合わせます。
オーボエの音に対してコンサートマスターは、
「オーボエ」≦「コンサートマスター」
で合わせます。
木管は舞台照明で上がり気味、弦は下がり気味だからです。
一方、
ソリストの音程は結構勝手なものです。
「ハイフェッツ」は調弦が高かった事で有名ですね。例は幾らでもあります。と言うか、誰でも知っています。
歴史的録音です。
https://youtu.be/s1vVlMp2YTA
ピアノ伴奏に対してあまりにも高い。
「レオポルド・アウアー」(1845~1930年)
https://youtu.be/3SftFjZvOrM
「カール・ズスケ」(1934~)
自身の調弦に対して音程が高い。室内楽でも有名な人で、合奏の中では音程が高かったりしません。
私は子供の頃には母に調弦して貰っていたから、指導を受けた事は無いのですが、先生によっては、弟子の調弦を三度程度緩めて、
「調弦し直しなさい」
とするイジメの様な指導をする先生もいます。
[56350]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 01:38
投稿者:松毬(ID:IIJyMwI)
※.アハハハぁっ、たまに良いこといいますね。 「オーケストラの基準音でAがEに聴こえる人は厳しい」、そうですね。 それは、逆に言って「基準音にオクターブ上のEを持ってくるのは非常識」です。
つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。 そして、もともと[56325]
に書いてあって「後からミキシングで電気的に合成音声にして」と、あらかじめ自作自演で仕込まれている訳です。
が、持ってきたご本人自身も恐らく訳が分らんようになっているようで、ピアニカの音と思っている様です。 どうもオケで鍵盤のAを押すシーンを見せられたことが加わってか、誤解したように見えます
そもそもこんな動画もってくる方がどうかしていると思っちゃいますよね。 威厳を示してハロー効果で説得では、何の論拠もありません。 ただの騙しです
さて、本筋に少しずつ戻ります
しかし、そんなんで騙されてはいけません。 調律師さんを騙すほどよく出来ているのは、元々このAらしきは音の本職で心理学と振動を研究した玄人が仕込んだようです。 (非常に良く計算されてあって、基準音でピッチがあったのように唸らない様に、且つ、のだ目ちゃんの音はハッキリ通るようにズラしてあると考えられます)
基準音にEは不適切でも、Aの3倍音であるオクターブ上のEは、非常に仲良しの音です。
それは、[56324]
リサージュ図の③④では、完全5度が完全8度に優先して、順番が飛んで逆になったかように見えるほどです
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
音程を考える時、この倍音が非常に関係していることを押さえて置かなければなりません[56332]
つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。 そして、もともと[56325]
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
が、持ってきたご本人自身も恐らく訳が分らんようになっているようで、ピアニカの音と思っている様です。 どうもオケで鍵盤のAを押すシーンを見せられたことが加わってか、誤解したように見えます
そもそもこんな動画もってくる方がどうかしていると思っちゃいますよね。 威厳を示してハロー効果で説得では、何の論拠もありません。 ただの騙しです
さて、本筋に少しずつ戻ります
しかし、そんなんで騙されてはいけません。 調律師さんを騙すほどよく出来ているのは、元々このAらしきは音の本職で心理学と振動を研究した玄人が仕込んだようです。 (非常に良く計算されてあって、基準音でピッチがあったのように唸らない様に、且つ、のだ目ちゃんの音はハッキリ通るようにズラしてあると考えられます)
基準音にEは不適切でも、Aの3倍音であるオクターブ上のEは、非常に仲良しの音です。
それは、[56324]
[56324]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 10:20
投稿者:松毬(ID:JRSIaRA)
音の感覚について
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
音程を考える時、この倍音が非常に関係していることを押さえて置かなければなりません[56332]
[56332]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月12日 05:28
投稿者:松毬(ID:MxQ5lyY)
※1.ありがとう。しかし、まだそんなには余計です。 先々を考えると、ってのはありますけどもね。
[56324]は、完全1度、完全5度の話の上で、しだいに音が複雑になるっていくことを図で示したにすぎません。 しかも、リンク先の図ありき、これに合わせたにすぎません
※2.ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32
そもそも論として、youtu.be/zieY5fVldeE?t=252 [56325]はピアニカの音ではないでしょうから、根本のところで頓珍漢になるのでしょう。
特殊な音なのですが耳で聞いたとは思えず、書いてある通りチューナーで図れば【ピアニカ<オーボエ】になるから、その通り書いていて[56325][56019] [54805] [53968]散々外してきたことになるでしょうね
◎.さて本筋では、[56327] は純音での話ですので、[56324] の終わりにある通り、実際のところ、つまり色んな倍音がある中での唸りや差音はどうか? もう少し掘り下げておきます。
では、次の機会に
[56324]は、完全1度、完全5度の話の上で、しだいに音が複雑になるっていくことを図で示したにすぎません。 しかも、リンク先の図ありき、これに合わせたにすぎません
※2.ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32
そもそも論として、youtu.be/zieY5fVldeE?t=252 [56325]はピアニカの音ではないでしょうから、根本のところで頓珍漢になるのでしょう。
特殊な音なのですが耳で聞いたとは思えず、書いてある通りチューナーで図れば【ピアニカ<オーボエ】になるから、その通り書いていて[56325][56019] [54805] [53968]散々外してきたことになるでしょうね
◎.さて本筋では、[56327] は純音での話ですので、[56324] の終わりにある通り、実際のところ、つまり色んな倍音がある中での唸りや差音はどうか? もう少し掘り下げておきます。
では、次の機会に
[56351]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 04:34
投稿者:pochi(ID:JzdhGHU)
[56350]
>つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。
-----------3倍音成分が多いとはいえ、明らかな間違いなので訂正しましょう。
ヴァイオリンでも基音より3倍音の方が大きくて、最も大きいのですよ。
[56350]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 01:38
投稿者:松毬(ID:IIJyMwI)
※.アハハハぁっ、たまに良いこといいますね。 「オーケストラの基準音でAがEに聴こえる人は厳しい」、そうですね。 それは、逆に言って「基準音にオクターブ上のEを持ってくるのは非常識」です。
つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。 そして、もともと[56325] に書いてあって「後からミキシングで電気的に合成音声にして」と、あらかじめ自作自演で仕込まれている訳です。
が、持ってきたご本人自身も恐らく訳が分らんようになっているようで、ピアニカの音と思っている様です。 どうもオケで鍵盤のAを押すシーンを見せられたことが加わってか、誤解したように見えます
そもそもこんな動画もってくる方がどうかしていると思っちゃいますよね。 威厳を示してハロー効果で説得では、何の論拠もありません。 ただの騙しです
さて、本筋に少しずつ戻ります
しかし、そんなんで騙されてはいけません。 調律師さんを騙すほどよく出来ているのは、元々このAらしきは音の本職で心理学と振動を研究した玄人が仕込んだようです。 (非常に良く計算されてあって、基準音でピッチがあったのように唸らない様に、且つ、のだ目ちゃんの音はハッキリ通るようにズラしてあると考えられます)
基準音にEは不適切でも、Aの3倍音であるオクターブ上のEは、非常に仲良しの音です。
それは、[56324]リサージュ図の③④では、完全5度が完全8度に優先して、順番が飛んで逆になったかように見えるほどです
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
音程を考える時、この倍音が非常に関係していることを押さえて置かなければなりません[56332]
つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。 そして、もともと[56325] に書いてあって「後からミキシングで電気的に合成音声にして」と、あらかじめ自作自演で仕込まれている訳です。
が、持ってきたご本人自身も恐らく訳が分らんようになっているようで、ピアニカの音と思っている様です。 どうもオケで鍵盤のAを押すシーンを見せられたことが加わってか、誤解したように見えます
そもそもこんな動画もってくる方がどうかしていると思っちゃいますよね。 威厳を示してハロー効果で説得では、何の論拠もありません。 ただの騙しです
さて、本筋に少しずつ戻ります
しかし、そんなんで騙されてはいけません。 調律師さんを騙すほどよく出来ているのは、元々このAらしきは音の本職で心理学と振動を研究した玄人が仕込んだようです。 (非常に良く計算されてあって、基準音でピッチがあったのように唸らない様に、且つ、のだ目ちゃんの音はハッキリ通るようにズラしてあると考えられます)
基準音にEは不適切でも、Aの3倍音であるオクターブ上のEは、非常に仲良しの音です。
それは、[56324]リサージュ図の③④では、完全5度が完全8度に優先して、順番が飛んで逆になったかように見えるほどです
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
音程を考える時、この倍音が非常に関係していることを押さえて置かなければなりません[56332]
>つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。
-----------3倍音成分が多いとはいえ、明らかな間違いなので訂正しましょう。
ヴァイオリンでも基音より3倍音の方が大きくて、最も大きいのですよ。
[56352]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 21:53
投稿者:pochi(ID:F5eBSIc)
レモン娘氏、
・楽器の整備が普通で、
・弦が新しくて、
・運弓が普通に出来て、
・同音が正確に解るのなら、
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
ヴァイオリンではあんまり行わない、こんな調弦法があります。A線の3倍音フラジオ(第4ポジション1)とE線2倍音フラジオ(第4ポジション4)は同音なので、チェロではよく行われる調弦法です(チェロではポジションは違いますが理屈は同じです)。
チェロではこのフラジオ調弦法で調弦して、完全五度が合わなくなったら弦の替え時なのです。最終的には完全五度で確認しますが、調弦の良い練習にはなるので挑戦してみましょう。
弦が傷むと高次倍音ほどフラジオの音程は低くなり勝ちです。
調弦は弾いた音の残響で合わせるのですが、開放弦を弾いた時に、弦の種類によって、弦が傷んだ時の残響の音程の高低が違います。ガット弦では残響が高くなり、金属弦では低くなる傾向があり、人工素材弦は中間で様々です。
・楽器の整備が普通で、
・弦が新しくて、
・運弓が普通に出来て、
・同音が正確に解るのなら、
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
ヴァイオリンではあんまり行わない、こんな調弦法があります。A線の3倍音フラジオ(第4ポジション1)とE線2倍音フラジオ(第4ポジション4)は同音なので、チェロではよく行われる調弦法です(チェロではポジションは違いますが理屈は同じです)。
チェロではこのフラジオ調弦法で調弦して、完全五度が合わなくなったら弦の替え時なのです。最終的には完全五度で確認しますが、調弦の良い練習にはなるので挑戦してみましょう。
弦が傷むと高次倍音ほどフラジオの音程は低くなり勝ちです。
調弦は弾いた音の残響で合わせるのですが、開放弦を弾いた時に、弦の種類によって、弦が傷んだ時の残響の音程の高低が違います。ガット弦では残響が高くなり、金属弦では低くなる傾向があり、人工素材弦は中間で様々です。
[56354]
調弦デモ比べてみました
投稿日時:2025年11月15日 09:32
投稿者:松毬(ID:KQNGV5A)
※.[56351]
→アハハハぁっ、そりゃ3倍音が高くなる場合があるのは当然しってるよ。 アコースティックの話をしても意味ないでしょ。 「後からミキシングで電気的に合成音声にして」[56325]
と書いているのだから。 電気的に合成音声での話をしてくれなきゃ
そもそもは、そんな変なもん持ってくるからでしょ。 [56352]
は良いと思いますが、嘲るように余計なことやってるから自ら嵌った訳でしょ
さて、本筋に戻ります。 レモン娘 様へ
実践に向かって、まずは色んな調弦デモを見比べてみましょう
①.youtu.be/-6Sbd6y9MPU 模範的とおもいます。 示すべきこと簡潔明瞭(堂々と筋だっている。不足も蛇足もなく混乱もない)。 これでのコメント通り☆和音(和声)が協和した趣きがポイントです
・Option1:音叉&指ではじく調弦
→youtu.be/TyC6e3LJKII
→youtu.be/6nrsjnSVEng?t=163
参考〈ペグ〉
・回し方Option:→youtu.be/ezJqLZZ06oA?t=202
・コンポジション調整法Option1:→youtu.be/1fz-Z7fp_FM?t=1356
・弦巻き方による調整法Option2:→youtu.be/uKCPcSEeMg4?t=46
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 理論的な説明が分かり易いとおもいます(ただ実践では要の第三の音の鼓動(唸り)は分かり難いものの、応用として他の5度、4度、3度、6度の音程へも展開できる大きな利点があります)
ステップ1:完全1度の同音、同音への鼓動(唸り)をバイオリンでハッキリと確認できます。 鼓動が消えて、同音で音がスッキリとした感じ、和音として協和した感覚が分ると思います
ステップ2:完全5度(A4:E5)、第三の音(コンビネーショントーン、差音)に触れます。 第三の音A3(A4のオクターブ下)は知覚できますが非常に微小で初めは識覚が不足してわからないかも、、、とおもいます。 (第三の音は、A4:E5に対しA3、D4:A4に対しD3、G3:D4に対しG2)
ステップ3:完全5度(A4:E5)に対しA4とA3(又はA'3→A3)の鼓動に触れます。 [56332]
予告通り実際は上ステップ1より音量が小さく、ステップ2の第三の音らの鼓動があります。 これに着目して上ステップ1同様に調整します
③.youtu.be/RzVdYZVaJHo?t=281 こちらの方が鼓動(唸り)が分かり易い(D4:A4)
★トレーニングの要点は、次三つの不足した識覚を強化する(音やその変化を聴いて覚える)ことです
・A4完全1度、A4:E5, D4:A4, G3:D4,完全5度の和声を知覚すること
・上が崩れて干渉した音や鼓動(唸り)を知覚すること
・第三の音を知覚すること
なお、上②では、ステップ2の通り第三の音はわからないかもで、初めは現実問題として結局は完全5度が協和した感覚を基に調弦しているかもです。 この為、初めはステップ1の協和の感覚に似た、第三の音含めた三音の和音が協和した感覚を先に探ってしまうかもしれませんね
また、同②では、感覚的には、A4:E5ではA3に第三の音が現れ、E'5→E5へ調弦に伴い、A4とA'3→A3への鼓動があります。 物理的には、純音では[56327]
の鼓動(唸り)に対して更には鼓動は追加されませんが、実際はA4,E5の倍音関係毎に色々な差音が生じ、また、同音関係にもなって同音の鼓動が生じて、A4とA'3は各々独立に鼓動していると思います
[差音同士で同音への鼓動]
A4とE'5の差音によるE'3 vs A4の2倍音のA5とE'5の差音によるE''3
[倍音同士で同音への鼓動] A4の3倍音のE6 vs E'5の2倍音のE'6
*更にこの上の倍音でも同じようなことが起きてこれらに重なります
[56351]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 04:34
投稿者:pochi(ID:JzdhGHU)
[56350]
>つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。
-----------3倍音成分が多いとはいえ、明らかな間違いなので訂正しましょう。
ヴァイオリンでも基音より3倍音の方が大きくて、最も大きいのですよ。
>つまり、Aらしきの正体は、3倍上の音、オクターブ上のEです。
-----------3倍音成分が多いとはいえ、明らかな間違いなので訂正しましょう。
ヴァイオリンでも基音より3倍音の方が大きくて、最も大きいのですよ。
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
そもそもは、そんな変なもん持ってくるからでしょ。 [56352]
[56352]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 21:53
投稿者:pochi(ID:F5eBSIc)
レモン娘氏、
・楽器の整備が普通で、
・弦が新しくて、
・運弓が普通に出来て、
・同音が正確に解るのなら、
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
ヴァイオリンではあんまり行わない、こんな調弦法があります。A線の3倍音フラジオ(第4ポジション1)とE線2倍音フラジオ(第4ポジション4)は同音なので、チェロではよく行われる調弦法です(チェロではポジションは違いますが理屈は同じです)。
チェロではこのフラジオ調弦法で調弦して、完全五度が合わなくなったら弦の替え時なのです。最終的には完全五度で確認しますが、調弦の良い練習にはなるので挑戦してみましょう。
弦が傷むと高次倍音ほどフラジオの音程は低くなり勝ちです。
調弦は弾いた音の残響で合わせるのですが、開放弦を弾いた時に、弦の種類によって、弦が傷んだ時の残響の音程の高低が違います。ガット弦では残響が高くなり、金属弦では低くなる傾向があり、人工素材弦は中間で様々です。
・楽器の整備が普通で、
・弦が新しくて、
・運弓が普通に出来て、
・同音が正確に解るのなら、
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
ヴァイオリンではあんまり行わない、こんな調弦法があります。A線の3倍音フラジオ(第4ポジション1)とE線2倍音フラジオ(第4ポジション4)は同音なので、チェロではよく行われる調弦法です(チェロではポジションは違いますが理屈は同じです)。
チェロではこのフラジオ調弦法で調弦して、完全五度が合わなくなったら弦の替え時なのです。最終的には完全五度で確認しますが、調弦の良い練習にはなるので挑戦してみましょう。
弦が傷むと高次倍音ほどフラジオの音程は低くなり勝ちです。
調弦は弾いた音の残響で合わせるのですが、開放弦を弾いた時に、弦の種類によって、弦が傷んだ時の残響の音程の高低が違います。ガット弦では残響が高くなり、金属弦では低くなる傾向があり、人工素材弦は中間で様々です。
さて、本筋に戻ります。 レモン娘 様へ
実践に向かって、まずは色んな調弦デモを見比べてみましょう
①.youtu.be/-6Sbd6y9MPU 模範的とおもいます。 示すべきこと簡潔明瞭(堂々と筋だっている。不足も蛇足もなく混乱もない)。 これでのコメント通り☆和音(和声)が協和した趣きがポイントです
・Option1:音叉&指ではじく調弦
→youtu.be/TyC6e3LJKII
→youtu.be/6nrsjnSVEng?t=163
参考〈ペグ〉
・回し方Option:→youtu.be/ezJqLZZ06oA?t=202
・コンポジション調整法Option1:→youtu.be/1fz-Z7fp_FM?t=1356
・弦巻き方による調整法Option2:→youtu.be/uKCPcSEeMg4?t=46
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 理論的な説明が分かり易いとおもいます(ただ実践では要の第三の音の鼓動(唸り)は分かり難いものの、応用として他の5度、4度、3度、6度の音程へも展開できる大きな利点があります)
ステップ1:完全1度の同音、同音への鼓動(唸り)をバイオリンでハッキリと確認できます。 鼓動が消えて、同音で音がスッキリとした感じ、和音として協和した感覚が分ると思います
ステップ2:完全5度(A4:E5)、第三の音(コンビネーショントーン、差音)に触れます。 第三の音A3(A4のオクターブ下)は知覚できますが非常に微小で初めは識覚が不足してわからないかも、、、とおもいます。 (第三の音は、A4:E5に対しA3、D4:A4に対しD3、G3:D4に対しG2)
ステップ3:完全5度(A4:E5)に対しA4とA3(又はA'3→A3)の鼓動に触れます。 [56332]
[56332]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月12日 05:28
投稿者:松毬(ID:MxQ5lyY)
※1.ありがとう。しかし、まだそんなには余計です。 先々を考えると、ってのはありますけどもね。
[56324]は、完全1度、完全5度の話の上で、しだいに音が複雑になるっていくことを図で示したにすぎません。 しかも、リンク先の図ありき、これに合わせたにすぎません
※2.ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32
そもそも論として、youtu.be/zieY5fVldeE?t=252 [56325]はピアニカの音ではないでしょうから、根本のところで頓珍漢になるのでしょう。
特殊な音なのですが耳で聞いたとは思えず、書いてある通りチューナーで図れば【ピアニカ<オーボエ】になるから、その通り書いていて[56325][56019] [54805] [53968]散々外してきたことになるでしょうね
◎.さて本筋では、[56327]
は純音での話ですので、[56324] の終わりにある通り、実際のところ、つまり色んな倍音がある中での唸りや差音はどうか? もう少し掘り下げておきます。
では、次の機会に
[56324]は、完全1度、完全5度の話の上で、しだいに音が複雑になるっていくことを図で示したにすぎません。 しかも、リンク先の図ありき、これに合わせたにすぎません
※2.ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32
そもそも論として、youtu.be/zieY5fVldeE?t=252 [56325]はピアニカの音ではないでしょうから、根本のところで頓珍漢になるのでしょう。
特殊な音なのですが耳で聞いたとは思えず、書いてある通りチューナーで図れば【ピアニカ<オーボエ】になるから、その通り書いていて[56325][56019] [54805] [53968]散々外してきたことになるでしょうね
◎.さて本筋では、[56327]
[56327]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月10日 04:47
投稿者:松毬(ID:F5BiETU)
※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから殆んど無関係に近い音で、微妙なニュアンスでアピールしたストーリーになってるんじゃないかなぁぁ。 なので本筋から外れています
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
では、次の機会に
③.youtu.be/RzVdYZVaJHo?t=281 こちらの方が鼓動(唸り)が分かり易い(D4:A4)
★トレーニングの要点は、次三つの不足した識覚を強化する(音やその変化を聴いて覚える)ことです
・A4完全1度、A4:E5, D4:A4, G3:D4,完全5度の和声を知覚すること
・上が崩れて干渉した音や鼓動(唸り)を知覚すること
・第三の音を知覚すること
なお、上②では、ステップ2の通り第三の音はわからないかもで、初めは現実問題として結局は完全5度が協和した感覚を基に調弦しているかもです。 この為、初めはステップ1の協和の感覚に似た、第三の音含めた三音の和音が協和した感覚を先に探ってしまうかもしれませんね
また、同②では、感覚的には、A4:E5ではA3に第三の音が現れ、E'5→E5へ調弦に伴い、A4とA'3→A3への鼓動があります。 物理的には、純音では[56327]
[56327]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月10日 04:47
投稿者:松毬(ID:F5BiETU)
※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから殆んど無関係に近い音で、微妙なニュアンスでアピールしたストーリーになってるんじゃないかなぁぁ。 なので本筋から外れています
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
[差音同士で同音への鼓動]
A4とE'5の差音によるE'3 vs A4の2倍音のA5とE'5の差音によるE''3
[倍音同士で同音への鼓動] A4の3倍音のE6 vs E'5の2倍音のE'6
*更にこの上の倍音でも同じようなことが起きてこれらに重なります
[56357]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月16日 02:20
投稿者:pochi(ID:MCaYARA)
削除されて仕舞ったので、
件のピアニカは「E」ではなく「A」です。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
件のピアニカは「E」ではなく「A」です。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
ヴァイオリン掲示板に戻る
2 / 4 ページ [ 32コメント ]