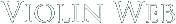不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[56314]
音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 11:39
投稿者:レモン娘(ID:KHFoB5Y)
大学生になってからバイオリンを始めた、所謂レイトスターターです。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
ヴァイオリン掲示板に戻る
1 / 4 ページ [ 32コメント ]
【ご参考】
[56315]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 14:47
投稿者:通りすがり(ID:JEIUkHU)
最初はチューナー見つつ、で良いんじゃないでしょうか。
ただそればっかりだと良くないので、自分の出したい音を歌ってから弾いてみるとか、色々試してみましょう。
ただそればっかりだと良くないので、自分の出したい音を歌ってから弾いてみるとか、色々試してみましょう。
[56316]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 16:46
投稿者:pochi(ID:mWMxVWA)
レモン娘氏、お早う御座います。
まず、「感」を鍛える方法は無い、と考えて下さい。
そうは言っても何ともなら無いので、何とかする手法を考えるべきですよね。
音叉を使いましょう。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/marina-guitar/onsa-442-box.html
極近くでピッタリのAを大きな音で弾くと、極僅かですが共鳴します。
アジャスタで調整してピッタリのAを「共鳴で」弾ける様にしましょう。
出来ない人がいて、本当に何とも成りません。
音程の理屈として、「完全一度」(同音)が解らない人には、何ともなら無いのがヴァイオリンです。作音楽器の原理です。
チューナーの針を見詰めても解る様にはならない(解る事に繋がらない)ので無駄ですが、音程の前提に「良い運弓」の獲得が有ります。
運弓が下手だとチューナーの針が揺れるので、運弓の良し悪しの可視化にはなります。
便利なのは高感度設定にしたチューナーの針が動かなければ良く、針が真ん中に来る必要も無いので、良い練習になると思います。
E線開放弦pp全弓、特にダウンは誰に取っても非常に難しいものです。ヴァイオリンの演奏技術の盲点で、現実的には楽曲の中に滅多に出てきません。
>誹謗中傷
------本当の事を書いています。誹謗中傷だと思う時点でヴァイオリンには向きません。ヴァイオリンを習うと、先生からずっと誹謗中傷され続ける事になりますよ。
まず、「感」を鍛える方法は無い、と考えて下さい。
そうは言っても何ともなら無いので、何とかする手法を考えるべきですよね。
音叉を使いましょう。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/marina-guitar/onsa-442-box.html
極近くでピッタリのAを大きな音で弾くと、極僅かですが共鳴します。
アジャスタで調整してピッタリのAを「共鳴で」弾ける様にしましょう。
出来ない人がいて、本当に何とも成りません。
音程の理屈として、「完全一度」(同音)が解らない人には、何ともなら無いのがヴァイオリンです。作音楽器の原理です。
チューナーの針を見詰めても解る様にはならない(解る事に繋がらない)ので無駄ですが、音程の前提に「良い運弓」の獲得が有ります。
運弓が下手だとチューナーの針が揺れるので、運弓の良し悪しの可視化にはなります。
便利なのは高感度設定にしたチューナーの針が動かなければ良く、針が真ん中に来る必要も無いので、良い練習になると思います。
E線開放弦pp全弓、特にダウンは誰に取っても非常に難しいものです。ヴァイオリンの演奏技術の盲点で、現実的には楽曲の中に滅多に出てきません。
>誹謗中傷
------本当の事を書いています。誹謗中傷だと思う時点でヴァイオリンには向きません。ヴァイオリンを習うと、先生からずっと誹謗中傷され続ける事になりますよ。
[56317]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月08日 05:00
投稿者:松毬(ID:GScAdSY)
レモン娘 様 初めまして、おはようございます
大変恐縮ですが、コメントから今は恐らく純正5度にもピアノの平均律5度にもなってないのでは??と思えます。 先生も、まあまあいい加減には合ってるからいいかぁ、と思ってるよう見えます。 また、そんな先生がピッタリ純正5度調弦できるようになったら、さぞ感動するでしょう
先ずペグ調整で微小な音程1centの音を調整できるようにペグを調整して下さい。 これが上手くできないなら4弦アジャスター付きのテールピースにしてください
-0.先ず開放A合わせです
基準Aの音を出してもらって、この音との重音で開放Aをピッタリ同音(0cent)にゆぅっくりとでよいので合わせて下さい。 基準Aは、弦の音、ピアノの音、音叉と色々試すと良いでしょう
-1.次、純正5度合わせです
正しく純正5度(702cent)で調弦してもらった自身の楽器で、G-D、D-A、A-Eの正しく純正5度の響きを追体験すると良いでしょう。 この響きが基準です。
この基準の響きから音を少しずつずらして唸りと響きの変化を確認してください。 同じようにゆぅっくりと唸りと響きの変化を確認しながら元の正しい響きに戻してください。 これを繰り返して定着すればよいでしょう
-2.調弦レッスンなんて言って、先生に頼んで付き合ってもらったら良いでしょう。 センスが良ければ2日か3日でざっくりと掴めますよ
※1.ポイントを絞り込んで、半音の1/4 辺りからピッタリ同音(0cent)、または、ピッタリ純正5度(702cent)になればほぼ完ぺきです。 半音の1/4あたりへは、チューナー合わせで構いませんので、そこから唸りと響きの変化を確認しながらゆぅっくりとピッタリにして下さい
※2.同音合わせでは唸りは完全に消え、その響き方と合わせて割と分かり易いです。 純正5度では唸りは完全には消えておらず純正5度の唸りが残り同音の響きとは異なりますので、この響きを最初に確認できると早いです。 また、調弦5度の基本は、純正の完全5度で、ピアノやチューナーの完全5度(平均律)ではありませんので、高い精度で純正5度を識別できることを目指してください
大変恐縮ですが、コメントから今は恐らく純正5度にもピアノの平均律5度にもなってないのでは??と思えます。 先生も、まあまあいい加減には合ってるからいいかぁ、と思ってるよう見えます。 また、そんな先生がピッタリ純正5度調弦できるようになったら、さぞ感動するでしょう
先ずペグ調整で微小な音程1centの音を調整できるようにペグを調整して下さい。 これが上手くできないなら4弦アジャスター付きのテールピースにしてください
-0.先ず開放A合わせです
基準Aの音を出してもらって、この音との重音で開放Aをピッタリ同音(0cent)にゆぅっくりとでよいので合わせて下さい。 基準Aは、弦の音、ピアノの音、音叉と色々試すと良いでしょう
-1.次、純正5度合わせです
正しく純正5度(702cent)で調弦してもらった自身の楽器で、G-D、D-A、A-Eの正しく純正5度の響きを追体験すると良いでしょう。 この響きが基準です。
この基準の響きから音を少しずつずらして唸りと響きの変化を確認してください。 同じようにゆぅっくりと唸りと響きの変化を確認しながら元の正しい響きに戻してください。 これを繰り返して定着すればよいでしょう
-2.調弦レッスンなんて言って、先生に頼んで付き合ってもらったら良いでしょう。 センスが良ければ2日か3日でざっくりと掴めますよ
※1.ポイントを絞り込んで、半音の1/4 辺りからピッタリ同音(0cent)、または、ピッタリ純正5度(702cent)になればほぼ完ぺきです。 半音の1/4あたりへは、チューナー合わせで構いませんので、そこから唸りと響きの変化を確認しながらゆぅっくりとピッタリにして下さい
※2.同音合わせでは唸りは完全に消え、その響き方と合わせて割と分かり易いです。 純正5度では唸りは完全には消えておらず純正5度の唸りが残り同音の響きとは異なりますので、この響きを最初に確認できると早いです。 また、調弦5度の基本は、純正の完全5度で、ピアノやチューナーの完全5度(平均律)ではありませんので、高い精度で純正5度を識別できることを目指してください
[56318]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月08日 09:56
投稿者:pochi(ID:mWMxVWA)
レモン娘氏、今晩は。
音感は、
「完全一度」(同音)
が最も易しいのです。
だから、先ずは「完全一度」(同音)からです。
ヴァイオリン弾きに取っては慣れている「完全五度」(調弦)の方が易しいのですが、一般人に取っては「完全八度」(オクターブ)の方が易しい。
次が「完全五度」(調弦)です。
以下の数字を覚える必要は有りません。
周波数比が夫々異なり単純な整数倍になっています。
「完全一度」=1:1
「完全八度」=1:2
「完全五度」=2:3
整数比が単純であればあるほど音として協和しやすくなっています。
少しでも狂うと唸りが出ます。←これが音で解る必要があるのです。
音感が無いのなら、
「最も易しいモノから始めましょうね」
が趣旨です。
音感は、
「完全一度」(同音)
が最も易しいのです。
だから、先ずは「完全一度」(同音)からです。
ヴァイオリン弾きに取っては慣れている「完全五度」(調弦)の方が易しいのですが、一般人に取っては「完全八度」(オクターブ)の方が易しい。
次が「完全五度」(調弦)です。
以下の数字を覚える必要は有りません。
周波数比が夫々異なり単純な整数倍になっています。
「完全一度」=1:1
「完全八度」=1:2
「完全五度」=2:3
整数比が単純であればあるほど音として協和しやすくなっています。
少しでも狂うと唸りが出ます。←これが音で解る必要があるのです。
音感が無いのなら、
「最も易しいモノから始めましょうね」
が趣旨です。
[56324]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 10:20
投稿者:松毬(ID:JRSIaRA)
音の感覚について
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]
に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]
[56317]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月08日 05:00
投稿者:松毬(ID:GScAdSY)
レモン娘 様 初めまして、おはようございます
大変恐縮ですが、コメントから今は恐らく純正5度にもピアノの平均律5度にもなってないのでは??と思えます。 先生も、まあまあいい加減には合ってるからいいかぁ、と思ってるよう見えます。 また、そんな先生がピッタリ純正5度調弦できるようになったら、さぞ感動するでしょう
先ずペグ調整で微小な音程1centの音を調整できるようにペグを調整して下さい。 これが上手くできないなら4弦アジャスター付きのテールピースにしてください
-0.先ず開放A合わせです
基準Aの音を出してもらって、この音との重音で開放Aをピッタリ同音(0cent)にゆぅっくりとでよいので合わせて下さい。 基準Aは、弦の音、ピアノの音、音叉と色々試すと良いでしょう
-1.次、純正5度合わせです
正しく純正5度(702cent)で調弦してもらった自身の楽器で、G-D、D-A、A-Eの正しく純正5度の響きを追体験すると良いでしょう。 この響きが基準です。
この基準の響きから音を少しずつずらして唸りと響きの変化を確認してください。 同じようにゆぅっくりと唸りと響きの変化を確認しながら元の正しい響きに戻してください。 これを繰り返して定着すればよいでしょう
-2.調弦レッスンなんて言って、先生に頼んで付き合ってもらったら良いでしょう。 センスが良ければ2日か3日でざっくりと掴めますよ
※1.ポイントを絞り込んで、半音の1/4 辺りからピッタリ同音(0cent)、または、ピッタリ純正5度(702cent)になればほぼ完ぺきです。 半音の1/4あたりへは、チューナー合わせで構いませんので、そこから唸りと響きの変化を確認しながらゆぅっくりとピッタリにして下さい
※2.同音合わせでは唸りは完全に消え、その響き方と合わせて割と分かり易いです。 純正5度では唸りは完全には消えておらず純正5度の唸りが残り同音の響きとは異なりますので、この響きを最初に確認できると早いです。 また、調弦5度の基本は、純正の完全5度で、ピアノやチューナーの完全5度(平均律)ではありませんので、高い精度で純正5度を識別できることを目指してください
大変恐縮ですが、コメントから今は恐らく純正5度にもピアノの平均律5度にもなってないのでは??と思えます。 先生も、まあまあいい加減には合ってるからいいかぁ、と思ってるよう見えます。 また、そんな先生がピッタリ純正5度調弦できるようになったら、さぞ感動するでしょう
先ずペグ調整で微小な音程1centの音を調整できるようにペグを調整して下さい。 これが上手くできないなら4弦アジャスター付きのテールピースにしてください
-0.先ず開放A合わせです
基準Aの音を出してもらって、この音との重音で開放Aをピッタリ同音(0cent)にゆぅっくりとでよいので合わせて下さい。 基準Aは、弦の音、ピアノの音、音叉と色々試すと良いでしょう
-1.次、純正5度合わせです
正しく純正5度(702cent)で調弦してもらった自身の楽器で、G-D、D-A、A-Eの正しく純正5度の響きを追体験すると良いでしょう。 この響きが基準です。
この基準の響きから音を少しずつずらして唸りと響きの変化を確認してください。 同じようにゆぅっくりと唸りと響きの変化を確認しながら元の正しい響きに戻してください。 これを繰り返して定着すればよいでしょう
-2.調弦レッスンなんて言って、先生に頼んで付き合ってもらったら良いでしょう。 センスが良ければ2日か3日でざっくりと掴めますよ
※1.ポイントを絞り込んで、半音の1/4 辺りからピッタリ同音(0cent)、または、ピッタリ純正5度(702cent)になればほぼ完ぺきです。 半音の1/4あたりへは、チューナー合わせで構いませんので、そこから唸りと響きの変化を確認しながらゆぅっくりとピッタリにして下さい
※2.同音合わせでは唸りは完全に消え、その響き方と合わせて割と分かり易いです。 純正5度では唸りは完全には消えておらず純正5度の唸りが残り同音の響きとは異なりますので、この響きを最初に確認できると早いです。 また、調弦5度の基本は、純正の完全5度で、ピアノやチューナーの完全5度(平均律)ではありませんので、高い精度で純正5度を識別できることを目指してください
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
[56327]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月10日 04:47
投稿者:松毬(ID:F5BiETU)
※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから殆んど無関係に近い音で、微妙なニュアンスでアピールしたストーリーになってるんじゃないかなぁぁ。 なので本筋から外れています
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]
は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]
[56314]
音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 11:39
投稿者:レモン娘(ID:KHFoB5Y)
大学生になってからバイオリンを始めた、所謂レイトスターターです。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
[56157]
Re: いろいろ職人さん、あるある
投稿日時:2025年09月21日 11:36
投稿者:松毬(ID:E2SCSA)
ネセサイト 様 コメありがとうございます (遅くなり恐縮です)
因みに、
先生バージョンにこんなンありますね。 https://youtu.be/OSCSgQBPTZU?t=76
因みに、
先生バージョンにこんなンありますね。 https://youtu.be/OSCSgQBPTZU?t=76
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
[56331]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月11日 15:26
投稿者:pochi(ID:InIHgiU)
[56324]
松毬氏、
数字はドーデモイーのですが、抜けていますよ。
(単純な)周波数比(順)
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)←③と同じ(逆数)だから不必要
③ 1:2(完全8度)
④ 3:1(完全5度※1)
⑤ 4:1(完全8度※2)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 5:4( 長3度)←抜けている
⑨ 5:3( 長6度)←抜けている
⑩ 6:5( 短3度)
ここから蛇足
⑪ 8:5( 短6度)←ここ迄が協和音とされる
⑫ 9:8( 大全音)
⑬ 9:5( 短7度)
⑭ 10:9( 小全音)
⑮ 15:8( 長7度)
⑯ 16:15( 短2度)
[56324]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 10:20
投稿者:松毬(ID:JRSIaRA)
音の感覚について
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
数字はドーデモイーのですが、抜けていますよ。
(単純な)周波数比(順)
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)←③と同じ(逆数)だから不必要
③ 1:2(完全8度)
④ 3:1(完全5度※1)
⑤ 4:1(完全8度※2)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 5:4( 長3度)←抜けている
⑨ 5:3( 長6度)←抜けている
⑩ 6:5( 短3度)
ここから蛇足
⑪ 8:5( 短6度)←ここ迄が協和音とされる
⑫ 9:8( 大全音)
⑬ 9:5( 短7度)
⑭ 10:9( 小全音)
⑮ 15:8( 長7度)
⑯ 16:15( 短2度)
[56332]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月12日 05:28
投稿者:松毬(ID:MxQ5lyY)
※1.ありがとう。しかし、まだそんなには余計です。 先々を考えると、ってのはありますけどもね。
[56324]
は、完全1度、完全5度の話の上で、しだいに音が複雑になるっていくことを図で示したにすぎません。 しかも、リンク先の図ありき、これに合わせたにすぎません
※2.ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32
そもそも論として、youtu.be/zieY5fVldeE?t=252 [56325]
はピアニカの音ではないでしょうから、根本のところで頓珍漢になるのでしょう。
特殊な音なのですが耳で聞いたとは思えず、書いてある通りチューナーで図れば【ピアニカ<オーボエ】になるから、その通り書いていて[56325]
[56019]
[54805]
[53968]
散々外してきたことになるでしょうね
◎.さて本筋では、[56327]
は純音での話ですので、[56324]
の終わりにある通り、実際のところ、つまり色んな倍音がある中での唸りや差音はどうか? もう少し掘り下げておきます。
では、次の機会に
[56324]
[56324]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 10:20
投稿者:松毬(ID:JRSIaRA)
音の感覚について
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
※2.ピアニカの音 → youtu.be/5nSo2lS8Tlw?t=32
そもそも論として、youtu.be/zieY5fVldeE?t=252 [56325]
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
特殊な音なのですが耳で聞いたとは思えず、書いてある通りチューナーで図れば【ピアニカ<オーボエ】になるから、その通り書いていて[56325]
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
[56019]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月17日 03:44
投稿者:pochi(ID:NkkZSEM)
音叉の使い方とは少し趣旨が異なりますが、
「同音が全く解らない」
人が本当に存在します。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
ピアニカ<オーボエ
ですよね。
音楽監督は瞬時に、
「これはオカシイ」
と感じられて当然ですが、感じられなかったから上梓して仕舞ったのでしょう。
この手の人は作音楽器であるヴァイオリンには先天的に向いていないので、最初から諦めた方が無難です。
多分、ですが、
「個別にチューナーで合わせたのを電気的に編集でくっ付けた」
のだと思います。
常識として差が出る事があるので、絶対にしてはならなりません。
「同音が全く解らない」
人が本当に存在します。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
ピアニカ<オーボエ
ですよね。
音楽監督は瞬時に、
「これはオカシイ」
と感じられて当然ですが、感じられなかったから上梓して仕舞ったのでしょう。
この手の人は作音楽器であるヴァイオリンには先天的に向いていないので、最初から諦めた方が無難です。
多分、ですが、
「個別にチューナーで合わせたのを電気的に編集でくっ付けた」
のだと思います。
常識として差が出る事があるので、絶対にしてはならなりません。
[54805]
Re: 調弦についての質問です。
投稿日時:2023年10月28日 17:19
投稿者:pochi(ID:NINGViU)
サクジョ承知で、
「ミーハーアニメ」
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
「ピアニカ」<「オーボエ」
です。
でも、チューナーで計ればピッタリ同じかも知れません。
もう一度、[54770]
「ミーハーアニメ」
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
「ピアニカ」<「オーボエ」
です。
でも、チューナーで計ればピッタリ同じかも知れません。
もう一度、[54770]
[53968]
Re: 再修正版ヴァイオリンの音程の取り方の基本
投稿日時:2020年03月12日 17:07
投稿者:pochi(ID:NmOIIIA)
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
こちらには前提条件が有ります。
ピッタリ和音が合っている時「差音」が聴き取れる筈です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E9%9F%B3
http://musica.art.coocan.jp/differencetone.htm
http://abcviolin.com/double-stop1/
ところが、弦が少しでも傷むと差音が聴き取りにくく成ります。
差音が聴き取れなく成った時点を弦の交換のタイミングとすると、ドミナントなら1ヶ月も保ちませんし、ガット弦だと更に短く成ります。莫大なお金が掛かると共に、弦を張ってから落ち着くのに日にちが掛かり、ドミナントならシャリシャリ音が無くなるのに1週間位です。オリーブなら調弦が落ち着くのに3日位掛かります。差音が容易に聴き取れるかどうかを弦の交換タイミングとするのは、弦を使用出来る期間が剰りに短く、現実的では有りません。
従ってピッタリの和音は音で覚える必要が有ります。
弦の交換時期は、
①「差音」が聴き取りにくく成った時
②フラジオで調弦してみて通常の五度調弦と矛盾が出て来た時
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
こちらで「イヴリー・ギトリス」がフラジオを使った調弦を行っています。
(チェロでは頻繁に行われる調弦法で、多くは金属弦だから保ちが良く、弦の交換時期の指標ともされている)
③フラジオを単音で聴いて開放弦の2倍音依も低く感じた時
④開放弦を弾いて残響が低く感じられる時
⑤発音が悪く成った時
(ドミナントなら2ヶ月以内ですが徐々に悪くなるので解りにくい)
(弦を交換した時発音が良いのでよく解る)
①②③④⑤の順で期間が長く成ります。この他、順番に関係無く弦が切れて仕舞うと交換せざるを得ませんが、当たり前なので、言う迄も無いでしょう。
個人的に、②③④の何れかを弦の交換時期にするのが現実的なのではないかな?と思っています。
このサイトは以前、音程の取り方に「生徒用ID」が必要だったのですが、無くなりました。真っ当な事が書いてあります。
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
最後が厳し過ぎます。
①の差音に対する言及をしていますが、
「A線3指D」と「E線1指Fis/F」
の最も基礎的な長短三度の重音を差音で判断するのに「ドミナントA」と「ゴールドブラカットE」で弦がどれくらい保つのかな?と考えると、ゴールドブラカットは1週間以内、ドミナントなら3週間以内でしょうか?ドミナントのシャリシャリ音が嫌いな場合、2週間足らずしか使えず、複数のヴァイオリンが必要に成ります。ヴァイオリンは個体に依って弾き味が違いますから、どう考えても非現実的です。
弦の振動の響きでは無く、楽器の響きで聴くと少しだけ弦の傷みに対して「差音」が解る耐用日数が長くは成るのですが、弦が少しでも傷むと倍音列が乱れるので、「差音」が解りにくく成る迄の日数が飛躍的に伸びるわけでは有りません。
==========
【純正律の理屈】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%BE%8B
こちらの方が私が書いたものよりも詳しくなっています。
整数比が単純で有れば有る程、和音は聴き取り易く、覚え易いのが和音です。
⑥主音1倍音に対して、
⑦長2度 9/8倍(周波数)音
⑧完全4度 4/3倍(周波数)音
⑨完全5度 3/2倍(周波数)音
⑩完全8度 2倍音
純正律、ピタゴラス律、どちらも同じで、この4つさえ合っていれば、それほど酷いオンチには聴こえない様に成っているのがヴァイオリンです。
ヴァイオリン演奏時に於ける難易度は、単純な整数比順ですが、ヴァイオリンは五度調弦なので特別で、⑨と⑩が入れ替わり、
⑥⑨⑩⑧⑦
の順に難しく成ります。
⑥の与えられた音に対する同音が解る、弾けるかどうかが、作音楽器にとっては最も大切で、基準となる楽器は、ピアノで有る事が多く、オーケストラではオーボエ、自分で弾く時には音叉を使います。
音律や音程の理屈を捏ねるのは、与えられた音とピッタリ同音で弾ける様に成ってから、にして下さい。
同音が全く解っていない例は幾らでも有ります。
https://youtu.be/qMRlX0E0QZg?t=884
ピアニカに対してオーボエが剰りに高過ぎます。
強い違和感・不快感として瞬時に感じられなければ、ヴァイオリンが弾ける様に成る可能性は有りません。
==========
鳴りを聴き取って音程を取り、重音は特に和音を意識する事そのものなのに、どれだけ罪深い指導をしているのか、良く解ります。
https://youtu.be/cODi4w1xjLk?t=120
重音の音程の練習をさせるのに、ピアノを使ってどうするんでしょう???
こちらには前提条件が有ります。
ピッタリ和音が合っている時「差音」が聴き取れる筈です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E9%9F%B3
http://musica.art.coocan.jp/differencetone.htm
http://abcviolin.com/double-stop1/
ところが、弦が少しでも傷むと差音が聴き取りにくく成ります。
差音が聴き取れなく成った時点を弦の交換のタイミングとすると、ドミナントなら1ヶ月も保ちませんし、ガット弦だと更に短く成ります。莫大なお金が掛かると共に、弦を張ってから落ち着くのに日にちが掛かり、ドミナントならシャリシャリ音が無くなるのに1週間位です。オリーブなら調弦が落ち着くのに3日位掛かります。差音が容易に聴き取れるかどうかを弦の交換タイミングとするのは、弦を使用出来る期間が剰りに短く、現実的では有りません。
従ってピッタリの和音は音で覚える必要が有ります。
弦の交換時期は、
①「差音」が聴き取りにくく成った時
②フラジオで調弦してみて通常の五度調弦と矛盾が出て来た時
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
こちらで「イヴリー・ギトリス」がフラジオを使った調弦を行っています。
(チェロでは頻繁に行われる調弦法で、多くは金属弦だから保ちが良く、弦の交換時期の指標ともされている)
③フラジオを単音で聴いて開放弦の2倍音依も低く感じた時
④開放弦を弾いて残響が低く感じられる時
⑤発音が悪く成った時
(ドミナントなら2ヶ月以内ですが徐々に悪くなるので解りにくい)
(弦を交換した時発音が良いのでよく解る)
①②③④⑤の順で期間が長く成ります。この他、順番に関係無く弦が切れて仕舞うと交換せざるを得ませんが、当たり前なので、言う迄も無いでしょう。
個人的に、②③④の何れかを弦の交換時期にするのが現実的なのではないかな?と思っています。
このサイトは以前、音程の取り方に「生徒用ID」が必要だったのですが、無くなりました。真っ当な事が書いてあります。
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
最後が厳し過ぎます。
①の差音に対する言及をしていますが、
「A線3指D」と「E線1指Fis/F」
の最も基礎的な長短三度の重音を差音で判断するのに「ドミナントA」と「ゴールドブラカットE」で弦がどれくらい保つのかな?と考えると、ゴールドブラカットは1週間以内、ドミナントなら3週間以内でしょうか?ドミナントのシャリシャリ音が嫌いな場合、2週間足らずしか使えず、複数のヴァイオリンが必要に成ります。ヴァイオリンは個体に依って弾き味が違いますから、どう考えても非現実的です。
弦の振動の響きでは無く、楽器の響きで聴くと少しだけ弦の傷みに対して「差音」が解る耐用日数が長くは成るのですが、弦が少しでも傷むと倍音列が乱れるので、「差音」が解りにくく成る迄の日数が飛躍的に伸びるわけでは有りません。
==========
【純正律の理屈】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%94%E6%AD%A3%E5%BE%8B
こちらの方が私が書いたものよりも詳しくなっています。
整数比が単純で有れば有る程、和音は聴き取り易く、覚え易いのが和音です。
⑥主音1倍音に対して、
⑦長2度 9/8倍(周波数)音
⑧完全4度 4/3倍(周波数)音
⑨完全5度 3/2倍(周波数)音
⑩完全8度 2倍音
純正律、ピタゴラス律、どちらも同じで、この4つさえ合っていれば、それほど酷いオンチには聴こえない様に成っているのがヴァイオリンです。
ヴァイオリン演奏時に於ける難易度は、単純な整数比順ですが、ヴァイオリンは五度調弦なので特別で、⑨と⑩が入れ替わり、
⑥⑨⑩⑧⑦
の順に難しく成ります。
⑥の与えられた音に対する同音が解る、弾けるかどうかが、作音楽器にとっては最も大切で、基準となる楽器は、ピアノで有る事が多く、オーケストラではオーボエ、自分で弾く時には音叉を使います。
音律や音程の理屈を捏ねるのは、与えられた音とピッタリ同音で弾ける様に成ってから、にして下さい。
同音が全く解っていない例は幾らでも有ります。
https://youtu.be/qMRlX0E0QZg?t=884
ピアニカに対してオーボエが剰りに高過ぎます。
強い違和感・不快感として瞬時に感じられなければ、ヴァイオリンが弾ける様に成る可能性は有りません。
==========
鳴りを聴き取って音程を取り、重音は特に和音を意識する事そのものなのに、どれだけ罪深い指導をしているのか、良く解ります。
https://youtu.be/cODi4w1xjLk?t=120
重音の音程の練習をさせるのに、ピアノを使ってどうするんでしょう???
◎.さて本筋では、[56327]
[56327]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月10日 04:47
投稿者:松毬(ID:F5BiETU)
※ちなみにピアニカは、オクターブ上のEだから殆んど無関係に近い音で、微妙なニュアンスでアピールしたストーリーになってるんじゃないかなぁぁ。 なので本筋から外れています
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
さてネタばらし
A合わせの完全1度では、唸りの響きを見るのでよいです
しかし、バイオリンの完全5度調弦では、もはや唸りとは言わず「差音」と言い、第三の音とも云います。
改めて言って、完全5度は、重音による「差音」を含めた三つの音が協和する点を取り、完全5度調弦では、三つの音が協和した響き(和音)に調整します。
例えば、次リンク先に書かれてる通りです。
https://www.256paga252.com/ヴァイオリンの正しい調弦方法-バイオリンの正しいチューニング/
http://www1.ttcn.ne.jp/~paga252/intonation.htm
申し訳ないですが、レモン娘 様の次[56314]は当たり前です。 ズバリ唸りのイメージだけでは一生やってもわかりません。 そんな先生なら、いいように誹謗中傷の的に育てられ、飼い殺しの弟子にされて果ては身の回りの世話までさせられれますよ[56157]
「完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず」
[56324]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 10:20
投稿者:松毬(ID:JRSIaRA)
音の感覚について
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
音の物理的な正体は、空気などの振動のことです。 この一方で音は哲学的な命題で扱われ思惟する(知性や心の働きで捉える)ものです
1)音の振動について
一般的に耳で捉える振動です。(場合によっては皮膚などでも捉えられます)
物を叩いたり擦ったりして発する音、人の声にも色んな音の成分の振動周波数が含まれています。 この音の成分の違いで、音程、音色や響き方の違いを感じ取っています。 この内、今ここでは音程の成分(の周波数)に着目して音程を合わせようとしている訳です
純音は、単純に一つの周波数成分だけのサインカーブの音だけで、音程、音色や響き方が示され、この他の音程、音色や響き方の成分がありません。 ほぼ純音に音叉があり、他にも、時報(440Hzと880Hz)、深夜のTV試験放送(1kHz)が知られます
二つの純音の同一周波数(①完全1度)での共鳴は、最も分かり易い物理現象です。
周波数の違う純音A、A'の二つを重ね、A'の周波数をAに近くつけ一致した時(A=A')に同音となります。 近ずくにつれて周波数差に等しい唸りが緩やかに完全に"0"なり、二つの音の振動の干渉も全く無くAの響きは二つの音源により良い響きに感じられます。 俄かに音量はAの2倍に至ります
他にも、二つの純音の周波数比が簡単な整数比で、似た様な共鳴があります。
これらビジュアル的に示したものにリサージュ図が知られます https://ys-blog.hatenablog.com/entry/2018/03/04/230716 このリンク先では1行目から下へ
周波数比
① 1:1(完全1度)
② 2:1(完全8度)
③ 3:1(完全5度※1)
④ 4:1(完全8度※2)
⑤ 1:2(完全8度)
⑥ 3:2(完全5度)
⑦ 4:3(完全4度)
⑧ 6:5( 短3度)
⑨√2:1 ( - )
※1,オクターブ上の5度(12度)、※2,オクターブ上の8度(15度)
同先1列目から右へ 位相:0°22.5°45°67.5°90°112.5°135°157.5°180°反転して、角度を変えて見るものです。 先ずは0°で見れば良く、更に90°や45°など角度を変えて掘り下げます
このリサージュ図では、①→④へ従って複雑になり、また①(完全1度)、②と⑤(完全8度)、③と⑥(完全5度)、⑦(完全4度)、⑧の順に複雑になります。 つまり共鳴するものの響き方は複雑になります。 これに応じた周波数差に等しい唸りを持ちますが、共鳴時はこの唸りは音源周波数と共鳴しており識別できなくなります。 共鳴とは、周波数差による唸りが元の音二つと共鳴関係になると言って過言ではありません
例えば、
② 2:1(完全8度)、880Hz:440Hzでは、周波数差440Hzで唸りますが元の音Aと同音関係(ズレ"0")にあり唸りとしては通常は全く識別できません。 これは上であげた①の場合に非常に似ています
2A' 882 881 880 879 878 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 442 441 440 439 438 ↘
ズレ (2) (1) (0) (1) (2) V
2A 880 880 880 880 880 -
A' 442 441 440 439 438 ↘
唸り 438 439 440 441 442 ↗
ズレ (4) (2) (0) (2) (4) V
⑥ 3:2(完全5度)、
660Hz:440Hz(E-A)では、周波数差220Hzで唸りますが元の二つの音と、2倍音3倍音での共鳴関係にあり恰も消えた様に感じます。 しかし、この響きは、E-Aの他にオクターブ下のAの音を聴くことが出来ます
E 662 661 660 659 658 ↘
A 440 440 440 440 440 -
唸り 222 221 220 219 218 ↘
ズレ (218) (219) (220) (221) (222) ↗
440Hz:293.33Hz(A-D)では、周波数差146.67Hzで唸りますが同様に2倍音3倍音での共鳴関係にあり、A-Dの他にオクターブ下のDの音を聴くことが出来ます
A 440 440 440 440 440 -
D 295.3 294.3 293.3 292.3 291.3 ↘
唸り 144.7 145.7 146.7 147.7 148.7 ↗
ズレ (146.7)(148.7) (146.7)(144.7)(142.7) ↘↘
293.34Hz:195.56Hz(D-G)では、周波数差97.77Hzで唸りますが上同様です。 D-Gの他にオクターブ下のGの音を聴くことが出来ます
D 293.3 293.3 293.3 293.3 293.3 -
G 197.5 196.5 195.5 194.5 193.5 ↘
唸り 95.8 96.8 97.8 98.8 99.8 ↗
ズレ (101.8) ( 99.8) ( 97.8) ( 95.8) ( 93.8) ↘↘
以上の通りで、唸りと言ってもバイオリンの5度ではイメージとは異なり可なりの高周波なのであまり分からないのが現実です。 他にも上らは純音で音程成分だけをとり出した格好ですが、実際に楽器を用いた場合は、音程成分以外の周波数も沢山混ざっており、その中で純正5度の調弦をすることは、実はかなり難易度が高い仕事になります。 高度なことに取り組んでいると思って良いでしょう。
また、実際のところは、唸りそのものよりも響き方を見ています。 唸りは上で示したオクターブ下の音を示し、この唸りを含めた三つの音の干渉が消えるところが共鳴する点ですから、この共鳴の響きを探します。 特に、純正5度では[56317]に示した通り、 最初に純正5度の共鳴の響きを体験した上で覚えることが大切です。 そこからズレるとどうなるのか?ズレたところから共鳴の響きに戻れるようして下さい
なお、次を完全協和音程と言います
完全1度、完全8度 → 特別に、絶対協和音程
完全5度、完全4度、
その中でも上の通り同音関係が取れる完全1度、完全8度は、絶対協和音程と言い、この点が物理理論と音楽理論を結ぶ最初の結節点であり、また、音楽理論の基本の基礎の根柢に絶対協和音程があります。
演奏をする上でも、とても大切な出発点です。 ここに開放A合わせから取り組む意味がありますので、ガンバって下さいね
では、次の機会に
ヴァイオリン掲示板に戻る
1 / 4 ページ [ 32コメント ]