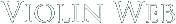不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[54964]
音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年04月05日 18:00
投稿者:松毬(ID:RDJJSGA)
名も知れない工房製の楽器やスズキやピグマリウスなどの工業製品で音大受験やご卒業した方などは本当に存在しないのか??
音大あるある??なのか、音大都市伝説か??ちょっと気になるところです。[54959]
のご意見もあり、また、音大に進むのに良い楽器の方が有利なのは確かにあり、少し前まではオールドのコンポジットやイタリアンモダンの楽器が当たり前のように用いていると聞こえました。ですが、最近では必ずしもそうでもない話も聞こえるような?ないような?
そこで、ありふれた名も知れない工房製の楽器やスズキやピグマリウスなどの工業製品では音大に進めないのか??皆さまに改めて尋ねてみたいと思います。
例えば、桐朋はイタリアンモダンが当たり前かのようですが、芸大では新作イタリアンですらない楽器を用いている方も多いようです。フレンチモダンならまだ良いようですが、では、どの程度の楽器で音大に進まれているのでしょうか??
音大あるある??なのか、音大都市伝説か??ちょっと気になるところです。[54959]
[54959]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年04月04日 14:48
投稿者:通りすがり(ID:MTNXeZM)
結局用途次第かなと思います。
音大受験などには不足してしまうかもしれません。
イタリア製は特に価格が高騰しているので、下手な200万円の楽器より性能が良い可能性はあると思います。
音大受験などには不足してしまうかもしれません。
イタリア製は特に価格が高騰しているので、下手な200万円の楽器より性能が良い可能性はあると思います。
そこで、ありふれた名も知れない工房製の楽器やスズキやピグマリウスなどの工業製品では音大に進めないのか??皆さまに改めて尋ねてみたいと思います。
例えば、桐朋はイタリアンモダンが当たり前かのようですが、芸大では新作イタリアンですらない楽器を用いている方も多いようです。フレンチモダンならまだ良いようですが、では、どの程度の楽器で音大に進まれているのでしょうか??
ヴァイオリン掲示板に戻る
3 / 4 ページ [ 34コメント ]
【ご参考】
[55065]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年05月12日 23:40
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
かにさん ありがとうございます。
痛たたたぁ、その通りです。それだけ見れば、ただ国際でイメージが良いだけです。でもね、高松あいさんは、小林美樹さんとの比較の意味では、結果的に小林美樹さんのヘンリク2位と同じ価値をもつことになります。
国際コンクールは、その副賞に大きな意味があり、1位であればヘンリク国際はストラドの名器貸与、オケをバックにヨーロッパツアーが組まれており、ここで更なる飛躍をもって、国際プロバイオリニストとしてデビューできます。
留学もしたものの小林美樹さんは惜しくも2位に甘んじ、ほか国際で1位をとっていない結果、国内では知名度が上がりプロデビューしたものの活動はほとんど国内に留まるのが現実です。姉のプロピアニスト小林有沙とのDuoなどありますが、活動は制約的です。
ブルクハルト国際では、副賞は海外音楽院などの留学です。このコンクールは概ね日本人で競われ、更なる海外研鑽のサポートへ、ヘンリク国際などでの1位を目指す道に進めるものです。この道を蹴った高松あいちゃんは、ヘロヘロ
https://youtu.be/HssBQnh6PI4 続 https://youtu.be/Ijj28TX7Q0w な子なんだけど、根っからの芸人でSNS活動の結果、国内プロバイオリニストの地位を確保しました。
ただ、これで留まるのか?更に伸びて国際派に成長できるかが、今後の分かれ道になりますね。モダンの貸与も受けたし金も稼いだようなので、改めて留学して国際コンクールで1位を狙ったらいいんじゃないかな。。
痛たたたぁ、その通りです。それだけ見れば、ただ国際でイメージが良いだけです。でもね、高松あいさんは、小林美樹さんとの比較の意味では、結果的に小林美樹さんのヘンリク2位と同じ価値をもつことになります。
国際コンクールは、その副賞に大きな意味があり、1位であればヘンリク国際はストラドの名器貸与、オケをバックにヨーロッパツアーが組まれており、ここで更なる飛躍をもって、国際プロバイオリニストとしてデビューできます。
留学もしたものの小林美樹さんは惜しくも2位に甘んじ、ほか国際で1位をとっていない結果、国内では知名度が上がりプロデビューしたものの活動はほとんど国内に留まるのが現実です。姉のプロピアニスト小林有沙とのDuoなどありますが、活動は制約的です。
ブルクハルト国際では、副賞は海外音楽院などの留学です。このコンクールは概ね日本人で競われ、更なる海外研鑽のサポートへ、ヘンリク国際などでの1位を目指す道に進めるものです。この道を蹴った高松あいちゃんは、ヘロヘロ
https://youtu.be/HssBQnh6PI4 続 https://youtu.be/Ijj28TX7Q0w な子なんだけど、根っからの芸人でSNS活動の結果、国内プロバイオリニストの地位を確保しました。
ただ、これで留まるのか?更に伸びて国際派に成長できるかが、今後の分かれ道になりますね。モダンの貸与も受けたし金も稼いだようなので、改めて留学して国際コンクールで1位を狙ったらいいんじゃないかな。。
[55066]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年05月13日 12:33
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
ところで、高松あいさんは、自らこじつけてプロデュースした東京芸大卒業ツアーを成功させており特殊な存在です。
確か、副賞のコンサートツアーを蹴った話しではチャイコフスキー国際 1位の諏訪内晶子さんがおり、未だ大学生だったためですが、難しく有名なチャイコフスキー国際、エリザベート王妃国際音楽、ジュネーヴ国際音楽、パブロ・サラサーテ国際バイオリン、パガニーニ国際、ロン・ティボー国際、ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際の内、日本人で完全2冠に最も近しい方としても知られています。3冠にも近しいほどで他にはおらず、クラシックの王道的トップトレンドになります。
諏訪内晶子
パガニーニ国際 2位、エリザベート王妃国際音楽 2位、日本国際音楽 2位、チャイコフスキー国際(出場最年少)1位
川久保賜紀
パブロ・サラサーテ国際 1位、チャイコフスキー国際 2位(1位なし)
有希・マヌエラ・ヤンケ
パガニーニ国際 2位(1位なし)、パブロ・サラサーテ国際 1位
樫本大進
ユーディ・メニューイン国際コンクール・ジュニア部門 1位、ケルン国際バイオリン 1位、フリッツ・クライスラー国際 1位、ロン・ティボー国際(史上最年少)1位
確か、副賞のコンサートツアーを蹴った話しではチャイコフスキー国際 1位の諏訪内晶子さんがおり、未だ大学生だったためですが、難しく有名なチャイコフスキー国際、エリザベート王妃国際音楽、ジュネーヴ国際音楽、パブロ・サラサーテ国際バイオリン、パガニーニ国際、ロン・ティボー国際、ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際の内、日本人で完全2冠に最も近しい方としても知られています。3冠にも近しいほどで他にはおらず、クラシックの王道的トップトレンドになります。
諏訪内晶子
パガニーニ国際 2位、エリザベート王妃国際音楽 2位、日本国際音楽 2位、チャイコフスキー国際(出場最年少)1位
川久保賜紀
パブロ・サラサーテ国際 1位、チャイコフスキー国際 2位(1位なし)
有希・マヌエラ・ヤンケ
パガニーニ国際 2位(1位なし)、パブロ・サラサーテ国際 1位
樫本大進
ユーディ・メニューイン国際コンクール・ジュニア部門 1位、ケルン国際バイオリン 1位、フリッツ・クライスラー国際 1位、ロン・ティボー国際(史上最年少)1位
[55074]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年05月15日 12:13
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
話を戻して、トレンドトップでストラドを音大で使う場合は置いといて
https://youtu.be/trUtfosRNgs?t=50 では、
新作イタリアでもモダンイタリアやガダニーニの音と取り違えたり、
https://youtu.be/TQUxLzUMo6I?t=537 では、
スズキでも、モダンイタリアの様な音に聞こえたり、ストラドでも、モダンイタリアやスズキの音に聞こえたりするので、スズキでも結構いけたりするかなぁと思いますが、、、、、
この様な実話は、音大で使う楽器では本当にないのでしょうか??
ただ、動画のスズキはS550だから、10series辺りでどうかなぁと思いますが。。。
https://youtu.be/trUtfosRNgs?t=50 では、
新作イタリアでもモダンイタリアやガダニーニの音と取り違えたり、
https://youtu.be/TQUxLzUMo6I?t=537 では、
スズキでも、モダンイタリアの様な音に聞こえたり、ストラドでも、モダンイタリアやスズキの音に聞こえたりするので、スズキでも結構いけたりするかなぁと思いますが、、、、、
この様な実話は、音大で使う楽器では本当にないのでしょうか??
ただ、動画のスズキはS550だから、10series辺りでどうかなぁと思いますが。。。
[55246]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年06月25日 04:22
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
最近、ひろった話です
[23591]
音大生、講師の持つ楽器の相場
↑では、素人は50万円で満足か?音大生は200万~相場?などありますが??
・50万円の楽器で頑張った音大2年生さん
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1050896045
・学生時代に、2万円とか10万円とか楽器を使ったN響の1stバイオリニストさんの
https://togetter.com/li/2262940
[23591]
[23591]
音大生、講師の持つ楽器の相場
投稿日時:2005年10月10日 13:57
投稿者:とくめい(ID:OJCEhVM)
値段が全てでないのは承知です。
相場を教えて下さい。
素人は「50万円で満足する人が多い」のも本当でしょうか?
200万までなら出せるのですが、お薦めがあれば教えて下さい。
相場を教えて下さい。
素人は「50万円で満足する人が多い」のも本当でしょうか?
200万までなら出せるのですが、お薦めがあれば教えて下さい。
↑では、素人は50万円で満足か?音大生は200万~相場?などありますが??
・50万円の楽器で頑張った音大2年生さん
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1050896045
・学生時代に、2万円とか10万円とか楽器を使ったN響の1stバイオリニストさんの
https://togetter.com/li/2262940
[55251]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年06月25日 12:07
投稿者:通りすがり(ID:JgkgMSU)
神尾真由子さんが新作楽器を試奏する動画を拝見しましたが、当たり前ですが私などが同じ作者の楽器を触ったときとは次元の違う楽器かと思われるような音量・音色の幅を披露されていました。限度はあると思いますが、それなりの楽器であれば後は演奏者の腕次第という人がいてもおかしくはないなと思いました。
ただ、性能の高い楽器を演奏すると色々な気づきが得られるというのも確かなことなので、良い楽器を色々と試せるのはよいことだと思います。
ただ、性能の高い楽器を演奏すると色々な気づきが得られるというのも確かなことなので、良い楽器を色々と試せるのはよいことだと思います。
[55265]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年06月28日 13:06
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
https://www.instagram.com/kamiomayuko/reel/C2zd6PbPiL1/ ですなぁ?
バイオリンの演奏をちゃんと知ってるってことですね。 知ってるのと否では天と地ほど違います
鈴木鎮一は、スズキ・メソードでも『音は腕前にある』と言うようです
[55238]
https://meigaku.repo.nii.ac.jp/record/2526/files/A33_text.pdf(p.95/149pdf)
知らないと困難、知ってるとこんなんです[54233]
https://youtu.be/TgX73hN40VI
やってる藤原望さんお気に入りみたい。 https://www.nozomiviolin.com/
知らないってなると、さぁ大変で、先生にも楽器にも大変一所懸命に学ばなきゃ、分って知ってることに成れませんからねぇw もう大変です。 しかも、職人とかの徒弟制度[55258]
と同じだから、何をいつまでどうすればいいか分からないうちに辞めちゃうからねぇw 見通しよくないとダメです。 楽器の問題ではないわけです
バイオリンの演奏をちゃんと知ってるってことですね。 知ってるのと否では天と地ほど違います
鈴木鎮一は、スズキ・メソードでも『音は腕前にある』と言うようです
[55238]
[55238]
Re: スズキ・メソード
投稿日時:2024年06月22日 02:48
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
鈴木鎮一と才能教育――その形成史と本質の解明 明治学院大学機関リポジトリ
https://meigaku.repo.nii.ac.jp/record/2526/files/A33_text.pdf
『現在の才能教育において指摘されている問指摘されている問題点を踏まえ、「鈴木鎮一の才能教育」の本質の解明を図る』とある
要は、周りの者が、子供のやる気を引き出して、子自らの欲求で芸術的探究へ向かう心と行動姿勢を躾ける手法のようです
《第四章 結論より抜粋》
子どもに芸術を学び追求する心を教え、育てること、更に、子ども自身が人格・感覚・能力ともに優れた人物を目指していくことを目的とした「芸術教育」なのである。 家庭や指導者は、子どもの「感覚」「心の在り方と働き」「日常の起居」などにも目を向けて教育を行う必要が出てくる
家庭の者が我が子のための教育を研究し、工夫するということは、まさに母国語教育の形である。 その家庭に教育を委ねられた「鈴木鎮一の才能教育」における教育の形は、各家庭の生活習慣、あるいは国、文化、伝統などの中で、それぞれに合う形で適宜考案され、構築されていく。 子どもの気持ちの変化や成長のタイミングに合わせた適格な指導を行うことで、強いられることのない自然な欲求から子どもが音楽を学ぶように導くのである
音楽教育の形式を持たない教育として展開するならば、ヴァイオリン教育において鈴木が提案した十六分音符から開始する練習法に代わるもの、つまり、その分野における「易しいもの」とは何なのかという発見と、方法の開発が行われ、その上で他分野に転用できるのかどうかを検証する必要があるだろう
例えば、「暗記(譜)と反復」をメソード(方法)として定めることは、他分野に応用するためには有用であろう。 しかし、「暗記(譜)と反復」は「鈴木鎮一の才能教育」における「方法」の部分的な側面でしかなく、理解を誤れば、「早教育と訓練主義」への傾倒という問題を容易に引き起こしてしまう
https://meigaku.repo.nii.ac.jp/record/2526/files/A33_text.pdf
『現在の才能教育において指摘されている問指摘されている問題点を踏まえ、「鈴木鎮一の才能教育」の本質の解明を図る』とある
要は、周りの者が、子供のやる気を引き出して、子自らの欲求で芸術的探究へ向かう心と行動姿勢を躾ける手法のようです
《第四章 結論より抜粋》
子どもに芸術を学び追求する心を教え、育てること、更に、子ども自身が人格・感覚・能力ともに優れた人物を目指していくことを目的とした「芸術教育」なのである。 家庭や指導者は、子どもの「感覚」「心の在り方と働き」「日常の起居」などにも目を向けて教育を行う必要が出てくる
家庭の者が我が子のための教育を研究し、工夫するということは、まさに母国語教育の形である。 その家庭に教育を委ねられた「鈴木鎮一の才能教育」における教育の形は、各家庭の生活習慣、あるいは国、文化、伝統などの中で、それぞれに合う形で適宜考案され、構築されていく。 子どもの気持ちの変化や成長のタイミングに合わせた適格な指導を行うことで、強いられることのない自然な欲求から子どもが音楽を学ぶように導くのである
音楽教育の形式を持たない教育として展開するならば、ヴァイオリン教育において鈴木が提案した十六分音符から開始する練習法に代わるもの、つまり、その分野における「易しいもの」とは何なのかという発見と、方法の開発が行われ、その上で他分野に転用できるのかどうかを検証する必要があるだろう
例えば、「暗記(譜)と反復」をメソード(方法)として定めることは、他分野に応用するためには有用であろう。 しかし、「暗記(譜)と反復」は「鈴木鎮一の才能教育」における「方法」の部分的な側面でしかなく、理解を誤れば、「早教育と訓練主義」への傾倒という問題を容易に引き起こしてしまう
知らないと困難、知ってるとこんなんです[54233]
[54233]
Re: 弾き込み効果って??、、なにゆえおきる?
投稿日時:2021年06月04日 12:58
投稿者:松毬(ID:NgIgmVA)
別の方向へ、上手い奏者が楽器の特徴に合わせて弾き方を変えて弾き込んで上手くなる説はありそうな感じがしますね。
上手な奏者は、バイオリンの楽器なの?か解らない(V.S.O)ような下手でも、バイオリンの音を出すように演奏を変えていきますね。。それが、エントリー楽器なら、弾き込んでなおさらちゃんとバイオリンの音を出すようですね。
また、この手の楽器は、演奏の技術攻略への練習マシンなのか?とも思えます。ただ、経年効果も、大きいなぁと思いました。
※トークではなく演奏部の音を聞いてくださいね。
Ⅰ) V.S.O(violin shaped object)
〇号板目ポンタ https://www.youtube.com/watch?v=TgX73hN40VI
①号白木 https://www.youtube.com/watch?v=gcMum0Qs5QE
②号薄緑 https://www.youtube.com/watch?v=1KeJAz-sRfI
③号楽天 https://www.youtube.com/watch?v=bBj5JDtQmNc
④号小泉 https://www.youtube.com/watch?v=hTEJtP9Kgxo
Ⅱ) バイオリン
1).S230(島モ) https://www.youtube.com/watch?v=zidrueUUj1g
2).S280(Test) https://www.youtube.com/watch?v=7k-YLelLLRM
3).S330(Test) https://www.youtube.com/watch?v=aE3KPaDItYg
4).S360(Test) https://www.youtube.com/watch?v=fcZrunRVUBU
5).P-02(島デ) https://www.youtube.com/watch?v=nzU0E-aqN7w
6).S540(島デ) https://www.youtube.com/watch?v=ibRSjXOsRPg
A).番外1 https://www.youtube.com/watch?v=iV6ha9ARwX0
番外2 https://www.youtube.com/watch?v=3nqIPLA_BOQ
なお、別にS520番(b1990)を1年ほど試して、丁度昨日、別のS540番(b1996)と交換しました。
この辺り、必ず「破れ太鼓やオバさんの声」になるのか、上手な奏者にはその様になく、また、弾いた感じは「破れ太鼓やオバさんの声」とも言えず、その様な傾向もあるという感じでしょうかね。
S540番(b1996)に付いてた弓S200番は、少しバランスが良くて、ブラジルウッドでも響きの相性は良いのですが、ただ、より良い弓では、音色が綺麗になりました。S540番(b1996)は、量産でも見た目が良く美しいので日常使いして響きが良くなるか見たいなぁと思いました。今の響きは数年前に試弾したS1200番に通じて特に悪い訳ではありません。
だた、もともとは響きが良いと思ったのは S520番(b1990)の方で、加工細部の性格も異なり作者は違う感じですね。。然り、マリオG,ガエタノG等には及ばないでしょうけども。。
上手な奏者は、バイオリンの楽器なの?か解らない(V.S.O)ような下手でも、バイオリンの音を出すように演奏を変えていきますね。。それが、エントリー楽器なら、弾き込んでなおさらちゃんとバイオリンの音を出すようですね。
また、この手の楽器は、演奏の技術攻略への練習マシンなのか?とも思えます。ただ、経年効果も、大きいなぁと思いました。
※トークではなく演奏部の音を聞いてくださいね。
Ⅰ) V.S.O(violin shaped object)
〇号板目ポンタ https://www.youtube.com/watch?v=TgX73hN40VI
①号白木 https://www.youtube.com/watch?v=gcMum0Qs5QE
②号薄緑 https://www.youtube.com/watch?v=1KeJAz-sRfI
③号楽天 https://www.youtube.com/watch?v=bBj5JDtQmNc
④号小泉 https://www.youtube.com/watch?v=hTEJtP9Kgxo
Ⅱ) バイオリン
1).S230(島モ) https://www.youtube.com/watch?v=zidrueUUj1g
2).S280(Test) https://www.youtube.com/watch?v=7k-YLelLLRM
3).S330(Test) https://www.youtube.com/watch?v=aE3KPaDItYg
4).S360(Test) https://www.youtube.com/watch?v=fcZrunRVUBU
5).P-02(島デ) https://www.youtube.com/watch?v=nzU0E-aqN7w
6).S540(島デ) https://www.youtube.com/watch?v=ibRSjXOsRPg
A).番外1 https://www.youtube.com/watch?v=iV6ha9ARwX0
番外2 https://www.youtube.com/watch?v=3nqIPLA_BOQ
なお、別にS520番(b1990)を1年ほど試して、丁度昨日、別のS540番(b1996)と交換しました。
この辺り、必ず「破れ太鼓やオバさんの声」になるのか、上手な奏者にはその様になく、また、弾いた感じは「破れ太鼓やオバさんの声」とも言えず、その様な傾向もあるという感じでしょうかね。
S540番(b1996)に付いてた弓S200番は、少しバランスが良くて、ブラジルウッドでも響きの相性は良いのですが、ただ、より良い弓では、音色が綺麗になりました。S540番(b1996)は、量産でも見た目が良く美しいので日常使いして響きが良くなるか見たいなぁと思いました。今の響きは数年前に試弾したS1200番に通じて特に悪い訳ではありません。
だた、もともとは響きが良いと思ったのは S520番(b1990)の方で、加工細部の性格も異なり作者は違う感じですね。。然り、マリオG,ガエタノG等には及ばないでしょうけども。。
やってる藤原望さんお気に入りみたい。 https://www.nozomiviolin.com/
知らないってなると、さぁ大変で、先生にも楽器にも大変一所懸命に学ばなきゃ、分って知ってることに成れませんからねぇw もう大変です。 しかも、職人とかの徒弟制度[55258]
[55258]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2024年06月27日 06:07
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
訂正 " Series "です
P.S.
梅雄社長は秩を育てて、秩社長は職人を育てたが、職人が職人を育てることができなかった
'60年代に、梅雄社長は、秩を社長にすべく秩に梅雄の楽器製作をさせ販売しています。 これは政吉が梅雄にしたことを、秩にしています。 秩は、'71年に社長になると、ビオラ製作し販売へ進むと一転して'70年代半ばより職人を育てます。 (∴秩は、チェロ製作し販売はしない)
ですが、'90~'00年代に、ご指摘の通り職人が後進を育てることが出来なかった様ですね。 楽器製作では、スズキ・メソード[55238][55239]が機能しなかったのでしょう。 社長が、工場制手工品の製作を引っ張るのではなく、分業ライン体制の中で職人修行の世界では良くありがちでしょう
これからは対応しなきゃ、ってヤツですね
P.S.
梅雄社長は秩を育てて、秩社長は職人を育てたが、職人が職人を育てることができなかった
'60年代に、梅雄社長は、秩を社長にすべく秩に梅雄の楽器製作をさせ販売しています。 これは政吉が梅雄にしたことを、秩にしています。 秩は、'71年に社長になると、ビオラ製作し販売へ進むと一転して'70年代半ばより職人を育てます。 (∴秩は、チェロ製作し販売はしない)
ですが、'90~'00年代に、ご指摘の通り職人が後進を育てることが出来なかった様ですね。 楽器製作では、スズキ・メソード[55238][55239]が機能しなかったのでしょう。 社長が、工場制手工品の製作を引っ張るのではなく、分業ライン体制の中で職人修行の世界では良くありがちでしょう
これからは対応しなきゃ、ってヤツですね
[55266]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年06月28日 13:32
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
訂正: 知ってるとこんなんです。https://youtu.be/tGj19u3icRs
[55270]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年06月30日 12:26
投稿者:通りすがり(ID:KSMjBlM)
私が見たのはこちらの動画です。
https://youtu.be/kG7h1ADaSD8?si=UN1OQEsy3u6XxwDf
https://youtu.be/kG7h1ADaSD8?si=UN1OQEsy3u6XxwDf
[55272]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年06月30日 22:45
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
失礼しました。 新作バイオリン違いでした
他にも動画、Anastasiya Petryshak / Lena Yokoyama / 伊藤黎 演奏、あるので参考に
Stefano Trabucchi : www.youtube.com/watch?v=o_AyQRsw8zk
Hiroshi Kikuta : www.youtube.com/watch?v=a7vdITRG84w
www.youtube.com/watch?v=Ewo1_HUbRK4
Riccardo Bergonzi : www.youtube.com/watch?v=WISBWYUlwCI
Davide Sora / Elisa Gaboardi / Lorenzo Cassi / Takaomi Shibata /
: www.youtube.com/watch?v=Agj1XZ_TUfI
他にも動画、Anastasiya Petryshak / Lena Yokoyama / 伊藤黎 演奏、あるので参考に
Stefano Trabucchi : www.youtube.com/watch?v=o_AyQRsw8zk
Hiroshi Kikuta : www.youtube.com/watch?v=a7vdITRG84w
www.youtube.com/watch?v=Ewo1_HUbRK4
Riccardo Bergonzi : www.youtube.com/watch?v=WISBWYUlwCI
Davide Sora / Elisa Gaboardi / Lorenzo Cassi / Takaomi Shibata /
: www.youtube.com/watch?v=Agj1XZ_TUfI
[56165]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2025年09月23日 08:38
投稿者:松毬(ID:QWASIGc)
先日クラシックTVは、幸田延のバイオリンソナタを取り上げました[56116]
[56134]
。 19世紀末ごろ楽器はこんな[54991]
感じで延はアマティも使ったらしい。 その後、東京音楽学校では1920年ごろ多くは国産のスズキ政吉を使ったハズで、そんな中、宮本金八が登場しました。 (スズキ政吉→宮本金八→キングジョージⅢへと神話もありますが、、、)
[56003]
[56073]
で取り上げた Lutherie Vosgienne は、1910年ごろ~20年ごろにJ.T.L.が大学の教育学部生や音高,音大生と高等教育機関などに向けてと謳って販売した楽器です。
この楽器は、上のスズキ政吉よりも全然良くて、もしかしたら1980年代のエターナル、ヘリテージよりも良いかも知れません。 J.T.L全体でも今のスズキよりも良いのでは?と思えるくらいですので、、、。 この辺りの楽器なら、ザクソニー/シェーンバッハ(ブーベンロイトら)[56139]
[56141]
の量産でも同じことです
欧州の音大ではこんな感じでOKなようで、今でも[55001]
[55005]
だから、、、 てるてる様[54996]
の話には道理があります
一方で、学生でもより良い楽器を使う方が良いから、経済的余力があってフランスやイタリアのモダン、オールドらを使うのかな。 ご褒美や卒業後の音楽活動を見据えて、って話もあるかも知れませんが
しかし、残念なことに学生への楽器貸与をあまり聞かないのは、文化的価値観の遅れからでしょうか、きっと
[56116]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2025年09月12日 07:04
投稿者:松毬(ID:N2VjBzA)
クラシックTV「点と線 つながるヒストリー」放送9月11日、再放送9月15日14:00~
NHK企画のセリフに従って、清塚信也さんは自慢げに嘘を云う羽目になりました。
あぁ恥ずかしいNHKは影響力があるので、ここではささやかですが訂正します。「点と線 つながるヒストリー」 ⇒ [55366]の方が全然ましだよ
1).日本で初めて国費で音大留学した者:幸田延 [これ間違いです]
⇓
1871年(明治4)岩倉岩倉使節団に随行した第1回海外女子留学生の永井繁子(1881年帰国)[55146]です。幸田延のピアノの師で、日本人初の本格的ピアニストです。ピアノの清塚さん、んなことも知らんの?
繁子は、ニューヨーク州ヴァッサー大学音楽科で学びます。第一回海外女子留学生には津田梅子(津田塾大を創設)、山川捨松(津田塾を支援)らがおり、この二人も当初のホームステイ先でピアノを学んでおり、ヴァッサー大学では英文学専攻の捨松とともに繁子は過ごします
幸田延は、永井繁子や音楽取調掛を設立し東京音楽学校校長となる伊澤修二(1875-1878年マサチューセッツ州へ留学しメーソンに学ぶ)に遅れて、1889年(明治22)第1回文部省派遣留学生としてメーソンゆかりボストンのニューイングランド音楽院へ留学します。幸田はヨアヒムの弟子エミールマールに学び、翌年には、東京音楽学校教授デートリッヒの師で、エネスク、クライスラーを指導したヘルメスベルガーの下へウイーンに留学し直します。1895年帰国
2).日本で初めての西洋音楽技法の曲:幸田延のバイオリンソナタ一番(変ホ長調)1985年作 [これ色々問題ありです]
⇓
[55168][55160]でも示した通り未完の曲で、留学中1985年の習作として帰国後1897年に東京音楽学校学友会演奏会での学内披露に留まった曲です。あまり知られていないのはこの為です。歴史上は未公開の曲として扱われてきたことから、日本で初めての西洋音楽技法の曲としては、1901年公表歌曲「荒城の月」作詞 土井晩翠、作曲 瀧廉太郎と扱われてきました。
この為、日本人が初めて作曲した西洋音楽技法の曲として扱うか否か意見が大きく分かれます。ソナタ一番はバイオリンソナタ二番(ロ短調)と共に最近補筆出版され話題になっており、私的な作曲としては幸田の方が早いと言えますが、幸田の前には師の永井繁子の曲があるとされ、グレーな歯切れの悪さを残しています
この頃の作曲レベルの高さは[55168][55160]の通り伺えますが、それには永井繁子と伊澤修二の音楽留学の他、この板でも示した通り幕末~明治の海外使節団の音楽体験やがあります
3).日本で初めて西洋音楽を聴いた人:安土桃山時代1591年に天正遣欧使節の演奏を聴いた豊臣秀吉(1537-1598)で、3度再演を依頼した。 織田信長(1534-1582)との説もあるが、、、。[これ間違いです]
⇓
その30年~40年前に、すでに聴くだけでなく演奏までしています。室町後期、戦国時代の末のキリシタンに初まります。キリシタンである天正遣欧使団は、遣欧する前に既に上手に四重奏で演奏することができました[55375] (因みに、秀吉は四重奏を聴いたもので、放送された撥弦楽器のビウエラ単奏に感動したのではない)
日本は[55367][55370][55375][55389]の通り、フランシスコ・ザビエルのキリスト布教が切っ掛けです。
日本人としては、1547年マラッカでキリシタンの洗礼を受けたアンジロ(ヤジロウ)と推定でき、日本国内としてもザビエルに同行して1549年帰国したアンジロと推定できます。
また、アンジロの他、ザビエルは 1550年:肥前国平戸、1551年:周防国山口、および豊後国府内でも宣教しており、集まった信者らが教会音楽を耳にしていると推定できます
記録の上では、1551年に周防の守護大名の大内義隆(1507-1551)に、楽器(クラヴォ:鍵盤楽器・クラヴィコード)を贈ります。 これは日本初の西洋音楽に関わった記録で、西洋音楽は山口からとされます!!
また、日本人が初めて西洋音楽を奏でた記録で、豊後(大分)では、1555年、1557年、1561年、1562年、聖歌が歌われ又西洋音楽が教えられたとあり、大伴宗麟を招いて日本の子供たちが西洋音楽を披露している記録があります
『子どもたちのヴィオラ・ダ・アルコ(ヴィオラ)の演奏は「基督教国の王侯の前にても奏し得べきものなりき」と称賛され、ヨーロッパの王侯の前で披露しても恥ずかしくないほどの腕前と記録がある。 大分市に、日本人初の西洋音楽を演奏した「西洋音楽発祥」の地として、宣教師がヴィオラを弾き、日本の子どもたちが歌を歌っている記念碑があります!! 西洋音楽発祥記念碑 https://www.oishiimati-oita.jp/spot/3341』
この延長上に、布教を支援した織田信長[55370]が1581年に京都、安土にセミナリオを建てており、この演奏を聴いたと伝わっています。もしかしたら1582年に信長に京都見物に招待された徳川家康も演奏を聴いたかも知れないくらいです。
これらを踏まえて、演奏が出来る者が選ばれて天正遣欧使団が派遣されたものです
4).因みに、江戸時代は、海外へ漂流した者か国内では徳川秀忠の禁教令と鎖国政策によ出島のオランダ人に会う日本人に限られました。鍵盤の歴史は上ですがピアノはオランダから1823年出島に派遣されたシーボルトが持ち込みます。出島での西洋音楽は、開国のポーハタン号での音楽会[55280] [55355]に繋がっていきます
NHK企画のセリフに従って、清塚信也さんは自慢げに嘘を云う羽目になりました。
あぁ恥ずかしいNHKは影響力があるので、ここではささやかですが訂正します。「点と線 つながるヒストリー」 ⇒ [55366]の方が全然ましだよ
1).日本で初めて国費で音大留学した者:幸田延 [これ間違いです]
⇓
1871年(明治4)岩倉岩倉使節団に随行した第1回海外女子留学生の永井繁子(1881年帰国)[55146]です。幸田延のピアノの師で、日本人初の本格的ピアニストです。ピアノの清塚さん、んなことも知らんの?
繁子は、ニューヨーク州ヴァッサー大学音楽科で学びます。第一回海外女子留学生には津田梅子(津田塾大を創設)、山川捨松(津田塾を支援)らがおり、この二人も当初のホームステイ先でピアノを学んでおり、ヴァッサー大学では英文学専攻の捨松とともに繁子は過ごします
幸田延は、永井繁子や音楽取調掛を設立し東京音楽学校校長となる伊澤修二(1875-1878年マサチューセッツ州へ留学しメーソンに学ぶ)に遅れて、1889年(明治22)第1回文部省派遣留学生としてメーソンゆかりボストンのニューイングランド音楽院へ留学します。幸田はヨアヒムの弟子エミールマールに学び、翌年には、東京音楽学校教授デートリッヒの師で、エネスク、クライスラーを指導したヘルメスベルガーの下へウイーンに留学し直します。1895年帰国
2).日本で初めての西洋音楽技法の曲:幸田延のバイオリンソナタ一番(変ホ長調)1985年作 [これ色々問題ありです]
⇓
[55168][55160]でも示した通り未完の曲で、留学中1985年の習作として帰国後1897年に東京音楽学校学友会演奏会での学内披露に留まった曲です。あまり知られていないのはこの為です。歴史上は未公開の曲として扱われてきたことから、日本で初めての西洋音楽技法の曲としては、1901年公表歌曲「荒城の月」作詞 土井晩翠、作曲 瀧廉太郎と扱われてきました。
この為、日本人が初めて作曲した西洋音楽技法の曲として扱うか否か意見が大きく分かれます。ソナタ一番はバイオリンソナタ二番(ロ短調)と共に最近補筆出版され話題になっており、私的な作曲としては幸田の方が早いと言えますが、幸田の前には師の永井繁子の曲があるとされ、グレーな歯切れの悪さを残しています
この頃の作曲レベルの高さは[55168][55160]の通り伺えますが、それには永井繁子と伊澤修二の音楽留学の他、この板でも示した通り幕末~明治の海外使節団の音楽体験やがあります
3).日本で初めて西洋音楽を聴いた人:安土桃山時代1591年に天正遣欧使節の演奏を聴いた豊臣秀吉(1537-1598)で、3度再演を依頼した。 織田信長(1534-1582)との説もあるが、、、。[これ間違いです]
⇓
その30年~40年前に、すでに聴くだけでなく演奏までしています。室町後期、戦国時代の末のキリシタンに初まります。キリシタンである天正遣欧使団は、遣欧する前に既に上手に四重奏で演奏することができました[55375] (因みに、秀吉は四重奏を聴いたもので、放送された撥弦楽器のビウエラ単奏に感動したのではない)
日本は[55367][55370][55375][55389]の通り、フランシスコ・ザビエルのキリスト布教が切っ掛けです。
日本人としては、1547年マラッカでキリシタンの洗礼を受けたアンジロ(ヤジロウ)と推定でき、日本国内としてもザビエルに同行して1549年帰国したアンジロと推定できます。
また、アンジロの他、ザビエルは 1550年:肥前国平戸、1551年:周防国山口、および豊後国府内でも宣教しており、集まった信者らが教会音楽を耳にしていると推定できます
記録の上では、1551年に周防の守護大名の大内義隆(1507-1551)に、楽器(クラヴォ:鍵盤楽器・クラヴィコード)を贈ります。 これは日本初の西洋音楽に関わった記録で、西洋音楽は山口からとされます!!
また、日本人が初めて西洋音楽を奏でた記録で、豊後(大分)では、1555年、1557年、1561年、1562年、聖歌が歌われ又西洋音楽が教えられたとあり、大伴宗麟を招いて日本の子供たちが西洋音楽を披露している記録があります
『子どもたちのヴィオラ・ダ・アルコ(ヴィオラ)の演奏は「基督教国の王侯の前にても奏し得べきものなりき」と称賛され、ヨーロッパの王侯の前で披露しても恥ずかしくないほどの腕前と記録がある。 大分市に、日本人初の西洋音楽を演奏した「西洋音楽発祥」の地として、宣教師がヴィオラを弾き、日本の子どもたちが歌を歌っている記念碑があります!! 西洋音楽発祥記念碑 https://www.oishiimati-oita.jp/spot/3341』
この延長上に、布教を支援した織田信長[55370]が1581年に京都、安土にセミナリオを建てており、この演奏を聴いたと伝わっています。もしかしたら1582年に信長に京都見物に招待された徳川家康も演奏を聴いたかも知れないくらいです。
これらを踏まえて、演奏が出来る者が選ばれて天正遣欧使団が派遣されたものです
4).因みに、江戸時代は、海外へ漂流した者か国内では徳川秀忠の禁教令と鎖国政策によ出島のオランダ人に会う日本人に限られました。鍵盤の歴史は上ですがピアノはオランダから1823年出島に派遣されたシーボルトが持ち込みます。出島での西洋音楽は、開国のポーハタン号での音楽会[55280] [55355]に繋がっていきます
[56134]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2025年09月15日 15:59
投稿者:松毬(ID:gXdAkWA)
修正訂正と感想 再放送を確認して、不正確だった点はお詫びします。
ただ、ちゃらん、ぽらん、んなNHK放送は良くないね
「2).日本で初めての西洋音楽技法の曲」の問いではなく、「日本人として初めてバイオリンソナタを作曲した者として幸田延」が紹介されるのですが、一番(変ホ長調)も二番(ロ短調)も未完だったことや出版してなかった点は、日本初のバイオリンソナタとしても引っ掛かります
番組では一番ではなく、二番を石上真由子さんの演奏で紹介してこぶしがかった演歌のようとあり、改めて思うに幸田延は一番も二番も世間に受け入れられないのではないか??と思案し躊躇もあって一般公開を憚ったのではないか?もっと当時の世間に受け入れやすいメロディーへと一番から改めて二番の一楽章作曲へ取り組んだまま、そのままの感じです [55168]
後に幸田延は、東京音楽学校を追われるように退官してヨーロッパへと行きます。ベルリン留学した山田耕筰が幸田延を訪れて入学試験の前に挨拶した際に、延に鼻であしらわれた耕筰は発奮して試験に合格したそうです。 東京音楽学校で思い通りに行かずに作曲家として大成しなかった皮肉と耕筰への期待があったのではないか?と思えるエピソードです
「3).日本で初めて西洋音楽を聴いた人」の問いではなく「日本へどのように西洋音楽が入ってくるかとして天正遣欧使節が欧州で学んできた」と紹介されますが、[56116]の通りザビエルの布教に伴って持ち込まれたものです
なお、国産初のピアノ、1900年だったっけ? んー確認必要な気が、、、
ただ、ちゃらん、ぽらん、んなNHK放送は良くないね
「2).日本で初めての西洋音楽技法の曲」の問いではなく、「日本人として初めてバイオリンソナタを作曲した者として幸田延」が紹介されるのですが、一番(変ホ長調)も二番(ロ短調)も未完だったことや出版してなかった点は、日本初のバイオリンソナタとしても引っ掛かります
番組では一番ではなく、二番を石上真由子さんの演奏で紹介してこぶしがかった演歌のようとあり、改めて思うに幸田延は一番も二番も世間に受け入れられないのではないか??と思案し躊躇もあって一般公開を憚ったのではないか?もっと当時の世間に受け入れやすいメロディーへと一番から改めて二番の一楽章作曲へ取り組んだまま、そのままの感じです [55168]
後に幸田延は、東京音楽学校を追われるように退官してヨーロッパへと行きます。ベルリン留学した山田耕筰が幸田延を訪れて入学試験の前に挨拶した際に、延に鼻であしらわれた耕筰は発奮して試験に合格したそうです。 東京音楽学校で思い通りに行かずに作曲家として大成しなかった皮肉と耕筰への期待があったのではないか?と思えるエピソードです
「3).日本で初めて西洋音楽を聴いた人」の問いではなく「日本へどのように西洋音楽が入ってくるかとして天正遣欧使節が欧州で学んできた」と紹介されますが、[56116]の通りザビエルの布教に伴って持ち込まれたものです
なお、国産初のピアノ、1900年だったっけ? んー確認必要な気が、、、
[54991]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年04月11日 03:07
投稿者:松毬(ID:dEmXlFA)
藝大と言えば、戦前の幸田延さんの話があります。
当時の事情では、楽器はジャーマン系の様でイタリアンはありませんが、芸大の学生は高価な舶来品を授業で使った様です。これは、時代は変わっても、良くも悪くも今も概ねは同じですね。
幸田延さんは、日本人初の本格的なバイオリニストで、東京音楽大学の教授となった方です。ディトリッヒの他、ヘルメスベルガーⅡに師事されてクライスラーとは兄妹弟子です。ウイーン留学中に本屋さんからニコロ・アマティを贈られたようで、バイオリニストは、もっと良い楽器を弾かなきゃ、ってパトロネージを承けています。また、帰国後、ピアノはスタンウェイを使ったようですね。幸田幸の姉です。
明治時代、藝大の元(東京音楽大学)の元である音楽取調所(取調掛の改称)の伝習生の時は、何を使ったのか?と観ると、メーソンが教授として着任した時に授業用にアメリカから持ってきたオーケストラが出来る楽器の様ですね。
しかし、幸田延さんの後の伝習生、恒川鐐之介さんを観ると、卒業後に師範学校教授となりますが、学生の甘利鉄吉は和製バイオリン、鈴木政吉は楽器を持っていない時代です。
当時の事情では、楽器はジャーマン系の様でイタリアンはありませんが、芸大の学生は高価な舶来品を授業で使った様です。これは、時代は変わっても、良くも悪くも今も概ねは同じですね。
幸田延さんは、日本人初の本格的なバイオリニストで、東京音楽大学の教授となった方です。ディトリッヒの他、ヘルメスベルガーⅡに師事されてクライスラーとは兄妹弟子です。ウイーン留学中に本屋さんからニコロ・アマティを贈られたようで、バイオリニストは、もっと良い楽器を弾かなきゃ、ってパトロネージを承けています。また、帰国後、ピアノはスタンウェイを使ったようですね。幸田幸の姉です。
明治時代、藝大の元(東京音楽大学)の元である音楽取調所(取調掛の改称)の伝習生の時は、何を使ったのか?と観ると、メーソンが教授として着任した時に授業用にアメリカから持ってきたオーケストラが出来る楽器の様ですね。
しかし、幸田延さんの後の伝習生、恒川鐐之介さんを観ると、卒業後に師範学校教授となりますが、学生の甘利鉄吉は和製バイオリン、鈴木政吉は楽器を持っていない時代です。
[56003]
[56003]
サービス
投稿日時:2025年07月09日 02:25
投稿者:松毬(ID:iDFZgSA)
Lutherie Vosgienne は、大学の教育学部生や音高,音大生と高等教育機関などに向けて、職人がちゃんとした材料でキチッと造った楽器です。LV0(17Fr.)~LV12(100Fr.)まで12レベル(11欠番)あり、Stentor Ⅱ は その5番目レベルの楽器です。(弦楽器カタログより)
[55994] P019参照方https://www.luthiers-mirecourt.com/thibouville1912.htm#Violons
要は、J.T.L.ボトムグレードMi - fin(8 Fr.)よりも少し良いもので、J.T.L.の中間ゾーンをカバーするブランドです。趣味向けではなく、また、マスターピースでもなく、Stentorの名の通り教育学習者向けです。機能的でも恐らく装飾性は少なく、また、職人がと言っても分業で価格を抑えた楽器でしょう。Stentor Ⅱ は練習用楽器です。
しかし、とは言え造りが良いことから、1世紀を経て根強い評価からそこそこ結構な価格ではないでしょうか?
[55994] P019参照方https://www.luthiers-mirecourt.com/thibouville1912.htm#Violons
要は、J.T.L.ボトムグレードMi - fin(8 Fr.)よりも少し良いもので、J.T.L.の中間ゾーンをカバーするブランドです。趣味向けではなく、また、マスターピースでもなく、Stentorの名の通り教育学習者向けです。機能的でも恐らく装飾性は少なく、また、職人がと言っても分業で価格を抑えた楽器でしょう。Stentor Ⅱ は練習用楽器です。
しかし、とは言え造りが良いことから、1世紀を経て根強い評価からそこそこ結構な価格ではないでしょうか?
[56073]
Re: JTL バイオリン
投稿日時:2025年08月28日 11:34
投稿者:松毬(ID:RoZCU4A)
[56002] と[55994] に示した通りで、このラベル自体には特別な価値がある訳でなく、モデルNo.として StentorⅡ を、製作年代として1906~1910年ころを、表すだけのものです
この一方で、楽器屋さんが[56067]のエチケットだけを見て StentorⅡ としているなら、Lutherie VosgienneのJ.T.L.レーベルエチケットが外れていることは真贋の信憑性が下がっています。鑑定眼がある楽器屋さんならよいですが、、、
また、J.T.L.とは平たく言うなら、ピアノは造らない楽器総合メーカーで、今の日本では≒[ヤマハ株式会社の楽器部門(ピアノを除く)]+[鈴木バイオリン製造&杉藤楽弓社+文京楽器の楽器製作&株式会社アルシェ]のような巨大な総合楽器メーカーです
バイオリン製造では[56006]の通り、諸々多くモデルがあり特に当時 SarasateモデルとLutherie Vosgienne(Serie Artiste/Serie Etude)モデルの2つをセールスアピールしたようです。名は、Sarasateは名演奏家より、Lutherie Vosgienneは名工の名のようです
この2つの関係は各々、ヤマハ、鈴木、文京楽器並びにアルシェの、アルティダとブレヴィオルの関係、1000番台と500+300番台の関係、リバースとピグマリウスの関係と、各々の関係に似ています。
そして Stentor Ⅱ は、恐らく ブレヴィオルV20~10, スズキ500番台, ピグマリウスのスペチャリタ~スタンダド辺りの位置づけの楽器で、これが120年ほど経年した楽器に相似するでしょう
Les modèles Sarasate
Serie d'Sarasate (260-38Fr.)
・Virtuose
・Artiste
・Maître
・Elève
Les modèles Lutherie Vosgienne
Serie Artiste (100-38Fr.)
・Claude Ⅲ, Ⅱ,Ⅰ
・Stentor Ⅳ, Ⅲ
・Hieronymous
Serie Etude (35-17Fr.)
・Stentor Ⅱ, Ⅰ
・Ciceron
・Némésianus
・Dracontius
・Pharamus
[56003][56004] の通りで、工芸美術品ではなく工場制手工量産楽器ですが造りもよく一世紀を超えた骨董価値が出て、楽器としても悪くはないでしょう。([56003] 訂正:6番目です)
因みに、当時日本ではスズキがパリ万博1900年に初中級楽器を出品して、銅賞など得るハズもなく選外佳作を得て褒賞されており、これは量産メーカーとして日本で初めて世界に認めれたと言えます。これよりStentor Ⅱは上位の楽器で、とは言っても当時のスズキの上級機種、特性5~3くらいに位置づき、このスズキは骨董的にも学術的にも価値があります
J.T.L.の良い点は、ピンからキリまで楽器(モデル)があり、100年位経年した良い量産楽器が豊富にあることとピンでは手工芸術楽器があることです。
量産楽器ではやたら骨董価値を上げる楽器屋さんもあり要注意です。
ピン楽器ということなら工芸美術品としてのバイオリン、芸術的製作モデル Lutherie D'artを考えますが、ただまず100万円では買えないでしょう。先の例で言えば文京の堀さんの楽器の位置づけイメージに一世紀の骨董価値が乗りますかね
Lutherie D'art (600-280Fr.)
・J. Thibouville-Lamy
・A.Acoulon
・E.Blondelet
この一方で、楽器屋さんが[56067]のエチケットだけを見て StentorⅡ としているなら、Lutherie VosgienneのJ.T.L.レーベルエチケットが外れていることは真贋の信憑性が下がっています。鑑定眼がある楽器屋さんならよいですが、、、
また、J.T.L.とは平たく言うなら、ピアノは造らない楽器総合メーカーで、今の日本では≒[ヤマハ株式会社の楽器部門(ピアノを除く)]+[鈴木バイオリン製造&杉藤楽弓社+文京楽器の楽器製作&株式会社アルシェ]のような巨大な総合楽器メーカーです
バイオリン製造では[56006]の通り、諸々多くモデルがあり特に当時 SarasateモデルとLutherie Vosgienne(Serie Artiste/Serie Etude)モデルの2つをセールスアピールしたようです。名は、Sarasateは名演奏家より、Lutherie Vosgienneは名工の名のようです
この2つの関係は各々、ヤマハ、鈴木、文京楽器並びにアルシェの、アルティダとブレヴィオルの関係、1000番台と500+300番台の関係、リバースとピグマリウスの関係と、各々の関係に似ています。
そして Stentor Ⅱ は、恐らく ブレヴィオルV20~10, スズキ500番台, ピグマリウスのスペチャリタ~スタンダド辺りの位置づけの楽器で、これが120年ほど経年した楽器に相似するでしょう
Les modèles Sarasate
Serie d'Sarasate (260-38Fr.)
・Virtuose
・Artiste
・Maître
・Elève
Les modèles Lutherie Vosgienne
Serie Artiste (100-38Fr.)
・Claude Ⅲ, Ⅱ,Ⅰ
・Stentor Ⅳ, Ⅲ
・Hieronymous
Serie Etude (35-17Fr.)
・Stentor Ⅱ, Ⅰ
・Ciceron
・Némésianus
・Dracontius
・Pharamus
[56003][56004] の通りで、工芸美術品ではなく工場制手工量産楽器ですが造りもよく一世紀を超えた骨董価値が出て、楽器としても悪くはないでしょう。([56003] 訂正:6番目です)
因みに、当時日本ではスズキがパリ万博1900年に初中級楽器を出品して、銅賞など得るハズもなく選外佳作を得て褒賞されており、これは量産メーカーとして日本で初めて世界に認めれたと言えます。これよりStentor Ⅱは上位の楽器で、とは言っても当時のスズキの上級機種、特性5~3くらいに位置づき、このスズキは骨董的にも学術的にも価値があります
J.T.L.の良い点は、ピンからキリまで楽器(モデル)があり、100年位経年した良い量産楽器が豊富にあることとピンでは手工芸術楽器があることです。
量産楽器ではやたら骨董価値を上げる楽器屋さんもあり要注意です。
ピン楽器ということなら工芸美術品としてのバイオリン、芸術的製作モデル Lutherie D'artを考えますが、ただまず100万円では買えないでしょう。先の例で言えば文京の堀さんの楽器の位置づけイメージに一世紀の骨董価値が乗りますかね
Lutherie D'art (600-280Fr.)
・J. Thibouville-Lamy
・A.Acoulon
・E.Blondelet
この楽器は、上のスズキ政吉よりも全然良くて、もしかしたら1980年代のエターナル、ヘリテージよりも良いかも知れません。 J.T.L全体でも今のスズキよりも良いのでは?と思えるくらいですので、、、。 この辺りの楽器なら、ザクソニー/シェーンバッハ(ブーベンロイトら)[56139]
[56139]
Re: JTL バイオリン
投稿日時:2025年09月16日 05:20
投稿者:松毬(ID:F0ImFTk)
P.S. 忘れてはならないことは
モダンは、パリでモダン化されたストラド(オールド)が原点にあり基準になります
ミラクールは、ルポー、ピク、シャノー、ビヨーム、ベルナルデルなどパリでモダン発祥と普及に関わった者らのホームタウンで、彼らに連れだってパリで成功したミラクールの者も多く、パリのモダン楽器製作と深く関わっています。この他、弓ではパリに出て活躍したペカット、アダム、シモン、メイア―、マリーン、ボアラン、マルタン、ラミー、ベネロンら名工がおり、ペカットなどミラクールに戻って製作した者は何人も居ます。
モダン発祥のパリの楽器に最も近しいのがミラクールの楽器なのです
ザクソニーは、他に Hopf Ficker Pfretzschner Reichel Schoflder Voigt それにGotz Roth同様に戦後ブーベンロイトなどに移った K.Hofner Kirschnek Paesold らが居ます。此方の方が聞き覚えがあって身近でしょう。それほどドイツの楽器と言ったらとにかくザクソニーってほどなのです。
(なお、ブーベンロイトとエルランゲンは、ザクソニーからの南西方向にドイツ中央よりニュルンベルクの少し上当りです)
モダン量産って、フランスならミラクールか、ジャーマンならザクソニー/シェーンバッハか、この二大拠点の間でたまにバヴァーリアン(ミッテンヴァルド)って感じで、簡単化して覚えてよいでしょう
モダンは、パリでモダン化されたストラド(オールド)が原点にあり基準になります
ミラクールは、ルポー、ピク、シャノー、ビヨーム、ベルナルデルなどパリでモダン発祥と普及に関わった者らのホームタウンで、彼らに連れだってパリで成功したミラクールの者も多く、パリのモダン楽器製作と深く関わっています。この他、弓ではパリに出て活躍したペカット、アダム、シモン、メイア―、マリーン、ボアラン、マルタン、ラミー、ベネロンら名工がおり、ペカットなどミラクールに戻って製作した者は何人も居ます。
モダン発祥のパリの楽器に最も近しいのがミラクールの楽器なのです
ザクソニーは、他に Hopf Ficker Pfretzschner Reichel Schoflder Voigt それにGotz Roth同様に戦後ブーベンロイトなどに移った K.Hofner Kirschnek Paesold らが居ます。此方の方が聞き覚えがあって身近でしょう。それほどドイツの楽器と言ったらとにかくザクソニーってほどなのです。
(なお、ブーベンロイトとエルランゲンは、ザクソニーからの南西方向にドイツ中央よりニュルンベルクの少し上当りです)
モダン量産って、フランスならミラクールか、ジャーマンならザクソニー/シェーンバッハか、この二大拠点の間でたまにバヴァーリアン(ミッテンヴァルド)って感じで、簡単化して覚えてよいでしょう
[56141]
おまけ
投稿日時:2025年09月17日 02:27
投稿者:松毬(ID:FwaQiSM)
第2次大戦後について
ミラクールは、生産量が落ちてJ.T.L(1857-1968)を最後にモダン量産メーカーがなくなります。 優位性と販路を失った結果だろうと思います。 革新的な更に新型の登場は無いままとっくの昔にモダンストラドスタイルは新型ではなく当たり前なってることとフランス植民地が独立した結果、シェアを落としたのでしょう。 生産効率がよく品質が良くなったジャーマンには勝てなかったようで、手工品の製作だけが残りました。 しかし、1987年にAlain Moinierが中級楽器の半手工的な新作生産を始めて復興の兆しがあります
バヴァーリアンは、第1次大戦後のドイツ恐慌と世界恐慌を経てモダン量産は衰退します。シェーンバッハの低廉な楽器に負けたからです。第2次大戦後も僅かに量産楽器が続く程度です。
なお、手工品バイオリンの町として繁栄は続き、ミッテンヴァルドの製作学校や製作競技会あります。 この学校で村田蔵六氏も学び、氏は帰国後にバイオリン製作学校を開いて日本での製作普及もしています。 ここには作家のカントゥーシャがおり、この地で学んだ有名な日本人作家も多い
ザクソニー/シェーンバッハも、いずれも社会主義体制下(東ドイツ/チェコスロバキア)で生産量を下げて衰退します。
これを事前に嫌って、ザクソニー(マルクノイキルヘン)からは、Roth Gotz Kirschnek Paesoldらが、シェーンバッハからは K.Hofner([56139]誤植訂正) E.Wernerらがブーベンロイト/エルランゲン(旧西ドイツ)に移り、シェーンバッハのSandnerはフランクフルト近くのナウハイムに移って、現在もモダン量産メーカーとして今に至ります。
体制崩壊後は、ザクソニーでは、Kreuzinger GEWA(ミッテンヴァルドに問屋がある)らも続いており、シェーンバッハではCremonaが、かつての様に復活する期待はあります。 なお、この二つの生産地は17世紀にシェーンバッハから職人が国境の山を越えてザクソニーへ移って隣り合わせており元々一つです。また、ニューヨークのウォーリッツア商会はザクソニーの出身です
日本は、スズキが1927(昭2)年に洗練した高級イタリアシリーズを出しますが、大戦により一度壊滅します。 息子の梅雄が経営も製作も創業時をなぞるように立て直して現在に至ります。 生産量はピークの大正時代の足元程度にも及ぶか否かと少ないのですが、上のブーベンロイトと競って品質は格段によくなっています。 この他多くの弦楽器取扱い店が、ピグマリウスのほか自社ブランドの新作を次々と出しています
最も大きなことは、生産性の良い中国が世界最大の量産地として最前線に来たことです。 ブーベンロイトら、日本も、アメリカ(EastManなど)も、自社ブランドを中国で生産して販売する楽器が増えており、20世紀末には中国が最前線に並んでいます。 この他、量産製作はザクソニー/シェーンバッハの東へ東へと広がって、ハンガリーやルーマニア(Gliga)へと変わっています
以上 お持ちの Stentor2 位置づけが、歴史的に客観的にモダン量産の中にみえるのではないでしょうか?
楽器のことで、入り口からもろもろ広く読むなら
・ヴァイオリンの見方・選び方 基礎編/応用編 レッスンの友社 及び せきれい社
・楽器の辞典 ヴァイオリン 増補版[ショパン] 1995年
まともなサイトは、今はここくらいでしょう
ミラクールは、生産量が落ちてJ.T.L(1857-1968)を最後にモダン量産メーカーがなくなります。 優位性と販路を失った結果だろうと思います。 革新的な更に新型の登場は無いままとっくの昔にモダンストラドスタイルは新型ではなく当たり前なってることとフランス植民地が独立した結果、シェアを落としたのでしょう。 生産効率がよく品質が良くなったジャーマンには勝てなかったようで、手工品の製作だけが残りました。 しかし、1987年にAlain Moinierが中級楽器の半手工的な新作生産を始めて復興の兆しがあります
バヴァーリアンは、第1次大戦後のドイツ恐慌と世界恐慌を経てモダン量産は衰退します。シェーンバッハの低廉な楽器に負けたからです。第2次大戦後も僅かに量産楽器が続く程度です。
なお、手工品バイオリンの町として繁栄は続き、ミッテンヴァルドの製作学校や製作競技会あります。 この学校で村田蔵六氏も学び、氏は帰国後にバイオリン製作学校を開いて日本での製作普及もしています。 ここには作家のカントゥーシャがおり、この地で学んだ有名な日本人作家も多い
ザクソニー/シェーンバッハも、いずれも社会主義体制下(東ドイツ/チェコスロバキア)で生産量を下げて衰退します。
これを事前に嫌って、ザクソニー(マルクノイキルヘン)からは、Roth Gotz Kirschnek Paesoldらが、シェーンバッハからは K.Hofner([56139]誤植訂正) E.Wernerらがブーベンロイト/エルランゲン(旧西ドイツ)に移り、シェーンバッハのSandnerはフランクフルト近くのナウハイムに移って、現在もモダン量産メーカーとして今に至ります。
体制崩壊後は、ザクソニーでは、Kreuzinger GEWA(ミッテンヴァルドに問屋がある)らも続いており、シェーンバッハではCremonaが、かつての様に復活する期待はあります。 なお、この二つの生産地は17世紀にシェーンバッハから職人が国境の山を越えてザクソニーへ移って隣り合わせており元々一つです。また、ニューヨークのウォーリッツア商会はザクソニーの出身です
日本は、スズキが1927(昭2)年に洗練した高級イタリアシリーズを出しますが、大戦により一度壊滅します。 息子の梅雄が経営も製作も創業時をなぞるように立て直して現在に至ります。 生産量はピークの大正時代の足元程度にも及ぶか否かと少ないのですが、上のブーベンロイトと競って品質は格段によくなっています。 この他多くの弦楽器取扱い店が、ピグマリウスのほか自社ブランドの新作を次々と出しています
最も大きなことは、生産性の良い中国が世界最大の量産地として最前線に来たことです。 ブーベンロイトら、日本も、アメリカ(EastManなど)も、自社ブランドを中国で生産して販売する楽器が増えており、20世紀末には中国が最前線に並んでいます。 この他、量産製作はザクソニー/シェーンバッハの東へ東へと広がって、ハンガリーやルーマニア(Gliga)へと変わっています
以上 お持ちの Stentor2 位置づけが、歴史的に客観的にモダン量産の中にみえるのではないでしょうか?
楽器のことで、入り口からもろもろ広く読むなら
・ヴァイオリンの見方・選び方 基礎編/応用編 レッスンの友社 及び せきれい社
・楽器の辞典 ヴァイオリン 増補版[ショパン] 1995年
まともなサイトは、今はここくらいでしょう
欧州の音大ではこんな感じでOKなようで、今でも[55001]
[55001]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年04月21日 15:57
投稿者:日本だけ(ID:EnEQcxQ)
巨匠や名手ほど腕9割楽器1割と言っていますね。
ヨーロッパの音大生は大学や銀行から楽器貸与されている人が多いです。自分の楽器は100万円以下の健康なモダン楽器が多く、素晴らしい演奏をします。
掲示板の皆さん、どうか音程を外さないでね。
ヨーロッパの音大生は大学や銀行から楽器貸与されている人が多いです。自分の楽器は100万円以下の健康なモダン楽器が多く、素晴らしい演奏をします。
掲示板の皆さん、どうか音程を外さないでね。
[55005]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年04月22日 02:08
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
てるてる 様 ありがとうございます。
確かにそうですね。
プロの演奏でも19世紀頃のジャーマン系を使われれる方もいらっしゃいますね。
18世紀頃からの量産楽器の中心地に、ミッテンヴァルド/バヴァーリアン、フォクトランド/ザクソニー、ボヘミアンがあり、Neuner、Roth、Herberlein、Hofnerなど親しみのあるメーカーがあり、色んなグレードもあって、更に、これ以外にも沢山の量産メーカーがあります。当りも外れもとありますね。この辺りも日本に沢山輸入されていますからね。
[54993] で書いた、フランスのカルテットの2nd奏者さんは、50年位前の無名楽器と云ってました。サロンホールで双眼鏡を使って演奏を見た時、楽器はカピキオーニか?と思ったのは恥ずかしいほど大外れでした。
お示しされた大学は、音大と看板をつけている大学ですね。一声、音大と言っても沢山あり、バイオリンなどでは、桐朋、東京芸大以外に、
関東では、東京音大、国立音大、武蔵野音大、洗足音大、昭和音大、東邦音大の様に音大と看板をつけている大学の他にフェリス、日大、玉川大、東海大など他もろもろあって、上野学園短大や宇都宮短大など短大でも学べるようですね。北は札幌大谷大学から、南は沖縄県立芸大まであって、弦管打楽器/管弦打楽器コース(←同じ?違うの??)があり、東京芸大以外の国公立の芸大と各教育学部などでも学べるらしいですね。
因みに、紛らわしく愛知県立芸大と名古屋芸大に名古屋音大と名が重なっているし、名古屋だけでなく大阪でも大阪芸大と大阪音大は両方私立です。平成音大もあり何れ令和音大?も登場するかも知れず、音大といっても数々ありますね。加えて、音大に進まず慶応卒、京大卒や医大卒などのプロ奏者もいましたね。
確かにそうですね。
プロの演奏でも19世紀頃のジャーマン系を使われれる方もいらっしゃいますね。
18世紀頃からの量産楽器の中心地に、ミッテンヴァルド/バヴァーリアン、フォクトランド/ザクソニー、ボヘミアンがあり、Neuner、Roth、Herberlein、Hofnerなど親しみのあるメーカーがあり、色んなグレードもあって、更に、これ以外にも沢山の量産メーカーがあります。当りも外れもとありますね。この辺りも日本に沢山輸入されていますからね。
[54993] で書いた、フランスのカルテットの2nd奏者さんは、50年位前の無名楽器と云ってました。サロンホールで双眼鏡を使って演奏を見た時、楽器はカピキオーニか?と思ったのは恥ずかしいほど大外れでした。
お示しされた大学は、音大と看板をつけている大学ですね。一声、音大と言っても沢山あり、バイオリンなどでは、桐朋、東京芸大以外に、
関東では、東京音大、国立音大、武蔵野音大、洗足音大、昭和音大、東邦音大の様に音大と看板をつけている大学の他にフェリス、日大、玉川大、東海大など他もろもろあって、上野学園短大や宇都宮短大など短大でも学べるようですね。北は札幌大谷大学から、南は沖縄県立芸大まであって、弦管打楽器/管弦打楽器コース(←同じ?違うの??)があり、東京芸大以外の国公立の芸大と各教育学部などでも学べるらしいですね。
因みに、紛らわしく愛知県立芸大と名古屋芸大に名古屋音大と名が重なっているし、名古屋だけでなく大阪でも大阪芸大と大阪音大は両方私立です。平成音大もあり何れ令和音大?も登場するかも知れず、音大といっても数々ありますね。加えて、音大に進まず慶応卒、京大卒や医大卒などのプロ奏者もいましたね。
[54996]
Re: 音大生が用いる楽器の実情は?
投稿日時:2024年04月17日 20:17
投稿者:てるてる(ID:NpeJBEU)
ここのプロフェッショナルの方々には、そんなレベルのところは音大とは言わないと鼻で笑われてしまうかも知れませんが、世間的に芸大桐朋の1ランク下の学群と認識されてる音大に進学した友人は、30万以下のノーラベルで推定100年くらい前のドイツ量産を小学生の頃から大学院卒業してからも長いこと使ってました。
楽器選びの順番が前後していたら、教室の落ちこぼれだった私の手元に来ていたかも知れない楽器で、私も欲しかった楽器です。
あれが所謂大当たりの楽器だったのかは分かりませんが、100年程経過した楽器であれば、大半はプロの使用に耐えうるポテンシャルはあるように感じてしまいます。
楽器選びの順番が前後していたら、教室の落ちこぼれだった私の手元に来ていたかも知れない楽器で、私も欲しかった楽器です。
あれが所謂大当たりの楽器だったのかは分かりませんが、100年程経過した楽器であれば、大半はプロの使用に耐えうるポテンシャルはあるように感じてしまいます。
一方で、学生でもより良い楽器を使う方が良いから、経済的余力があってフランスやイタリアのモダン、オールドらを使うのかな。 ご褒美や卒業後の音楽活動を見据えて、って話もあるかも知れませんが
しかし、残念なことに学生への楽器貸与をあまり聞かないのは、文化的価値観の遅れからでしょうか、きっと
ヴァイオリン掲示板に戻る
3 / 4 ページ [ 34コメント ]