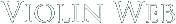[56314]
音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 11:39
投稿者:レモン娘(ID:KHFoB5Y)
大学生になってからバイオリンを始めた、所謂レイトスターターです。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
ヴァイオリン掲示板に戻る
3 / 3 ページ [ 28コメント ]
【ご参考】
[56358]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月16日 03:37
投稿者:pochi(ID:MCaYARA)
微妙なので難易度は高いのですが、
https://anixl.com/title/12144-nodame-cantabile/40916-lesson-18-arousal
12:42~
オーボエ≧コンマス
になっています。
ジックリ聴いたのではなく、瞬時に解って当然で、私はこんなミスはしません。
音楽監督が調弦の性質を知らないと、こんな事になってしまいます。
アニメの話の筋は知らないのですが演奏は全部検証しました。未々おかしな(有り得ない)所は沢山あります。
https://anixl.com/title/12144-nodame-cantabile/40916-lesson-18-arousal
12:42~
オーボエ≧コンマス
になっています。
ジックリ聴いたのではなく、瞬時に解って当然で、私はこんなミスはしません。
音楽監督が調弦の性質を知らないと、こんな事になってしまいます。
アニメの話の筋は知らないのですが演奏は全部検証しました。未々おかしな(有り得ない)所は沢山あります。
[56362]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月17日 14:36
投稿者:松毬(ID:MocoQTA)
※. またぁその変なものPartⅡもってきて、懲りない方ですね。 いい加減なことは書いてある通り示されたのだから、厳格に考えてないよ。 そんなぁんどっちでもいいよ
確かに少し真面的なったけど、前回[56325]
のが外れ過ぎで何か明確な意図があること感じますね。 オーボエの前にピアニカ画像だったからね。
それと、
「吹奏楽関係者が音楽監督なので」ってあるけど、倍音楽器の管楽をバカにしてない??
今回は、[56346]
この講師の方 youtu.be/HrHZjzXRSK4?t=322 、ピアノAとのズラシと同じ程度で逆なわけだけど、、、この講師を非難していたのはどういと、言語同断って思っちゃいますよ
さて、本題にもどって
同音が分れば、[56352]
youtu.be/bh8pKgwapSA ギトリスが行ったプラジオで5度を取ることが出来るかもしれません
同音は、[56354]
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 、ステップ1の通り訓練して、同音は分ると思います
これに加えて、弓を安定して弾く訓練が必要になります
1Hzズレて1回の唸り(1Hz)を聴くには、1秒以上安定して弓を弾く必要があります
0.1Hzズレて1回の唸り(1Hz)を聴くに10秒以上安定して弓を弾く必要があります
これを5秒で俄かに唸り1/2回を判断したとしても、5秒は安定して弓を弾かなければなりません
チューナー(精度1~5centほど)より高精度に調弦するには同音のズレ0.1Hz未満(<1cent)にすることですから、5~10秒ほど、1cent精度のチューナーで針が動かない様に弾きます[56316]
又、上②のステップ1 Optionとして、次が出来ます
・A:3番線にD線ではなくA線を張って、両方とも442Hzを取ります
A442Hzを中心に2番ペグを回してズラして唸りと同音を確認します
同様に3番ペグを回して同じことをします
・G:3番線にD線ではなくG線を張って、両方とも197Hzを取ります
G197Hzを中心に4番ペグを回してズラして唸りと同音を確認します
弦を張り替えて2つ出来ればよいでしょうから、E,Dはステップ1同様に指で取ってよいでしょう。 ステップ2については、また次の機会に
なお、聴覚とは、主に耳の器官の方を指しますが、識覚や知覚とは脳の情報処理で主に聴覚野以降によるものです。 訓練は、この音を処理する脳神経のニューラルネットを構築するものです。
上ら[56354]
②.ステップ1は、聴けば直ぐ分りますが、身に付ける、身体化するにはリハビリ同様、1ヵ月、2ヵ月と時間がかかるかもしれません。 1回10分ほど1日か2日ごとに短時間に集中して行うとよいでしょう
確かに少し真面的なったけど、前回[56325]
[56325]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月09日 19:31
投稿者:pochi(ID:GYk5hIA)
理屈よりも現実的には、
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
https://youtu.be/zieY5fVldeE?t=252
楽器が違うので難易度は少し高めですが音程は、
【ピアニカ<オーボエ】
です。
これは吹奏楽関係者が音楽監督なので、
「チューナーを使って計った」
に決まっています。
個別にチューナーを使ってピッタリに合わせて、後からミキシングで電気的に合成音声にしても、
「合わないから行ってはならない」
決まり切った事で必ず、
「耳で聴いて」
合わせます。
元から「完全一度」(同音)が解らない人が本当に存在する例として良いでしょう。作音楽器であるヴァイオリン演奏では何とも成りません。
それと、
「吹奏楽関係者が音楽監督なので」ってあるけど、倍音楽器の管楽をバカにしてない??
今回は、[56346]
[56346]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月13日 13:02
投稿者:松毬(ID:ODcmGHU)
※.440Hz[56333]って言っているから、だいぶ話は違うみたい。
オーボエは、事前にチューニングメータで442Hzや443に合わせますね。 ピアニカの442Hzや443なら、協和するか1Hzくらいで唸ってるでしょう。 Aみたいなの440Hzでも、2~3Hzで唸るハズかぁ
それに、この[56170]一つ前の投稿でも変なこと言ってたんですよ。 (同じ様に同音が分らないとか音痴だとか何とか言ってて誹謗中傷か名誉棄損かに当たったのか今はいつものように削除されてますね。)
この講師の方 youtu.be/HrHZjzXRSK4?t=322 、別に音感が悪い訳ではなく、この後のAを高く合わせるって言ってます。 これを取り上げて「(ピアノに比べて)明らかにAが高い、同音が分っていないとかレイトは直らない証拠ですとか何とか云々」とオウム返して取り上げただけでなく避難していた様に記憶しています。 更にこの後Gでは、この講師の方が言う通りピアノのGと大体合っているにも関わらずです。
音を聴いた感じがしなくて何をお考えになってんだろっ、って思っちゃいましたけどね
オーボエは、事前にチューニングメータで442Hzや443に合わせますね。 ピアニカの442Hzや443なら、協和するか1Hzくらいで唸ってるでしょう。 Aみたいなの440Hzでも、2~3Hzで唸るハズかぁ
それに、この[56170]一つ前の投稿でも変なこと言ってたんですよ。 (同じ様に同音が分らないとか音痴だとか何とか言ってて誹謗中傷か名誉棄損かに当たったのか今はいつものように削除されてますね。)
この講師の方 youtu.be/HrHZjzXRSK4?t=322 、別に音感が悪い訳ではなく、この後のAを高く合わせるって言ってます。 これを取り上げて「(ピアノに比べて)明らかにAが高い、同音が分っていないとかレイトは直らない証拠ですとか何とか云々」とオウム返して取り上げただけでなく避難していた様に記憶しています。 更にこの後Gでは、この講師の方が言う通りピアノのGと大体合っているにも関わらずです。
音を聴いた感じがしなくて何をお考えになってんだろっ、って思っちゃいましたけどね
さて、本題にもどって
同音が分れば、[56352]
[56352]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月14日 21:53
投稿者:pochi(ID:F5eBSIc)
レモン娘氏、
・楽器の整備が普通で、
・弦が新しくて、
・運弓が普通に出来て、
・同音が正確に解るのなら、
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
ヴァイオリンではあんまり行わない、こんな調弦法があります。A線の3倍音フラジオ(第4ポジション1)とE線2倍音フラジオ(第4ポジション4)は同音なので、チェロではよく行われる調弦法です(チェロではポジションは違いますが理屈は同じです)。
チェロではこのフラジオ調弦法で調弦して、完全五度が合わなくなったら弦の替え時なのです。最終的には完全五度で確認しますが、調弦の良い練習にはなるので挑戦してみましょう。
弦が傷むと高次倍音ほどフラジオの音程は低くなり勝ちです。
調弦は弾いた音の残響で合わせるのですが、開放弦を弾いた時に、弦の種類によって、弦が傷んだ時の残響の音程の高低が違います。ガット弦では残響が高くなり、金属弦では低くなる傾向があり、人工素材弦は中間で様々です。
・楽器の整備が普通で、
・弦が新しくて、
・運弓が普通に出来て、
・同音が正確に解るのなら、
https://youtu.be/bh8pKgwapSA
ヴァイオリンではあんまり行わない、こんな調弦法があります。A線の3倍音フラジオ(第4ポジション1)とE線2倍音フラジオ(第4ポジション4)は同音なので、チェロではよく行われる調弦法です(チェロではポジションは違いますが理屈は同じです)。
チェロではこのフラジオ調弦法で調弦して、完全五度が合わなくなったら弦の替え時なのです。最終的には完全五度で確認しますが、調弦の良い練習にはなるので挑戦してみましょう。
弦が傷むと高次倍音ほどフラジオの音程は低くなり勝ちです。
調弦は弾いた音の残響で合わせるのですが、開放弦を弾いた時に、弦の種類によって、弦が傷んだ時の残響の音程の高低が違います。ガット弦では残響が高くなり、金属弦では低くなる傾向があり、人工素材弦は中間で様々です。
同音は、[56354]
[56354]
調弦デモ比べてみました
投稿日時:2025年11月15日 09:32
投稿者:松毬(ID:KQNGV5A)
※.[56351] →アハハハぁっ、そりゃ3倍音が高くなる場合があるのは当然しってるよ。 アコースティックの話をしても意味ないでしょ。 「後からミキシングで電気的に合成音声にして」[56325]と書いているのだから。 電気的に合成音声での話をしてくれなきゃ
そもそもは、そんな変なもん持ってくるからでしょ。 [56352]は良いと思いますが、嘲るように余計なことやってるから自ら嵌った訳でしょ
さて、本筋に戻ります。 レモン娘 様へ
実践に向かって、まずは色んな調弦デモを見比べてみましょう
①.youtu.be/-6Sbd6y9MPU 模範的とおもいます。 示すべきこと簡潔明瞭(堂々と筋だっている。不足も蛇足もなく混乱もない)。 これでのコメント通り☆和音(和声)が協和した趣きがポイントです
・Option1:音叉&指ではじく調弦
→youtu.be/TyC6e3LJKII
→youtu.be/6nrsjnSVEng?t=163
参考〈ペグ〉
・回し方Option:→youtu.be/ezJqLZZ06oA?t=202
・コンポジション調整法Option1:→youtu.be/1fz-Z7fp_FM?t=1356
・弦巻き方による調整法Option2:→youtu.be/uKCPcSEeMg4?t=46
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 理論的な説明が分かり易いとおもいます(ただ実践では要の第三の音の鼓動(唸り)は分かり難いものの、応用として他の5度、4度、3度、6度の音程へも展開できる大きな利点があります)
ステップ1:完全1度の同音、同音への鼓動(唸り)をバイオリンでハッキリと確認できます。 鼓動が消えて、同音で音がスッキリとした感じ、和音として協和した感覚が分ると思います
ステップ2:完全5度(A4:E5)、第三の音(コンビネーショントーン、差音)に触れます。 第三の音A3(A4のオクターブ下)は知覚できますが非常に微小で初めは識覚が不足してわからないかも、、、とおもいます。 (第三の音は、A4:E5に対しA3、D4:A4に対しD3、G3:D4に対しG2)
ステップ3:完全5度(A4:E5)に対しA4とA3(又はA'3→A3)の鼓動に触れます。 [56332]予告通り実際は上ステップ1より音量が小さく、ステップ2の第三の音らの鼓動があります。 これに着目して上ステップ1同様に調整します
③.youtu.be/RzVdYZVaJHo?t=281 こちらの方が鼓動(唸り)が分かり易い(D4:A4)
★トレーニングの要点は、次三つの不足した識覚を強化する(音やその変化を聴いて覚える)ことです
・A4完全1度、A4:E5, D4:A4, G3:D4,完全5度の和声を知覚すること
・上が崩れて干渉した音や鼓動(唸り)を知覚すること
・第三の音を知覚すること
なお、上②では、ステップ2の通り第三の音はわからないかもで、初めは現実問題として結局は完全5度が協和した感覚を基に調弦しているかもです。 この為、初めはステップ1の協和の感覚に似た、第三の音含めた三音の和音が協和した感覚を先に探ってしまうかもしれませんね
また、同②では、感覚的には、A4:E5ではA3に第三の音が現れ、E'5→E5へ調弦に伴い、A4とA'3→A3への鼓動があります。 物理的には、純音では[56327] の鼓動(唸り)に対して更には鼓動は追加されませんが、実際はA4,E5の倍音関係毎に色々な差音が生じ、また、同音関係にもなって同音の鼓動が生じて、A4とA'3は各々独立に鼓動していると思います
[差音同士で同音への鼓動]
A4とE'5の差音によるE'3 vs A4の2倍音のA5とE'5の差音によるE''3
[倍音同士で同音への鼓動] A4の3倍音のE6 vs E'5の2倍音のE'6
*更にこの上の倍音でも同じようなことが起きてこれらに重なります
そもそもは、そんな変なもん持ってくるからでしょ。 [56352]は良いと思いますが、嘲るように余計なことやってるから自ら嵌った訳でしょ
さて、本筋に戻ります。 レモン娘 様へ
実践に向かって、まずは色んな調弦デモを見比べてみましょう
①.youtu.be/-6Sbd6y9MPU 模範的とおもいます。 示すべきこと簡潔明瞭(堂々と筋だっている。不足も蛇足もなく混乱もない)。 これでのコメント通り☆和音(和声)が協和した趣きがポイントです
・Option1:音叉&指ではじく調弦
→youtu.be/TyC6e3LJKII
→youtu.be/6nrsjnSVEng?t=163
参考〈ペグ〉
・回し方Option:→youtu.be/ezJqLZZ06oA?t=202
・コンポジション調整法Option1:→youtu.be/1fz-Z7fp_FM?t=1356
・弦巻き方による調整法Option2:→youtu.be/uKCPcSEeMg4?t=46
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 理論的な説明が分かり易いとおもいます(ただ実践では要の第三の音の鼓動(唸り)は分かり難いものの、応用として他の5度、4度、3度、6度の音程へも展開できる大きな利点があります)
ステップ1:完全1度の同音、同音への鼓動(唸り)をバイオリンでハッキリと確認できます。 鼓動が消えて、同音で音がスッキリとした感じ、和音として協和した感覚が分ると思います
ステップ2:完全5度(A4:E5)、第三の音(コンビネーショントーン、差音)に触れます。 第三の音A3(A4のオクターブ下)は知覚できますが非常に微小で初めは識覚が不足してわからないかも、、、とおもいます。 (第三の音は、A4:E5に対しA3、D4:A4に対しD3、G3:D4に対しG2)
ステップ3:完全5度(A4:E5)に対しA4とA3(又はA'3→A3)の鼓動に触れます。 [56332]予告通り実際は上ステップ1より音量が小さく、ステップ2の第三の音らの鼓動があります。 これに着目して上ステップ1同様に調整します
③.youtu.be/RzVdYZVaJHo?t=281 こちらの方が鼓動(唸り)が分かり易い(D4:A4)
★トレーニングの要点は、次三つの不足した識覚を強化する(音やその変化を聴いて覚える)ことです
・A4完全1度、A4:E5, D4:A4, G3:D4,完全5度の和声を知覚すること
・上が崩れて干渉した音や鼓動(唸り)を知覚すること
・第三の音を知覚すること
なお、上②では、ステップ2の通り第三の音はわからないかもで、初めは現実問題として結局は完全5度が協和した感覚を基に調弦しているかもです。 この為、初めはステップ1の協和の感覚に似た、第三の音含めた三音の和音が協和した感覚を先に探ってしまうかもしれませんね
また、同②では、感覚的には、A4:E5ではA3に第三の音が現れ、E'5→E5へ調弦に伴い、A4とA'3→A3への鼓動があります。 物理的には、純音では[56327] の鼓動(唸り)に対して更には鼓動は追加されませんが、実際はA4,E5の倍音関係毎に色々な差音が生じ、また、同音関係にもなって同音の鼓動が生じて、A4とA'3は各々独立に鼓動していると思います
[差音同士で同音への鼓動]
A4とE'5の差音によるE'3 vs A4の2倍音のA5とE'5の差音によるE''3
[倍音同士で同音への鼓動] A4の3倍音のE6 vs E'5の2倍音のE'6
*更にこの上の倍音でも同じようなことが起きてこれらに重なります
これに加えて、弓を安定して弾く訓練が必要になります
1Hzズレて1回の唸り(1Hz)を聴くには、1秒以上安定して弓を弾く必要があります
0.1Hzズレて1回の唸り(1Hz)を聴くに10秒以上安定して弓を弾く必要があります
これを5秒で俄かに唸り1/2回を判断したとしても、5秒は安定して弓を弾かなければなりません
チューナー(精度1~5centほど)より高精度に調弦するには同音のズレ0.1Hz未満(<1cent)にすることですから、5~10秒ほど、1cent精度のチューナーで針が動かない様に弾きます[56316]
[56316]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 16:46
投稿者:pochi(ID:mWMxVWA)
レモン娘氏、お早う御座います。
まず、「感」を鍛える方法は無い、と考えて下さい。
そうは言っても何ともなら無いので、何とかする手法を考えるべきですよね。
音叉を使いましょう。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/marina-guitar/onsa-442-box.html
極近くでピッタリのAを大きな音で弾くと、極僅かですが共鳴します。
アジャスタで調整してピッタリのAを「共鳴で」弾ける様にしましょう。
出来ない人がいて、本当に何とも成りません。
音程の理屈として、「完全一度」(同音)が解らない人には、何ともなら無いのがヴァイオリンです。作音楽器の原理です。
チューナーの針を見詰めても解る様にはならない(解る事に繋がらない)ので無駄ですが、音程の前提に「良い運弓」の獲得が有ります。
運弓が下手だとチューナーの針が揺れるので、運弓の良し悪しの可視化にはなります。
便利なのは高感度設定にしたチューナーの針が動かなければ良く、針が真ん中に来る必要も無いので、良い練習になると思います。
E線開放弦pp全弓、特にダウンは誰に取っても非常に難しいものです。ヴァイオリンの演奏技術の盲点で、現実的には楽曲の中に滅多に出てきません。
>誹謗中傷
------本当の事を書いています。誹謗中傷だと思う時点でヴァイオリンには向きません。ヴァイオリンを習うと、先生からずっと誹謗中傷され続ける事になりますよ。
まず、「感」を鍛える方法は無い、と考えて下さい。
そうは言っても何ともなら無いので、何とかする手法を考えるべきですよね。
音叉を使いましょう。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/marina-guitar/onsa-442-box.html
極近くでピッタリのAを大きな音で弾くと、極僅かですが共鳴します。
アジャスタで調整してピッタリのAを「共鳴で」弾ける様にしましょう。
出来ない人がいて、本当に何とも成りません。
音程の理屈として、「完全一度」(同音)が解らない人には、何ともなら無いのがヴァイオリンです。作音楽器の原理です。
チューナーの針を見詰めても解る様にはならない(解る事に繋がらない)ので無駄ですが、音程の前提に「良い運弓」の獲得が有ります。
運弓が下手だとチューナーの針が揺れるので、運弓の良し悪しの可視化にはなります。
便利なのは高感度設定にしたチューナーの針が動かなければ良く、針が真ん中に来る必要も無いので、良い練習になると思います。
E線開放弦pp全弓、特にダウンは誰に取っても非常に難しいものです。ヴァイオリンの演奏技術の盲点で、現実的には楽曲の中に滅多に出てきません。
>誹謗中傷
------本当の事を書いています。誹謗中傷だと思う時点でヴァイオリンには向きません。ヴァイオリンを習うと、先生からずっと誹謗中傷され続ける事になりますよ。
又、上②のステップ1 Optionとして、次が出来ます
・A:3番線にD線ではなくA線を張って、両方とも442Hzを取ります
A442Hzを中心に2番ペグを回してズラして唸りと同音を確認します
同様に3番ペグを回して同じことをします
・G:3番線にD線ではなくG線を張って、両方とも197Hzを取ります
G197Hzを中心に4番ペグを回してズラして唸りと同音を確認します
弦を張り替えて2つ出来ればよいでしょうから、E,Dはステップ1同様に指で取ってよいでしょう。 ステップ2については、また次の機会に
なお、聴覚とは、主に耳の器官の方を指しますが、識覚や知覚とは脳の情報処理で主に聴覚野以降によるものです。 訓練は、この音を処理する脳神経のニューラルネットを構築するものです。
上ら[56354]
[56354]
調弦デモ比べてみました
投稿日時:2025年11月15日 09:32
投稿者:松毬(ID:KQNGV5A)
※.[56351] →アハハハぁっ、そりゃ3倍音が高くなる場合があるのは当然しってるよ。 アコースティックの話をしても意味ないでしょ。 「後からミキシングで電気的に合成音声にして」[56325]と書いているのだから。 電気的に合成音声での話をしてくれなきゃ
そもそもは、そんな変なもん持ってくるからでしょ。 [56352]は良いと思いますが、嘲るように余計なことやってるから自ら嵌った訳でしょ
さて、本筋に戻ります。 レモン娘 様へ
実践に向かって、まずは色んな調弦デモを見比べてみましょう
①.youtu.be/-6Sbd6y9MPU 模範的とおもいます。 示すべきこと簡潔明瞭(堂々と筋だっている。不足も蛇足もなく混乱もない)。 これでのコメント通り☆和音(和声)が協和した趣きがポイントです
・Option1:音叉&指ではじく調弦
→youtu.be/TyC6e3LJKII
→youtu.be/6nrsjnSVEng?t=163
参考〈ペグ〉
・回し方Option:→youtu.be/ezJqLZZ06oA?t=202
・コンポジション調整法Option1:→youtu.be/1fz-Z7fp_FM?t=1356
・弦巻き方による調整法Option2:→youtu.be/uKCPcSEeMg4?t=46
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 理論的な説明が分かり易いとおもいます(ただ実践では要の第三の音の鼓動(唸り)は分かり難いものの、応用として他の5度、4度、3度、6度の音程へも展開できる大きな利点があります)
ステップ1:完全1度の同音、同音への鼓動(唸り)をバイオリンでハッキリと確認できます。 鼓動が消えて、同音で音がスッキリとした感じ、和音として協和した感覚が分ると思います
ステップ2:完全5度(A4:E5)、第三の音(コンビネーショントーン、差音)に触れます。 第三の音A3(A4のオクターブ下)は知覚できますが非常に微小で初めは識覚が不足してわからないかも、、、とおもいます。 (第三の音は、A4:E5に対しA3、D4:A4に対しD3、G3:D4に対しG2)
ステップ3:完全5度(A4:E5)に対しA4とA3(又はA'3→A3)の鼓動に触れます。 [56332]予告通り実際は上ステップ1より音量が小さく、ステップ2の第三の音らの鼓動があります。 これに着目して上ステップ1同様に調整します
③.youtu.be/RzVdYZVaJHo?t=281 こちらの方が鼓動(唸り)が分かり易い(D4:A4)
★トレーニングの要点は、次三つの不足した識覚を強化する(音やその変化を聴いて覚える)ことです
・A4完全1度、A4:E5, D4:A4, G3:D4,完全5度の和声を知覚すること
・上が崩れて干渉した音や鼓動(唸り)を知覚すること
・第三の音を知覚すること
なお、上②では、ステップ2の通り第三の音はわからないかもで、初めは現実問題として結局は完全5度が協和した感覚を基に調弦しているかもです。 この為、初めはステップ1の協和の感覚に似た、第三の音含めた三音の和音が協和した感覚を先に探ってしまうかもしれませんね
また、同②では、感覚的には、A4:E5ではA3に第三の音が現れ、E'5→E5へ調弦に伴い、A4とA'3→A3への鼓動があります。 物理的には、純音では[56327] の鼓動(唸り)に対して更には鼓動は追加されませんが、実際はA4,E5の倍音関係毎に色々な差音が生じ、また、同音関係にもなって同音の鼓動が生じて、A4とA'3は各々独立に鼓動していると思います
[差音同士で同音への鼓動]
A4とE'5の差音によるE'3 vs A4の2倍音のA5とE'5の差音によるE''3
[倍音同士で同音への鼓動] A4の3倍音のE6 vs E'5の2倍音のE'6
*更にこの上の倍音でも同じようなことが起きてこれらに重なります
そもそもは、そんな変なもん持ってくるからでしょ。 [56352]は良いと思いますが、嘲るように余計なことやってるから自ら嵌った訳でしょ
さて、本筋に戻ります。 レモン娘 様へ
実践に向かって、まずは色んな調弦デモを見比べてみましょう
①.youtu.be/-6Sbd6y9MPU 模範的とおもいます。 示すべきこと簡潔明瞭(堂々と筋だっている。不足も蛇足もなく混乱もない)。 これでのコメント通り☆和音(和声)が協和した趣きがポイントです
・Option1:音叉&指ではじく調弦
→youtu.be/TyC6e3LJKII
→youtu.be/6nrsjnSVEng?t=163
参考〈ペグ〉
・回し方Option:→youtu.be/ezJqLZZ06oA?t=202
・コンポジション調整法Option1:→youtu.be/1fz-Z7fp_FM?t=1356
・弦巻き方による調整法Option2:→youtu.be/uKCPcSEeMg4?t=46
②.youtu.be/g_fm5k6NRjk?t=34 理論的な説明が分かり易いとおもいます(ただ実践では要の第三の音の鼓動(唸り)は分かり難いものの、応用として他の5度、4度、3度、6度の音程へも展開できる大きな利点があります)
ステップ1:完全1度の同音、同音への鼓動(唸り)をバイオリンでハッキリと確認できます。 鼓動が消えて、同音で音がスッキリとした感じ、和音として協和した感覚が分ると思います
ステップ2:完全5度(A4:E5)、第三の音(コンビネーショントーン、差音)に触れます。 第三の音A3(A4のオクターブ下)は知覚できますが非常に微小で初めは識覚が不足してわからないかも、、、とおもいます。 (第三の音は、A4:E5に対しA3、D4:A4に対しD3、G3:D4に対しG2)
ステップ3:完全5度(A4:E5)に対しA4とA3(又はA'3→A3)の鼓動に触れます。 [56332]予告通り実際は上ステップ1より音量が小さく、ステップ2の第三の音らの鼓動があります。 これに着目して上ステップ1同様に調整します
③.youtu.be/RzVdYZVaJHo?t=281 こちらの方が鼓動(唸り)が分かり易い(D4:A4)
★トレーニングの要点は、次三つの不足した識覚を強化する(音やその変化を聴いて覚える)ことです
・A4完全1度、A4:E5, D4:A4, G3:D4,完全5度の和声を知覚すること
・上が崩れて干渉した音や鼓動(唸り)を知覚すること
・第三の音を知覚すること
なお、上②では、ステップ2の通り第三の音はわからないかもで、初めは現実問題として結局は完全5度が協和した感覚を基に調弦しているかもです。 この為、初めはステップ1の協和の感覚に似た、第三の音含めた三音の和音が協和した感覚を先に探ってしまうかもしれませんね
また、同②では、感覚的には、A4:E5ではA3に第三の音が現れ、E'5→E5へ調弦に伴い、A4とA'3→A3への鼓動があります。 物理的には、純音では[56327] の鼓動(唸り)に対して更には鼓動は追加されませんが、実際はA4,E5の倍音関係毎に色々な差音が生じ、また、同音関係にもなって同音の鼓動が生じて、A4とA'3は各々独立に鼓動していると思います
[差音同士で同音への鼓動]
A4とE'5の差音によるE'3 vs A4の2倍音のA5とE'5の差音によるE''3
[倍音同士で同音への鼓動] A4の3倍音のE6 vs E'5の2倍音のE'6
*更にこの上の倍音でも同じようなことが起きてこれらに重なります
[56363]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月17日 15:26
投稿者:pochi(ID:IJMVJmI)
調弦はチョッと弾いて残響で合わせます。←知らなかったの?
狂っていたら(頭の中で)唸ります。
[53576]
にピアノに合わせた調弦例があります。
「クレア・ホジキンズ」が調弦のGが少し低くて運弓でミスって更に低くて「ハイフェッツ」に言外に指摘されています。「ホジキンズ」のミスは解るでしょうが「ハイフェッツの指摘」は解らないでしょう。私がお目に掛かった時には長身美人のオバサマでした。「ハイフェッツ」はヨボヨボの優しいお爺さんでした。
>倍音楽器の管楽をバカにしてない??
--------していませんが、ガッコのスイソーガク関係者はね、、、。音痴は感染症の一種でチューナーを使っても治りません(治癒に繋がりません)。
この掲示板では、開放弦全弓をシツコク推奨しています。特にppダウンは難しいのです。初心者に出来るとは思っていないから、調弦の序でに開放弦の重音全弓を推奨しています。こちらの方が簡単です。推奨には理由があります。
「A」が「E」に聞こえる様ではヴァイオリンには生まれ付き向いていません。
知識やお金では通用しない事があるのですよ。
狂っていたら(頭の中で)唸ります。
[53576]
[53576]
Re: Fis-DurとGes-Dur
投稿日時:2018年12月30日 04:58
投稿者:pochi(ID:EmRZcVc)
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53477
あじ氏、
>純正律短2度が133セントになっていますが、112セントですよね?
----純正律短二度は色々あります。
http://musica.art.coocan.jp/enharmonic.htm
http://www.niji.or.jp/home/ss1996/tech/psm.htm
多く使われるのは、16/15倍周波数比ですから、理論値は、約111.7セントで、あじ氏が正解です。増一度は更に狭いので、ヘマンの20ページの純正律短2度が133セントには、疑問があります。
===============
===============
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53575
abeg氏、
[53478]のリンク
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
にヴァイオリンの音程の取り方の基本が書いてあります。
GesやFisもありますよ。
======
【ファースト・ポジション】
■4の指
G線D、D線A、A線Eは、開放弦と同音ですから、ピッタリ合わせられます。音が吸い込まれる様に感じます。E線Hは少し難しいのですが、A-Eの幅で、E-Hを弾きます。重音で弾きたいのであれば、E線に対するA線Hを取り、そのオクターブでE線Hを弾きます。ピッタリ合わせて下さい。
■3の指
E線A、A線D、D線Gは響くので簡単です。G線Cは少し難しいのですが、3の指は全部同じ高さ、(E-Aの幅)=(A-Dの幅)=(D-Gの幅)=(G-Cの幅)です。全部同じ高さなので、慣れれば弾けます。ピアノよりも若干低めです。
■1の指
G線A、D線Eは、開放弦のオクターブ下なので響きます。A線HはE線との完全四度で弾けます。この(G-Aの幅)=(D-Eの幅)=(A-Hの幅)で、(E-Fisの幅)を弾きます。1の指の音も全部同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からH・Fis・Cis・Gis
1の指で取ったD線Eに対して完全四度の重音でG線Hを取ります。残りのFisCisGisはすべて同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からB・F・C・G
G線2オクターブにピッタリのE線Gが鳴らせます。この高さで、G・C・F・Bと弾きます。ピアノよりも低めです。
■1の指G線からAs・Es・B・F
2の指で取ったA線Cの完全四度上のE線Fを取ります。この高さで、As・Es・B・Fを弾きます。低めです。
■4の指G線からDes・As・Es・B
1の指で取ったA線Bのオクターブ上のE線Bを取ります。D線Esでもオクターブ上のA線Esが取れます。これも全部同じ高さで、Des・As・Es・Bが弾けます。結構低めです。
■3の指G線からCis・Gis・Dis・Ais
2の指で取ったFisやCisの完全四度下の重音で取ります。同じ高さでCis・Gis・Dis・Aisが弾けます。結構高めです。
■1の指G線からGis・Dis・Ais・Eis
3の指で取ったGis・Dis・Aisに対してオクターブ下です。全部同じ高さでEisも取れます。ベートーヴェンのメヌエットト長調でA線Aisが出てきます。結構高めです。
■3の指G線からCes・Ges・Des・As
既に取った1の指G線のAsに対して2オクターブのE線3の指Asを取ります。 導音が解れば、E線2の指Gを導音とする様に3の指でAsを取ります。
3の指の♭は全部同じ高さ、 (G-Cesの幅)=(D-Gesの幅)=(A-Desの幅)=(E-Asの幅) です。
【サード・ポジション】
■1の指
G線からC・G・D・Aに移動します。当たり前ですよね。
■4の指
G線からF・C・G・Dです。 G線に対する2オクターブ上のA線Gが取れますから、残りは全部同じ高さです。 響きますから、容易に取れます。
■3の指
G線EをE線との共鳴で取れます。G線からE・H・Fis・Cisが取れます。全部同じ高さです。結構高めです。 D線HをG線の5倍音で取ってしまうと低くなるので、注意が必要です。
■2の指
簡単です。G線からD・A・E・Hですね。全部同じ高さです。
■3の指を加筆 E線からC・F・B・Es
A線4指GをG開放弦の2オクターブの響きで取り、そのGに対して完全四度上のE線Cを重音で取ります。
C・F・B・Esは同じ高さで弾きます。 1の指のE線からA・D・G・Cに対して短三度(A-C)(D-F)(G-B)(C-Es)は全部同じ幅です。
結構低い音なのですが、低くなり過ぎない様に弾くのがポイントです。
======
メロディの音階を弾く時の基本として、ピタゴラス音律を更に極端に取る事が多いのが抜けています。
A-durを弾く場合、
「A-Hの幅」=「D-Eの幅」=「E-Fisの幅」≦「H-Cisの幅」≦「Fis-Gisの幅」
移動のドでは、ヴァイオリンの音程の取り方の原則、
ドレミファ/ソラシド
の組になっているので、「H-Cisの幅」≒「Fis-Gisの幅」としても良く、
長調の第3音と第7音は高めに取る、のが、ヴァイオリンの音程です。
パブロ・カザルス曰く、半音は全音の1/3と言っています。数学的ピタゴラス律では約44%になっています。
ヴァイオリンの音程は、更に「オクターブ伸張」を勘案する必要があります。
高い音はより高く、低い音はより低く、弾いた方が、正しい音程に聞こえるのが、人間の耳の特性です。
ピアノでは、レイルスバックカーブとして示されています。
http://78.media.tumblr.com/cee54fc842172c5844cc963d9abdfc9c/tumblr_nnmhd7vyTr1qdsqmfo1_500.jpg
ヴァイオリンの音程は、開放弦G・D・A・E迄は3/2周波数比で、弦楽合奏では時代によって、G-D、D-Aは、それを平均律にどれだけ近付けるか、狭くするか、1.96セントの幅で勘案します。A-E、E-HはEの3/2倍音としてよい、と思います。
Gは低くなり過ぎない様に注意が必要です。ミスっている例です。
https://youtu.be/9tfSH9Sm-Ek
「クレア・ホジキンズ」のGの調弦はホンの少し低めで、運弓のミスで更に低く成り過ぎて、言外にハイフェッツに指摘を受けています。耳の悪い人は、何処で指摘を受けたのか、解らないでしょう。尚、「クレア・ホジキンズ」は他の生徒とは立場と年齢が違い、ハイフェッツのアシスタントでした。
オクターブ伸張は、
「E線DはD線の4倍音で取ると低く聴こえる」
「E線のフラジオは、弦が新しくて正確な2倍音であっても、低めである」
明確に習います。
E線C・Cisは微妙です。ヴァイオリンのCは楽器自体が低めに響きを持っている事が多く、気を付けるべき音で、
「楽器の鳴りでCを弾くと低くなる」
これも習います。
しかし、一応、E線Cの根拠は、A線サードポジションでGの4倍音を取って、その完全四度上で、正しいE線Cとして良い、事になっています。
E線Cisは"Extensive Pythagoras"の関係もあり、高く取る事が多いと思います。
=====
純正律はメロディでは使わず、和声で使います。
完全五度(3/2)
完全四度(4/3)
完全八度(2/1)
大全音(9/8)
は、ピタゴラス律と同じです。
メロディと和声の音程の差が問題になるのは、長短三度と、オクターブの裏になる、短長六度です。
ピタゴラス音律の長三度は(9/8)^2=81/64
短三度は完全五度の裏ですから、(3/2)÷(81/64)
純正律の長三度は5/4(大全音+小全音)
純正律の短三度は6/5(完全五度と長三度の裏)
D線2の指をA線に合わせて、唸りが無く、F及びFisを取ると、純正律長短三度は容易に取れます。
長六度はオクターブと短三度の裏
短六度はオクターブと長三度の裏
=====
重音の音程の取り方の基本は、
①上の音をピタゴラスで弾き、下の音を純正で付ける
②下の音が開放弦とその偶数倍音なら、下の音に上の音を純正で付ける
③残響が少ない場所なら、どちらともピタゴラス音律で弾く
③'アルペジオも重音に準じて、残響の過多で取る音程が違い、残響の多い所では純正律で、少ない所ではピタゴラス律
④重音の次に同じ音のメロディが出て来る等、矛盾が出る場合、平均律っぽく弾いて誤魔化す
細かい所は違い、例外も沢山あるのですが、趣旨は、
へマン著「弦楽器のイントネーション」
https://www.amazon.co.jp/dp/4883952681
この本の解説みたいなものです。
疑問があれば、監修した海野義雄に問い合わせましょう。
https://ja-jp.facebook.com/mikio.unno
息子の幹雄に問い合わせれば何とかなるでしょう。
こちらも趣旨は同じです。
https://maki-music.net/weblec/ontei/
=====
短調は一般に3種類あるので、複雑ですが、短三度(第3音)を低めに取ります。
a-mollならCを低めに取り、FやGを低めに取る事が多いと思います。
更に、私のオリジナルです。
ヴァイオリン的短音階は、a-mollなら運指上、
AHCD/EFisGA
が基本形です。旋律的短音階の変形です。
旋律的短音階でGisで弾く場合は、高く取ると悲劇的な感じになります。
Fで弾いてFを低めに取ると、哀愁を帯びた感じになります。
F・GisでFを低く、Gisを高く弾くと、奇想的になります。
Hを低めに取ると、沈鬱な感じになります。
あじ氏、
>純正律短2度が133セントになっていますが、112セントですよね?
----純正律短二度は色々あります。
http://musica.art.coocan.jp/enharmonic.htm
http://www.niji.or.jp/home/ss1996/tech/psm.htm
多く使われるのは、16/15倍周波数比ですから、理論値は、約111.7セントで、あじ氏が正解です。増一度は更に狭いので、ヘマンの20ページの純正律短2度が133セントには、疑問があります。
===============
===============
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53575
abeg氏、
[53478]のリンク
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
にヴァイオリンの音程の取り方の基本が書いてあります。
GesやFisもありますよ。
======
【ファースト・ポジション】
■4の指
G線D、D線A、A線Eは、開放弦と同音ですから、ピッタリ合わせられます。音が吸い込まれる様に感じます。E線Hは少し難しいのですが、A-Eの幅で、E-Hを弾きます。重音で弾きたいのであれば、E線に対するA線Hを取り、そのオクターブでE線Hを弾きます。ピッタリ合わせて下さい。
■3の指
E線A、A線D、D線Gは響くので簡単です。G線Cは少し難しいのですが、3の指は全部同じ高さ、(E-Aの幅)=(A-Dの幅)=(D-Gの幅)=(G-Cの幅)です。全部同じ高さなので、慣れれば弾けます。ピアノよりも若干低めです。
■1の指
G線A、D線Eは、開放弦のオクターブ下なので響きます。A線HはE線との完全四度で弾けます。この(G-Aの幅)=(D-Eの幅)=(A-Hの幅)で、(E-Fisの幅)を弾きます。1の指の音も全部同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からH・Fis・Cis・Gis
1の指で取ったD線Eに対して完全四度の重音でG線Hを取ります。残りのFisCisGisはすべて同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からB・F・C・G
G線2オクターブにピッタリのE線Gが鳴らせます。この高さで、G・C・F・Bと弾きます。ピアノよりも低めです。
■1の指G線からAs・Es・B・F
2の指で取ったA線Cの完全四度上のE線Fを取ります。この高さで、As・Es・B・Fを弾きます。低めです。
■4の指G線からDes・As・Es・B
1の指で取ったA線Bのオクターブ上のE線Bを取ります。D線Esでもオクターブ上のA線Esが取れます。これも全部同じ高さで、Des・As・Es・Bが弾けます。結構低めです。
■3の指G線からCis・Gis・Dis・Ais
2の指で取ったFisやCisの完全四度下の重音で取ります。同じ高さでCis・Gis・Dis・Aisが弾けます。結構高めです。
■1の指G線からGis・Dis・Ais・Eis
3の指で取ったGis・Dis・Aisに対してオクターブ下です。全部同じ高さでEisも取れます。ベートーヴェンのメヌエットト長調でA線Aisが出てきます。結構高めです。
■3の指G線からCes・Ges・Des・As
既に取った1の指G線のAsに対して2オクターブのE線3の指Asを取ります。 導音が解れば、E線2の指Gを導音とする様に3の指でAsを取ります。
3の指の♭は全部同じ高さ、 (G-Cesの幅)=(D-Gesの幅)=(A-Desの幅)=(E-Asの幅) です。
【サード・ポジション】
■1の指
G線からC・G・D・Aに移動します。当たり前ですよね。
■4の指
G線からF・C・G・Dです。 G線に対する2オクターブ上のA線Gが取れますから、残りは全部同じ高さです。 響きますから、容易に取れます。
■3の指
G線EをE線との共鳴で取れます。G線からE・H・Fis・Cisが取れます。全部同じ高さです。結構高めです。 D線HをG線の5倍音で取ってしまうと低くなるので、注意が必要です。
■2の指
簡単です。G線からD・A・E・Hですね。全部同じ高さです。
■3の指を加筆 E線からC・F・B・Es
A線4指GをG開放弦の2オクターブの響きで取り、そのGに対して完全四度上のE線Cを重音で取ります。
C・F・B・Esは同じ高さで弾きます。 1の指のE線からA・D・G・Cに対して短三度(A-C)(D-F)(G-B)(C-Es)は全部同じ幅です。
結構低い音なのですが、低くなり過ぎない様に弾くのがポイントです。
======
メロディの音階を弾く時の基本として、ピタゴラス音律を更に極端に取る事が多いのが抜けています。
A-durを弾く場合、
「A-Hの幅」=「D-Eの幅」=「E-Fisの幅」≦「H-Cisの幅」≦「Fis-Gisの幅」
移動のドでは、ヴァイオリンの音程の取り方の原則、
ドレミファ/ソラシド
の組になっているので、「H-Cisの幅」≒「Fis-Gisの幅」としても良く、
長調の第3音と第7音は高めに取る、のが、ヴァイオリンの音程です。
パブロ・カザルス曰く、半音は全音の1/3と言っています。数学的ピタゴラス律では約44%になっています。
ヴァイオリンの音程は、更に「オクターブ伸張」を勘案する必要があります。
高い音はより高く、低い音はより低く、弾いた方が、正しい音程に聞こえるのが、人間の耳の特性です。
ピアノでは、レイルスバックカーブとして示されています。
http://78.media.tumblr.com/cee54fc842172c5844cc963d9abdfc9c/tumblr_nnmhd7vyTr1qdsqmfo1_500.jpg
ヴァイオリンの音程は、開放弦G・D・A・E迄は3/2周波数比で、弦楽合奏では時代によって、G-D、D-Aは、それを平均律にどれだけ近付けるか、狭くするか、1.96セントの幅で勘案します。A-E、E-HはEの3/2倍音としてよい、と思います。
Gは低くなり過ぎない様に注意が必要です。ミスっている例です。
https://youtu.be/9tfSH9Sm-Ek
「クレア・ホジキンズ」のGの調弦はホンの少し低めで、運弓のミスで更に低く成り過ぎて、言外にハイフェッツに指摘を受けています。耳の悪い人は、何処で指摘を受けたのか、解らないでしょう。尚、「クレア・ホジキンズ」は他の生徒とは立場と年齢が違い、ハイフェッツのアシスタントでした。
オクターブ伸張は、
「E線DはD線の4倍音で取ると低く聴こえる」
「E線のフラジオは、弦が新しくて正確な2倍音であっても、低めである」
明確に習います。
E線C・Cisは微妙です。ヴァイオリンのCは楽器自体が低めに響きを持っている事が多く、気を付けるべき音で、
「楽器の鳴りでCを弾くと低くなる」
これも習います。
しかし、一応、E線Cの根拠は、A線サードポジションでGの4倍音を取って、その完全四度上で、正しいE線Cとして良い、事になっています。
E線Cisは"Extensive Pythagoras"の関係もあり、高く取る事が多いと思います。
=====
純正律はメロディでは使わず、和声で使います。
完全五度(3/2)
完全四度(4/3)
完全八度(2/1)
大全音(9/8)
は、ピタゴラス律と同じです。
メロディと和声の音程の差が問題になるのは、長短三度と、オクターブの裏になる、短長六度です。
ピタゴラス音律の長三度は(9/8)^2=81/64
短三度は完全五度の裏ですから、(3/2)÷(81/64)
純正律の長三度は5/4(大全音+小全音)
純正律の短三度は6/5(完全五度と長三度の裏)
D線2の指をA線に合わせて、唸りが無く、F及びFisを取ると、純正律長短三度は容易に取れます。
長六度はオクターブと短三度の裏
短六度はオクターブと長三度の裏
=====
重音の音程の取り方の基本は、
①上の音をピタゴラスで弾き、下の音を純正で付ける
②下の音が開放弦とその偶数倍音なら、下の音に上の音を純正で付ける
③残響が少ない場所なら、どちらともピタゴラス音律で弾く
③'アルペジオも重音に準じて、残響の過多で取る音程が違い、残響の多い所では純正律で、少ない所ではピタゴラス律
④重音の次に同じ音のメロディが出て来る等、矛盾が出る場合、平均律っぽく弾いて誤魔化す
細かい所は違い、例外も沢山あるのですが、趣旨は、
へマン著「弦楽器のイントネーション」
https://www.amazon.co.jp/dp/4883952681
この本の解説みたいなものです。
疑問があれば、監修した海野義雄に問い合わせましょう。
https://ja-jp.facebook.com/mikio.unno
息子の幹雄に問い合わせれば何とかなるでしょう。
こちらも趣旨は同じです。
https://maki-music.net/weblec/ontei/
=====
短調は一般に3種類あるので、複雑ですが、短三度(第3音)を低めに取ります。
a-mollならCを低めに取り、FやGを低めに取る事が多いと思います。
更に、私のオリジナルです。
ヴァイオリン的短音階は、a-mollなら運指上、
AHCD/EFisGA
が基本形です。旋律的短音階の変形です。
旋律的短音階でGisで弾く場合は、高く取ると悲劇的な感じになります。
Fで弾いてFを低めに取ると、哀愁を帯びた感じになります。
F・GisでFを低く、Gisを高く弾くと、奇想的になります。
Hを低めに取ると、沈鬱な感じになります。
「クレア・ホジキンズ」が調弦のGが少し低くて運弓でミスって更に低くて「ハイフェッツ」に言外に指摘されています。「ホジキンズ」のミスは解るでしょうが「ハイフェッツの指摘」は解らないでしょう。私がお目に掛かった時には長身美人のオバサマでした。「ハイフェッツ」はヨボヨボの優しいお爺さんでした。
>倍音楽器の管楽をバカにしてない??
--------していませんが、ガッコのスイソーガク関係者はね、、、。音痴は感染症の一種でチューナーを使っても治りません(治癒に繋がりません)。
この掲示板では、開放弦全弓をシツコク推奨しています。特にppダウンは難しいのです。初心者に出来るとは思っていないから、調弦の序でに開放弦の重音全弓を推奨しています。こちらの方が簡単です。推奨には理由があります。
「A」が「E」に聞こえる様ではヴァイオリンには生まれ付き向いていません。
知識やお金では通用しない事があるのですよ。
[56367]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月17日 18:21
投稿者:松毬(ID:IiWDgHA)
誤植訂正
0.1Hzズレて1回の唸り(0.1Hz)を聴くに10秒以上安定して弓を弾く必要があります
※.同音が分らないと言ってるのだから、頭の中で唸るわけないじゃん。 物事の順番が逆です
まぁ、これで9秒くらいかな、いいじゃん、いいじゃん、じゃないと物理的に唸りません。 弓の練習を兼ねてね。 音のビビりは出さないように
気持ちがビビってるなら、5秒で1/2回唸りで合っているか判断にしましょう。 少しずつ分るようになったらもっと短くてもいいでしょうよ。 実際的には0.1Hzの唸りよりも、ちょっと弾いた響きで分るようになるでしょう
0.1Hzズレて1回の唸り(0.1Hz)を聴くに10秒以上安定して弓を弾く必要があります
※.同音が分らないと言ってるのだから、頭の中で唸るわけないじゃん。 物事の順番が逆です
まぁ、これで9秒くらいかな、いいじゃん、いいじゃん、じゃないと物理的に唸りません。 弓の練習を兼ねてね。 音のビビりは出さないように
気持ちがビビってるなら、5秒で1/2回唸りで合っているか判断にしましょう。 少しずつ分るようになったらもっと短くてもいいでしょうよ。 実際的には0.1Hzの唸りよりも、ちょっと弾いた響きで分るようになるでしょう
[56368]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月17日 21:05
投稿者:松毬(ID:JgckgZQ)
※[56363]
どこにあるの?
「[53576]
にピアノに合わせた調弦例」、音ないゾ
今回のは重音全弓でいいだよ。 調弦の話しだよ すぐに話しの本筋を外す山犬ポチン漢だゾ
知識やお金では通用しない事あって、もともと普通の才で、とっくに信用なく伏魔殿になってないか?「誹謗中傷を受ける[56314]
」と。
一つ名誉としては、柏木論争の始まりには柏木氏による過剰な非難があると認む
しかし、論争と言うより闘争であり柏木氏の排除へ追い込む段は不名誉だろう。 この辺りからもチューナーをけ嫌いしてないか? なにもチューナー君自体は何も悪くありません。 オーボエもお世話になりますからね。 目的に合わせて使えば良いでしょう
[56363]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月17日 15:26
投稿者:pochi(ID:IJMVJmI)
調弦はチョッと弾いて残響で合わせます。←知らなかったの?
狂っていたら(頭の中で)唸ります。
[53576]
にピアノに合わせた調弦例があります。
「クレア・ホジキンズ」が調弦のGが少し低くて運弓でミスって更に低くて「ハイフェッツ」に言外に指摘されています。「ホジキンズ」のミスは解るでしょうが「ハイフェッツの指摘」は解らないでしょう。私がお目に掛かった時には長身美人のオバサマでした。「ハイフェッツ」はヨボヨボの優しいお爺さんでした。
>倍音楽器の管楽をバカにしてない??
--------していませんが、ガッコのスイソーガク関係者はね、、、。音痴は感染症の一種でチューナーを使っても治りません(治癒に繋がりません)。
この掲示板では、開放弦全弓をシツコク推奨しています。特にppダウンは難しいのです。初心者に出来るとは思っていないから、調弦の序でに開放弦の重音全弓を推奨しています。こちらの方が簡単です。推奨には理由があります。
「A」が「E」に聞こえる様ではヴァイオリンには生まれ付き向いていません。
知識やお金では通用しない事があるのですよ。
狂っていたら(頭の中で)唸ります。
[53576]
[53576]
Re: Fis-DurとGes-Dur
投稿日時:2018年12月30日 04:58
投稿者:pochi(ID:EmRZcVc)
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53477
あじ氏、
>純正律短2度が133セントになっていますが、112セントですよね?
----純正律短二度は色々あります。
http://musica.art.coocan.jp/enharmonic.htm
http://www.niji.or.jp/home/ss1996/tech/psm.htm
多く使われるのは、16/15倍周波数比ですから、理論値は、約111.7セントで、あじ氏が正解です。増一度は更に狭いので、ヘマンの20ページの純正律短2度が133セントには、疑問があります。
===============
===============
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53575
abeg氏、
[53478]のリンク
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
にヴァイオリンの音程の取り方の基本が書いてあります。
GesやFisもありますよ。
======
【ファースト・ポジション】
■4の指
G線D、D線A、A線Eは、開放弦と同音ですから、ピッタリ合わせられます。音が吸い込まれる様に感じます。E線Hは少し難しいのですが、A-Eの幅で、E-Hを弾きます。重音で弾きたいのであれば、E線に対するA線Hを取り、そのオクターブでE線Hを弾きます。ピッタリ合わせて下さい。
■3の指
E線A、A線D、D線Gは響くので簡単です。G線Cは少し難しいのですが、3の指は全部同じ高さ、(E-Aの幅)=(A-Dの幅)=(D-Gの幅)=(G-Cの幅)です。全部同じ高さなので、慣れれば弾けます。ピアノよりも若干低めです。
■1の指
G線A、D線Eは、開放弦のオクターブ下なので響きます。A線HはE線との完全四度で弾けます。この(G-Aの幅)=(D-Eの幅)=(A-Hの幅)で、(E-Fisの幅)を弾きます。1の指の音も全部同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からH・Fis・Cis・Gis
1の指で取ったD線Eに対して完全四度の重音でG線Hを取ります。残りのFisCisGisはすべて同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からB・F・C・G
G線2オクターブにピッタリのE線Gが鳴らせます。この高さで、G・C・F・Bと弾きます。ピアノよりも低めです。
■1の指G線からAs・Es・B・F
2の指で取ったA線Cの完全四度上のE線Fを取ります。この高さで、As・Es・B・Fを弾きます。低めです。
■4の指G線からDes・As・Es・B
1の指で取ったA線Bのオクターブ上のE線Bを取ります。D線Esでもオクターブ上のA線Esが取れます。これも全部同じ高さで、Des・As・Es・Bが弾けます。結構低めです。
■3の指G線からCis・Gis・Dis・Ais
2の指で取ったFisやCisの完全四度下の重音で取ります。同じ高さでCis・Gis・Dis・Aisが弾けます。結構高めです。
■1の指G線からGis・Dis・Ais・Eis
3の指で取ったGis・Dis・Aisに対してオクターブ下です。全部同じ高さでEisも取れます。ベートーヴェンのメヌエットト長調でA線Aisが出てきます。結構高めです。
■3の指G線からCes・Ges・Des・As
既に取った1の指G線のAsに対して2オクターブのE線3の指Asを取ります。 導音が解れば、E線2の指Gを導音とする様に3の指でAsを取ります。
3の指の♭は全部同じ高さ、 (G-Cesの幅)=(D-Gesの幅)=(A-Desの幅)=(E-Asの幅) です。
【サード・ポジション】
■1の指
G線からC・G・D・Aに移動します。当たり前ですよね。
■4の指
G線からF・C・G・Dです。 G線に対する2オクターブ上のA線Gが取れますから、残りは全部同じ高さです。 響きますから、容易に取れます。
■3の指
G線EをE線との共鳴で取れます。G線からE・H・Fis・Cisが取れます。全部同じ高さです。結構高めです。 D線HをG線の5倍音で取ってしまうと低くなるので、注意が必要です。
■2の指
簡単です。G線からD・A・E・Hですね。全部同じ高さです。
■3の指を加筆 E線からC・F・B・Es
A線4指GをG開放弦の2オクターブの響きで取り、そのGに対して完全四度上のE線Cを重音で取ります。
C・F・B・Esは同じ高さで弾きます。 1の指のE線からA・D・G・Cに対して短三度(A-C)(D-F)(G-B)(C-Es)は全部同じ幅です。
結構低い音なのですが、低くなり過ぎない様に弾くのがポイントです。
======
メロディの音階を弾く時の基本として、ピタゴラス音律を更に極端に取る事が多いのが抜けています。
A-durを弾く場合、
「A-Hの幅」=「D-Eの幅」=「E-Fisの幅」≦「H-Cisの幅」≦「Fis-Gisの幅」
移動のドでは、ヴァイオリンの音程の取り方の原則、
ドレミファ/ソラシド
の組になっているので、「H-Cisの幅」≒「Fis-Gisの幅」としても良く、
長調の第3音と第7音は高めに取る、のが、ヴァイオリンの音程です。
パブロ・カザルス曰く、半音は全音の1/3と言っています。数学的ピタゴラス律では約44%になっています。
ヴァイオリンの音程は、更に「オクターブ伸張」を勘案する必要があります。
高い音はより高く、低い音はより低く、弾いた方が、正しい音程に聞こえるのが、人間の耳の特性です。
ピアノでは、レイルスバックカーブとして示されています。
http://78.media.tumblr.com/cee54fc842172c5844cc963d9abdfc9c/tumblr_nnmhd7vyTr1qdsqmfo1_500.jpg
ヴァイオリンの音程は、開放弦G・D・A・E迄は3/2周波数比で、弦楽合奏では時代によって、G-D、D-Aは、それを平均律にどれだけ近付けるか、狭くするか、1.96セントの幅で勘案します。A-E、E-HはEの3/2倍音としてよい、と思います。
Gは低くなり過ぎない様に注意が必要です。ミスっている例です。
https://youtu.be/9tfSH9Sm-Ek
「クレア・ホジキンズ」のGの調弦はホンの少し低めで、運弓のミスで更に低く成り過ぎて、言外にハイフェッツに指摘を受けています。耳の悪い人は、何処で指摘を受けたのか、解らないでしょう。尚、「クレア・ホジキンズ」は他の生徒とは立場と年齢が違い、ハイフェッツのアシスタントでした。
オクターブ伸張は、
「E線DはD線の4倍音で取ると低く聴こえる」
「E線のフラジオは、弦が新しくて正確な2倍音であっても、低めである」
明確に習います。
E線C・Cisは微妙です。ヴァイオリンのCは楽器自体が低めに響きを持っている事が多く、気を付けるべき音で、
「楽器の鳴りでCを弾くと低くなる」
これも習います。
しかし、一応、E線Cの根拠は、A線サードポジションでGの4倍音を取って、その完全四度上で、正しいE線Cとして良い、事になっています。
E線Cisは"Extensive Pythagoras"の関係もあり、高く取る事が多いと思います。
=====
純正律はメロディでは使わず、和声で使います。
完全五度(3/2)
完全四度(4/3)
完全八度(2/1)
大全音(9/8)
は、ピタゴラス律と同じです。
メロディと和声の音程の差が問題になるのは、長短三度と、オクターブの裏になる、短長六度です。
ピタゴラス音律の長三度は(9/8)^2=81/64
短三度は完全五度の裏ですから、(3/2)÷(81/64)
純正律の長三度は5/4(大全音+小全音)
純正律の短三度は6/5(完全五度と長三度の裏)
D線2の指をA線に合わせて、唸りが無く、F及びFisを取ると、純正律長短三度は容易に取れます。
長六度はオクターブと短三度の裏
短六度はオクターブと長三度の裏
=====
重音の音程の取り方の基本は、
①上の音をピタゴラスで弾き、下の音を純正で付ける
②下の音が開放弦とその偶数倍音なら、下の音に上の音を純正で付ける
③残響が少ない場所なら、どちらともピタゴラス音律で弾く
③'アルペジオも重音に準じて、残響の過多で取る音程が違い、残響の多い所では純正律で、少ない所ではピタゴラス律
④重音の次に同じ音のメロディが出て来る等、矛盾が出る場合、平均律っぽく弾いて誤魔化す
細かい所は違い、例外も沢山あるのですが、趣旨は、
へマン著「弦楽器のイントネーション」
https://www.amazon.co.jp/dp/4883952681
この本の解説みたいなものです。
疑問があれば、監修した海野義雄に問い合わせましょう。
https://ja-jp.facebook.com/mikio.unno
息子の幹雄に問い合わせれば何とかなるでしょう。
こちらも趣旨は同じです。
https://maki-music.net/weblec/ontei/
=====
短調は一般に3種類あるので、複雑ですが、短三度(第3音)を低めに取ります。
a-mollならCを低めに取り、FやGを低めに取る事が多いと思います。
更に、私のオリジナルです。
ヴァイオリン的短音階は、a-mollなら運指上、
AHCD/EFisGA
が基本形です。旋律的短音階の変形です。
旋律的短音階でGisで弾く場合は、高く取ると悲劇的な感じになります。
Fで弾いてFを低めに取ると、哀愁を帯びた感じになります。
F・GisでFを低く、Gisを高く弾くと、奇想的になります。
Hを低めに取ると、沈鬱な感じになります。
あじ氏、
>純正律短2度が133セントになっていますが、112セントですよね?
----純正律短二度は色々あります。
http://musica.art.coocan.jp/enharmonic.htm
http://www.niji.or.jp/home/ss1996/tech/psm.htm
多く使われるのは、16/15倍周波数比ですから、理論値は、約111.7セントで、あじ氏が正解です。増一度は更に狭いので、ヘマンの20ページの純正律短2度が133セントには、疑問があります。
===============
===============
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53575
abeg氏、
[53478]のリンク
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
にヴァイオリンの音程の取り方の基本が書いてあります。
GesやFisもありますよ。
======
【ファースト・ポジション】
■4の指
G線D、D線A、A線Eは、開放弦と同音ですから、ピッタリ合わせられます。音が吸い込まれる様に感じます。E線Hは少し難しいのですが、A-Eの幅で、E-Hを弾きます。重音で弾きたいのであれば、E線に対するA線Hを取り、そのオクターブでE線Hを弾きます。ピッタリ合わせて下さい。
■3の指
E線A、A線D、D線Gは響くので簡単です。G線Cは少し難しいのですが、3の指は全部同じ高さ、(E-Aの幅)=(A-Dの幅)=(D-Gの幅)=(G-Cの幅)です。全部同じ高さなので、慣れれば弾けます。ピアノよりも若干低めです。
■1の指
G線A、D線Eは、開放弦のオクターブ下なので響きます。A線HはE線との完全四度で弾けます。この(G-Aの幅)=(D-Eの幅)=(A-Hの幅)で、(E-Fisの幅)を弾きます。1の指の音も全部同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からH・Fis・Cis・Gis
1の指で取ったD線Eに対して完全四度の重音でG線Hを取ります。残りのFisCisGisはすべて同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からB・F・C・G
G線2オクターブにピッタリのE線Gが鳴らせます。この高さで、G・C・F・Bと弾きます。ピアノよりも低めです。
■1の指G線からAs・Es・B・F
2の指で取ったA線Cの完全四度上のE線Fを取ります。この高さで、As・Es・B・Fを弾きます。低めです。
■4の指G線からDes・As・Es・B
1の指で取ったA線Bのオクターブ上のE線Bを取ります。D線Esでもオクターブ上のA線Esが取れます。これも全部同じ高さで、Des・As・Es・Bが弾けます。結構低めです。
■3の指G線からCis・Gis・Dis・Ais
2の指で取ったFisやCisの完全四度下の重音で取ります。同じ高さでCis・Gis・Dis・Aisが弾けます。結構高めです。
■1の指G線からGis・Dis・Ais・Eis
3の指で取ったGis・Dis・Aisに対してオクターブ下です。全部同じ高さでEisも取れます。ベートーヴェンのメヌエットト長調でA線Aisが出てきます。結構高めです。
■3の指G線からCes・Ges・Des・As
既に取った1の指G線のAsに対して2オクターブのE線3の指Asを取ります。 導音が解れば、E線2の指Gを導音とする様に3の指でAsを取ります。
3の指の♭は全部同じ高さ、 (G-Cesの幅)=(D-Gesの幅)=(A-Desの幅)=(E-Asの幅) です。
【サード・ポジション】
■1の指
G線からC・G・D・Aに移動します。当たり前ですよね。
■4の指
G線からF・C・G・Dです。 G線に対する2オクターブ上のA線Gが取れますから、残りは全部同じ高さです。 響きますから、容易に取れます。
■3の指
G線EをE線との共鳴で取れます。G線からE・H・Fis・Cisが取れます。全部同じ高さです。結構高めです。 D線HをG線の5倍音で取ってしまうと低くなるので、注意が必要です。
■2の指
簡単です。G線からD・A・E・Hですね。全部同じ高さです。
■3の指を加筆 E線からC・F・B・Es
A線4指GをG開放弦の2オクターブの響きで取り、そのGに対して完全四度上のE線Cを重音で取ります。
C・F・B・Esは同じ高さで弾きます。 1の指のE線からA・D・G・Cに対して短三度(A-C)(D-F)(G-B)(C-Es)は全部同じ幅です。
結構低い音なのですが、低くなり過ぎない様に弾くのがポイントです。
======
メロディの音階を弾く時の基本として、ピタゴラス音律を更に極端に取る事が多いのが抜けています。
A-durを弾く場合、
「A-Hの幅」=「D-Eの幅」=「E-Fisの幅」≦「H-Cisの幅」≦「Fis-Gisの幅」
移動のドでは、ヴァイオリンの音程の取り方の原則、
ドレミファ/ソラシド
の組になっているので、「H-Cisの幅」≒「Fis-Gisの幅」としても良く、
長調の第3音と第7音は高めに取る、のが、ヴァイオリンの音程です。
パブロ・カザルス曰く、半音は全音の1/3と言っています。数学的ピタゴラス律では約44%になっています。
ヴァイオリンの音程は、更に「オクターブ伸張」を勘案する必要があります。
高い音はより高く、低い音はより低く、弾いた方が、正しい音程に聞こえるのが、人間の耳の特性です。
ピアノでは、レイルスバックカーブとして示されています。
http://78.media.tumblr.com/cee54fc842172c5844cc963d9abdfc9c/tumblr_nnmhd7vyTr1qdsqmfo1_500.jpg
ヴァイオリンの音程は、開放弦G・D・A・E迄は3/2周波数比で、弦楽合奏では時代によって、G-D、D-Aは、それを平均律にどれだけ近付けるか、狭くするか、1.96セントの幅で勘案します。A-E、E-HはEの3/2倍音としてよい、と思います。
Gは低くなり過ぎない様に注意が必要です。ミスっている例です。
https://youtu.be/9tfSH9Sm-Ek
「クレア・ホジキンズ」のGの調弦はホンの少し低めで、運弓のミスで更に低く成り過ぎて、言外にハイフェッツに指摘を受けています。耳の悪い人は、何処で指摘を受けたのか、解らないでしょう。尚、「クレア・ホジキンズ」は他の生徒とは立場と年齢が違い、ハイフェッツのアシスタントでした。
オクターブ伸張は、
「E線DはD線の4倍音で取ると低く聴こえる」
「E線のフラジオは、弦が新しくて正確な2倍音であっても、低めである」
明確に習います。
E線C・Cisは微妙です。ヴァイオリンのCは楽器自体が低めに響きを持っている事が多く、気を付けるべき音で、
「楽器の鳴りでCを弾くと低くなる」
これも習います。
しかし、一応、E線Cの根拠は、A線サードポジションでGの4倍音を取って、その完全四度上で、正しいE線Cとして良い、事になっています。
E線Cisは"Extensive Pythagoras"の関係もあり、高く取る事が多いと思います。
=====
純正律はメロディでは使わず、和声で使います。
完全五度(3/2)
完全四度(4/3)
完全八度(2/1)
大全音(9/8)
は、ピタゴラス律と同じです。
メロディと和声の音程の差が問題になるのは、長短三度と、オクターブの裏になる、短長六度です。
ピタゴラス音律の長三度は(9/8)^2=81/64
短三度は完全五度の裏ですから、(3/2)÷(81/64)
純正律の長三度は5/4(大全音+小全音)
純正律の短三度は6/5(完全五度と長三度の裏)
D線2の指をA線に合わせて、唸りが無く、F及びFisを取ると、純正律長短三度は容易に取れます。
長六度はオクターブと短三度の裏
短六度はオクターブと長三度の裏
=====
重音の音程の取り方の基本は、
①上の音をピタゴラスで弾き、下の音を純正で付ける
②下の音が開放弦とその偶数倍音なら、下の音に上の音を純正で付ける
③残響が少ない場所なら、どちらともピタゴラス音律で弾く
③'アルペジオも重音に準じて、残響の過多で取る音程が違い、残響の多い所では純正律で、少ない所ではピタゴラス律
④重音の次に同じ音のメロディが出て来る等、矛盾が出る場合、平均律っぽく弾いて誤魔化す
細かい所は違い、例外も沢山あるのですが、趣旨は、
へマン著「弦楽器のイントネーション」
https://www.amazon.co.jp/dp/4883952681
この本の解説みたいなものです。
疑問があれば、監修した海野義雄に問い合わせましょう。
https://ja-jp.facebook.com/mikio.unno
息子の幹雄に問い合わせれば何とかなるでしょう。
こちらも趣旨は同じです。
https://maki-music.net/weblec/ontei/
=====
短調は一般に3種類あるので、複雑ですが、短三度(第3音)を低めに取ります。
a-mollならCを低めに取り、FやGを低めに取る事が多いと思います。
更に、私のオリジナルです。
ヴァイオリン的短音階は、a-mollなら運指上、
AHCD/EFisGA
が基本形です。旋律的短音階の変形です。
旋律的短音階でGisで弾く場合は、高く取ると悲劇的な感じになります。
Fで弾いてFを低めに取ると、哀愁を帯びた感じになります。
F・GisでFを低く、Gisを高く弾くと、奇想的になります。
Hを低めに取ると、沈鬱な感じになります。
「クレア・ホジキンズ」が調弦のGが少し低くて運弓でミスって更に低くて「ハイフェッツ」に言外に指摘されています。「ホジキンズ」のミスは解るでしょうが「ハイフェッツの指摘」は解らないでしょう。私がお目に掛かった時には長身美人のオバサマでした。「ハイフェッツ」はヨボヨボの優しいお爺さんでした。
>倍音楽器の管楽をバカにしてない??
--------していませんが、ガッコのスイソーガク関係者はね、、、。音痴は感染症の一種でチューナーを使っても治りません(治癒に繋がりません)。
この掲示板では、開放弦全弓をシツコク推奨しています。特にppダウンは難しいのです。初心者に出来るとは思っていないから、調弦の序でに開放弦の重音全弓を推奨しています。こちらの方が簡単です。推奨には理由があります。
「A」が「E」に聞こえる様ではヴァイオリンには生まれ付き向いていません。
知識やお金では通用しない事があるのですよ。
「[53576]
[53576]
Re: Fis-DurとGes-Dur
投稿日時:2018年12月30日 04:58
投稿者:pochi(ID:EmRZcVc)
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53477
あじ氏、
>純正律短2度が133セントになっていますが、112セントですよね?
----純正律短二度は色々あります。
http://musica.art.coocan.jp/enharmonic.htm
http://www.niji.or.jp/home/ss1996/tech/psm.htm
多く使われるのは、16/15倍周波数比ですから、理論値は、約111.7セントで、あじ氏が正解です。増一度は更に狭いので、ヘマンの20ページの純正律短2度が133セントには、疑問があります。
===============
===============
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53575
abeg氏、
[53478]のリンク
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
にヴァイオリンの音程の取り方の基本が書いてあります。
GesやFisもありますよ。
======
【ファースト・ポジション】
■4の指
G線D、D線A、A線Eは、開放弦と同音ですから、ピッタリ合わせられます。音が吸い込まれる様に感じます。E線Hは少し難しいのですが、A-Eの幅で、E-Hを弾きます。重音で弾きたいのであれば、E線に対するA線Hを取り、そのオクターブでE線Hを弾きます。ピッタリ合わせて下さい。
■3の指
E線A、A線D、D線Gは響くので簡単です。G線Cは少し難しいのですが、3の指は全部同じ高さ、(E-Aの幅)=(A-Dの幅)=(D-Gの幅)=(G-Cの幅)です。全部同じ高さなので、慣れれば弾けます。ピアノよりも若干低めです。
■1の指
G線A、D線Eは、開放弦のオクターブ下なので響きます。A線HはE線との完全四度で弾けます。この(G-Aの幅)=(D-Eの幅)=(A-Hの幅)で、(E-Fisの幅)を弾きます。1の指の音も全部同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からH・Fis・Cis・Gis
1の指で取ったD線Eに対して完全四度の重音でG線Hを取ります。残りのFisCisGisはすべて同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からB・F・C・G
G線2オクターブにピッタリのE線Gが鳴らせます。この高さで、G・C・F・Bと弾きます。ピアノよりも低めです。
■1の指G線からAs・Es・B・F
2の指で取ったA線Cの完全四度上のE線Fを取ります。この高さで、As・Es・B・Fを弾きます。低めです。
■4の指G線からDes・As・Es・B
1の指で取ったA線Bのオクターブ上のE線Bを取ります。D線Esでもオクターブ上のA線Esが取れます。これも全部同じ高さで、Des・As・Es・Bが弾けます。結構低めです。
■3の指G線からCis・Gis・Dis・Ais
2の指で取ったFisやCisの完全四度下の重音で取ります。同じ高さでCis・Gis・Dis・Aisが弾けます。結構高めです。
■1の指G線からGis・Dis・Ais・Eis
3の指で取ったGis・Dis・Aisに対してオクターブ下です。全部同じ高さでEisも取れます。ベートーヴェンのメヌエットト長調でA線Aisが出てきます。結構高めです。
■3の指G線からCes・Ges・Des・As
既に取った1の指G線のAsに対して2オクターブのE線3の指Asを取ります。 導音が解れば、E線2の指Gを導音とする様に3の指でAsを取ります。
3の指の♭は全部同じ高さ、 (G-Cesの幅)=(D-Gesの幅)=(A-Desの幅)=(E-Asの幅) です。
【サード・ポジション】
■1の指
G線からC・G・D・Aに移動します。当たり前ですよね。
■4の指
G線からF・C・G・Dです。 G線に対する2オクターブ上のA線Gが取れますから、残りは全部同じ高さです。 響きますから、容易に取れます。
■3の指
G線EをE線との共鳴で取れます。G線からE・H・Fis・Cisが取れます。全部同じ高さです。結構高めです。 D線HをG線の5倍音で取ってしまうと低くなるので、注意が必要です。
■2の指
簡単です。G線からD・A・E・Hですね。全部同じ高さです。
■3の指を加筆 E線からC・F・B・Es
A線4指GをG開放弦の2オクターブの響きで取り、そのGに対して完全四度上のE線Cを重音で取ります。
C・F・B・Esは同じ高さで弾きます。 1の指のE線からA・D・G・Cに対して短三度(A-C)(D-F)(G-B)(C-Es)は全部同じ幅です。
結構低い音なのですが、低くなり過ぎない様に弾くのがポイントです。
======
メロディの音階を弾く時の基本として、ピタゴラス音律を更に極端に取る事が多いのが抜けています。
A-durを弾く場合、
「A-Hの幅」=「D-Eの幅」=「E-Fisの幅」≦「H-Cisの幅」≦「Fis-Gisの幅」
移動のドでは、ヴァイオリンの音程の取り方の原則、
ドレミファ/ソラシド
の組になっているので、「H-Cisの幅」≒「Fis-Gisの幅」としても良く、
長調の第3音と第7音は高めに取る、のが、ヴァイオリンの音程です。
パブロ・カザルス曰く、半音は全音の1/3と言っています。数学的ピタゴラス律では約44%になっています。
ヴァイオリンの音程は、更に「オクターブ伸張」を勘案する必要があります。
高い音はより高く、低い音はより低く、弾いた方が、正しい音程に聞こえるのが、人間の耳の特性です。
ピアノでは、レイルスバックカーブとして示されています。
http://78.media.tumblr.com/cee54fc842172c5844cc963d9abdfc9c/tumblr_nnmhd7vyTr1qdsqmfo1_500.jpg
ヴァイオリンの音程は、開放弦G・D・A・E迄は3/2周波数比で、弦楽合奏では時代によって、G-D、D-Aは、それを平均律にどれだけ近付けるか、狭くするか、1.96セントの幅で勘案します。A-E、E-HはEの3/2倍音としてよい、と思います。
Gは低くなり過ぎない様に注意が必要です。ミスっている例です。
https://youtu.be/9tfSH9Sm-Ek
「クレア・ホジキンズ」のGの調弦はホンの少し低めで、運弓のミスで更に低く成り過ぎて、言外にハイフェッツに指摘を受けています。耳の悪い人は、何処で指摘を受けたのか、解らないでしょう。尚、「クレア・ホジキンズ」は他の生徒とは立場と年齢が違い、ハイフェッツのアシスタントでした。
オクターブ伸張は、
「E線DはD線の4倍音で取ると低く聴こえる」
「E線のフラジオは、弦が新しくて正確な2倍音であっても、低めである」
明確に習います。
E線C・Cisは微妙です。ヴァイオリンのCは楽器自体が低めに響きを持っている事が多く、気を付けるべき音で、
「楽器の鳴りでCを弾くと低くなる」
これも習います。
しかし、一応、E線Cの根拠は、A線サードポジションでGの4倍音を取って、その完全四度上で、正しいE線Cとして良い、事になっています。
E線Cisは"Extensive Pythagoras"の関係もあり、高く取る事が多いと思います。
=====
純正律はメロディでは使わず、和声で使います。
完全五度(3/2)
完全四度(4/3)
完全八度(2/1)
大全音(9/8)
は、ピタゴラス律と同じです。
メロディと和声の音程の差が問題になるのは、長短三度と、オクターブの裏になる、短長六度です。
ピタゴラス音律の長三度は(9/8)^2=81/64
短三度は完全五度の裏ですから、(3/2)÷(81/64)
純正律の長三度は5/4(大全音+小全音)
純正律の短三度は6/5(完全五度と長三度の裏)
D線2の指をA線に合わせて、唸りが無く、F及びFisを取ると、純正律長短三度は容易に取れます。
長六度はオクターブと短三度の裏
短六度はオクターブと長三度の裏
=====
重音の音程の取り方の基本は、
①上の音をピタゴラスで弾き、下の音を純正で付ける
②下の音が開放弦とその偶数倍音なら、下の音に上の音を純正で付ける
③残響が少ない場所なら、どちらともピタゴラス音律で弾く
③'アルペジオも重音に準じて、残響の過多で取る音程が違い、残響の多い所では純正律で、少ない所ではピタゴラス律
④重音の次に同じ音のメロディが出て来る等、矛盾が出る場合、平均律っぽく弾いて誤魔化す
細かい所は違い、例外も沢山あるのですが、趣旨は、
へマン著「弦楽器のイントネーション」
https://www.amazon.co.jp/dp/4883952681
この本の解説みたいなものです。
疑問があれば、監修した海野義雄に問い合わせましょう。
https://ja-jp.facebook.com/mikio.unno
息子の幹雄に問い合わせれば何とかなるでしょう。
こちらも趣旨は同じです。
https://maki-music.net/weblec/ontei/
=====
短調は一般に3種類あるので、複雑ですが、短三度(第3音)を低めに取ります。
a-mollならCを低めに取り、FやGを低めに取る事が多いと思います。
更に、私のオリジナルです。
ヴァイオリン的短音階は、a-mollなら運指上、
AHCD/EFisGA
が基本形です。旋律的短音階の変形です。
旋律的短音階でGisで弾く場合は、高く取ると悲劇的な感じになります。
Fで弾いてFを低めに取ると、哀愁を帯びた感じになります。
F・GisでFを低く、Gisを高く弾くと、奇想的になります。
Hを低めに取ると、沈鬱な感じになります。
あじ氏、
>純正律短2度が133セントになっていますが、112セントですよね?
----純正律短二度は色々あります。
http://musica.art.coocan.jp/enharmonic.htm
http://www.niji.or.jp/home/ss1996/tech/psm.htm
多く使われるのは、16/15倍周波数比ですから、理論値は、約111.7セントで、あじ氏が正解です。増一度は更に狭いので、ヘマンの20ページの純正律短2度が133セントには、疑問があります。
===============
===============
http://fstrings.com/board/index.asp?id=53477#53575
abeg氏、
[53478]のリンク
http://fstrings.com/board/index.asp?id=51303#51329
にヴァイオリンの音程の取り方の基本が書いてあります。
GesやFisもありますよ。
======
【ファースト・ポジション】
■4の指
G線D、D線A、A線Eは、開放弦と同音ですから、ピッタリ合わせられます。音が吸い込まれる様に感じます。E線Hは少し難しいのですが、A-Eの幅で、E-Hを弾きます。重音で弾きたいのであれば、E線に対するA線Hを取り、そのオクターブでE線Hを弾きます。ピッタリ合わせて下さい。
■3の指
E線A、A線D、D線Gは響くので簡単です。G線Cは少し難しいのですが、3の指は全部同じ高さ、(E-Aの幅)=(A-Dの幅)=(D-Gの幅)=(G-Cの幅)です。全部同じ高さなので、慣れれば弾けます。ピアノよりも若干低めです。
■1の指
G線A、D線Eは、開放弦のオクターブ下なので響きます。A線HはE線との完全四度で弾けます。この(G-Aの幅)=(D-Eの幅)=(A-Hの幅)で、(E-Fisの幅)を弾きます。1の指の音も全部同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からH・Fis・Cis・Gis
1の指で取ったD線Eに対して完全四度の重音でG線Hを取ります。残りのFisCisGisはすべて同じ高さです。結構高めです。
■2の指G線からB・F・C・G
G線2オクターブにピッタリのE線Gが鳴らせます。この高さで、G・C・F・Bと弾きます。ピアノよりも低めです。
■1の指G線からAs・Es・B・F
2の指で取ったA線Cの完全四度上のE線Fを取ります。この高さで、As・Es・B・Fを弾きます。低めです。
■4の指G線からDes・As・Es・B
1の指で取ったA線Bのオクターブ上のE線Bを取ります。D線Esでもオクターブ上のA線Esが取れます。これも全部同じ高さで、Des・As・Es・Bが弾けます。結構低めです。
■3の指G線からCis・Gis・Dis・Ais
2の指で取ったFisやCisの完全四度下の重音で取ります。同じ高さでCis・Gis・Dis・Aisが弾けます。結構高めです。
■1の指G線からGis・Dis・Ais・Eis
3の指で取ったGis・Dis・Aisに対してオクターブ下です。全部同じ高さでEisも取れます。ベートーヴェンのメヌエットト長調でA線Aisが出てきます。結構高めです。
■3の指G線からCes・Ges・Des・As
既に取った1の指G線のAsに対して2オクターブのE線3の指Asを取ります。 導音が解れば、E線2の指Gを導音とする様に3の指でAsを取ります。
3の指の♭は全部同じ高さ、 (G-Cesの幅)=(D-Gesの幅)=(A-Desの幅)=(E-Asの幅) です。
【サード・ポジション】
■1の指
G線からC・G・D・Aに移動します。当たり前ですよね。
■4の指
G線からF・C・G・Dです。 G線に対する2オクターブ上のA線Gが取れますから、残りは全部同じ高さです。 響きますから、容易に取れます。
■3の指
G線EをE線との共鳴で取れます。G線からE・H・Fis・Cisが取れます。全部同じ高さです。結構高めです。 D線HをG線の5倍音で取ってしまうと低くなるので、注意が必要です。
■2の指
簡単です。G線からD・A・E・Hですね。全部同じ高さです。
■3の指を加筆 E線からC・F・B・Es
A線4指GをG開放弦の2オクターブの響きで取り、そのGに対して完全四度上のE線Cを重音で取ります。
C・F・B・Esは同じ高さで弾きます。 1の指のE線からA・D・G・Cに対して短三度(A-C)(D-F)(G-B)(C-Es)は全部同じ幅です。
結構低い音なのですが、低くなり過ぎない様に弾くのがポイントです。
======
メロディの音階を弾く時の基本として、ピタゴラス音律を更に極端に取る事が多いのが抜けています。
A-durを弾く場合、
「A-Hの幅」=「D-Eの幅」=「E-Fisの幅」≦「H-Cisの幅」≦「Fis-Gisの幅」
移動のドでは、ヴァイオリンの音程の取り方の原則、
ドレミファ/ソラシド
の組になっているので、「H-Cisの幅」≒「Fis-Gisの幅」としても良く、
長調の第3音と第7音は高めに取る、のが、ヴァイオリンの音程です。
パブロ・カザルス曰く、半音は全音の1/3と言っています。数学的ピタゴラス律では約44%になっています。
ヴァイオリンの音程は、更に「オクターブ伸張」を勘案する必要があります。
高い音はより高く、低い音はより低く、弾いた方が、正しい音程に聞こえるのが、人間の耳の特性です。
ピアノでは、レイルスバックカーブとして示されています。
http://78.media.tumblr.com/cee54fc842172c5844cc963d9abdfc9c/tumblr_nnmhd7vyTr1qdsqmfo1_500.jpg
ヴァイオリンの音程は、開放弦G・D・A・E迄は3/2周波数比で、弦楽合奏では時代によって、G-D、D-Aは、それを平均律にどれだけ近付けるか、狭くするか、1.96セントの幅で勘案します。A-E、E-HはEの3/2倍音としてよい、と思います。
Gは低くなり過ぎない様に注意が必要です。ミスっている例です。
https://youtu.be/9tfSH9Sm-Ek
「クレア・ホジキンズ」のGの調弦はホンの少し低めで、運弓のミスで更に低く成り過ぎて、言外にハイフェッツに指摘を受けています。耳の悪い人は、何処で指摘を受けたのか、解らないでしょう。尚、「クレア・ホジキンズ」は他の生徒とは立場と年齢が違い、ハイフェッツのアシスタントでした。
オクターブ伸張は、
「E線DはD線の4倍音で取ると低く聴こえる」
「E線のフラジオは、弦が新しくて正確な2倍音であっても、低めである」
明確に習います。
E線C・Cisは微妙です。ヴァイオリンのCは楽器自体が低めに響きを持っている事が多く、気を付けるべき音で、
「楽器の鳴りでCを弾くと低くなる」
これも習います。
しかし、一応、E線Cの根拠は、A線サードポジションでGの4倍音を取って、その完全四度上で、正しいE線Cとして良い、事になっています。
E線Cisは"Extensive Pythagoras"の関係もあり、高く取る事が多いと思います。
=====
純正律はメロディでは使わず、和声で使います。
完全五度(3/2)
完全四度(4/3)
完全八度(2/1)
大全音(9/8)
は、ピタゴラス律と同じです。
メロディと和声の音程の差が問題になるのは、長短三度と、オクターブの裏になる、短長六度です。
ピタゴラス音律の長三度は(9/8)^2=81/64
短三度は完全五度の裏ですから、(3/2)÷(81/64)
純正律の長三度は5/4(大全音+小全音)
純正律の短三度は6/5(完全五度と長三度の裏)
D線2の指をA線に合わせて、唸りが無く、F及びFisを取ると、純正律長短三度は容易に取れます。
長六度はオクターブと短三度の裏
短六度はオクターブと長三度の裏
=====
重音の音程の取り方の基本は、
①上の音をピタゴラスで弾き、下の音を純正で付ける
②下の音が開放弦とその偶数倍音なら、下の音に上の音を純正で付ける
③残響が少ない場所なら、どちらともピタゴラス音律で弾く
③'アルペジオも重音に準じて、残響の過多で取る音程が違い、残響の多い所では純正律で、少ない所ではピタゴラス律
④重音の次に同じ音のメロディが出て来る等、矛盾が出る場合、平均律っぽく弾いて誤魔化す
細かい所は違い、例外も沢山あるのですが、趣旨は、
へマン著「弦楽器のイントネーション」
https://www.amazon.co.jp/dp/4883952681
この本の解説みたいなものです。
疑問があれば、監修した海野義雄に問い合わせましょう。
https://ja-jp.facebook.com/mikio.unno
息子の幹雄に問い合わせれば何とかなるでしょう。
こちらも趣旨は同じです。
https://maki-music.net/weblec/ontei/
=====
短調は一般に3種類あるので、複雑ですが、短三度(第3音)を低めに取ります。
a-mollならCを低めに取り、FやGを低めに取る事が多いと思います。
更に、私のオリジナルです。
ヴァイオリン的短音階は、a-mollなら運指上、
AHCD/EFisGA
が基本形です。旋律的短音階の変形です。
旋律的短音階でGisで弾く場合は、高く取ると悲劇的な感じになります。
Fで弾いてFを低めに取ると、哀愁を帯びた感じになります。
F・GisでFを低く、Gisを高く弾くと、奇想的になります。
Hを低めに取ると、沈鬱な感じになります。
今回のは重音全弓でいいだよ。 調弦の話しだよ すぐに話しの本筋を外す山犬ポチン漢だゾ
知識やお金では通用しない事あって、もともと普通の才で、とっくに信用なく伏魔殿になってないか?「誹謗中傷を受ける[56314]
[56314]
音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月07日 11:39
投稿者:レモン娘(ID:KHFoB5Y)
大学生になってからバイオリンを始めた、所謂レイトスターターです。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
これまで楽器の経験もなく、恥を承知で書きますと、例えばラの音から始まる楽曲を一音ズラしてシから初めて通されるような演奏をされても気付かないくらいには音感がありません。
現在、調弦に苦戦しており、完全五度が合うと音の波が消えるというやり方を頑張っていますが、毎日1時間程波を聞き分けるのに時間をとっても、完全一致が分からず、また開放弦の音(ソレラミ)を押さえた時についても、一番響くと思うスポットでチューナーを見ても完全一致ではなく、非常に難しさを感じています。
調弦の時点において、どういう練習が良いといった技術的な要素や、どういう道具だと分かりやすいといった物理的要素は何かありますでしょうか?
個人的に感じた事ですが、先生が使ってるガット弦は波が分かりやすかったです。
pochi様やchitose様のような方から、誹謗中傷を受ける事は覚悟の上で書き込みをさせていただきておりますが、お手柔らかに何卒お願いいたします。
一つ名誉としては、柏木論争の始まりには柏木氏による過剰な非難があると認む
しかし、論争と言うより闘争であり柏木氏の排除へ追い込む段は不名誉だろう。 この辺りからもチューナーをけ嫌いしてないか? なにもチューナー君自体は何も悪くありません。 オーボエもお世話になりますからね。 目的に合わせて使えば良いでしょう
[56369]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月18日 07:04
投稿者:pochi(ID:QFYAcoA)
リンクが切れていますね。
こちらです。
https://youtu.be/d3pLwVhm7xY
調弦法もあります。
基準になるオーボエのAだけならチューナー大いに結構です。オーボエの基準に他の楽器を合わせるのは、チューナー無効なのですよ。
こちらです。
https://youtu.be/d3pLwVhm7xY
調弦法もあります。
基準になるオーボエのAだけならチューナー大いに結構です。オーボエの基準に他の楽器を合わせるのは、チューナー無効なのですよ。
[56370]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月18日 19:34
投稿者:pochi(ID:F1VAGXU)
結論として、
【同音がピッタリ解らない人は何をしても無駄で作音楽器には向かない】
のです。
「A」が「E」に聞こえる人も無理です。
世の中にはそんな人が半数(若しかしたら20人中19人)います。
【同音がピッタリ解らない人は何をしても無駄で作音楽器には向かない】
のです。
「A」が「E」に聞こえる人も無理です。
世の中にはそんな人が半数(若しかしたら20人中19人)います。
[56371]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月18日 20:22
投稿者:通りすがり(ID:Z3eYMWA)
うーん、これで松毬さんが、ハイフェッツの動画中pochiさんの指摘箇所を挙げられれば、知識だけでなく音感もあることの何よりの証明になりますし格好いいのですが…
[56372]
Re: 音感の鍛え方について
投稿日時:2025年11月18日 22:10
投稿者:マルコムX(ID:I2iZiVM)
あ〜〜、とはいえ56分もある動画の中から指摘箇所を探せというのも大変でしょ〜
間違い探しはひとまず置いておき、ヴァイオリンに興味がある人なら最初の5,6分でも見ればそのまま最後まで見てしまうかも知れませんが
まぁ、チューナーでヴァイオリンはムリですね
間違い探しはひとまず置いておき、ヴァイオリンに興味がある人なら最初の5,6分でも見ればそのまま最後まで見てしまうかも知れませんが
まぁ、チューナーでヴァイオリンはムリですね
ヴァイオリン掲示板に戻る
3 / 3 ページ [ 28コメント ]