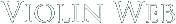不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[55691]
イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年01月18日 23:39
投稿者:よき(ID:iIBTNHA)
2大巨頭が亡くなった今のイタリアで最高峰に位置付けられるマエストロはどなたの名前が上がるのでしょうか?ビソロッティやモラッシーの弟子筋でも全く関係ない方でもいいです!
ヴァイオリン掲示板に戻る
3 / 4 ページ [ 30コメント ]
[55727]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年01月25日 21:44
投稿者:通りすがり(ID:InYBWXU)
Twoset violinの片方はScrollavezzaからアメリカの楽器に乗り換えてたはず。
イタリアのマエストロ??をありがたがる時代は終わったかも。
イタリアのマエストロ??をありがたがる時代は終わったかも。
[55728]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年01月25日 23:28
投稿者:pochi(ID:Njh0YTg)
[45120]
は存命です。
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Lisus
「Ojai」は「オジャイ」ではなくスペイン語風に「オーハイ」と読みます。カリフォルニアに引っ越したみたいです。
[45120]
Re: コストパフォーマンスの優れた楽器
投稿日時:2012年08月29日 16:28
投稿者:pochi(ID:EyRIKDA)
南アフリカの巨匠
ttp://www.lisusviolins.com/index.html
大凡100万円。
台湾人セミプロ(今はプロ)が持っていたのを弾いてみましたが、良いと思いました。
ttp://www.lisusviolins.com/index.html
大凡100万円。
台湾人セミプロ(今はプロ)が持っていたのを弾いてみましたが、良いと思いました。
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Lisus
「Ojai」は「オジャイ」ではなくスペイン語風に「オーハイ」と読みます。カリフォルニアに引っ越したみたいです。
[55736]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年02月08日 10:29
投稿者:通りすがり(ID:IDVVglc)
一昨年までヨーロッパ各国で仕事をしていましたが、けっこうぶっちゃけた事を言ってしまうとクレモナの2大巨匠なんてフレーズが通じるのはアメリカとアジア(特に日中韓)くらいだと思います。
意外かも知れませんが、その2人にドイツのカントゥーシャを加えて3大巨匠とする場合もありますが、ドイツでカントゥーシャの名前すら知らない愛好家や職人も珍しくありません。
日本では比較的最近になって、製作者や製作国によって音は変わらないって常識がようやく浸透してきましたが、ヨーロッパでは遙か昔からその考えでしたので、新作に関しては他国の職人の作品が入り込む余地がほとんどありませんでした。
ただ、イタリアは職人が飽和状態で自国の職人の手間賃よりも安い価格で流通するので、日本でいえばルーマニアやブルガリアの作品くらいの感覚で出回ってますね。
という事で、ヨーロッパの考え方が浸透してきた現代において、所謂巨匠や名人といった謳い文句は今後使われにくくあると予想します。
日本でも、こういう掲示板に集うマニアではない一般愛好家が何人国内の製作家の名前を挙げられるでしょうか?
クレモナ(とイタリアの一部)はまた別ですが、ドイツやフランスなんかでも、新作楽器は同じような現状ですし、日本人はクレモナの作者の名前なら知ってるだけ、あちらよりも不要な物知りかも知れません。
また、フランス型が広まったの20世紀以降、流派と呼べるような個性的な楽器を作る作者なんていましたっけ?
強いていえば、日本でも人気の某流派は職人からは素人流派のように言われております(エビデンスとして大家は師に就いて技術を学んだことがなく、今のモダンフレンチを祖とする作りからすればメチャクチャという意味)。いろいろ煩い世の中ですので、あえて名前もヒントも出しません。
ヤフコメなら、いいね0に対してそう思わないが1万超えるような内容は承知ですが、参考になれば。
意外かも知れませんが、その2人にドイツのカントゥーシャを加えて3大巨匠とする場合もありますが、ドイツでカントゥーシャの名前すら知らない愛好家や職人も珍しくありません。
日本では比較的最近になって、製作者や製作国によって音は変わらないって常識がようやく浸透してきましたが、ヨーロッパでは遙か昔からその考えでしたので、新作に関しては他国の職人の作品が入り込む余地がほとんどありませんでした。
ただ、イタリアは職人が飽和状態で自国の職人の手間賃よりも安い価格で流通するので、日本でいえばルーマニアやブルガリアの作品くらいの感覚で出回ってますね。
という事で、ヨーロッパの考え方が浸透してきた現代において、所謂巨匠や名人といった謳い文句は今後使われにくくあると予想します。
日本でも、こういう掲示板に集うマニアではない一般愛好家が何人国内の製作家の名前を挙げられるでしょうか?
クレモナ(とイタリアの一部)はまた別ですが、ドイツやフランスなんかでも、新作楽器は同じような現状ですし、日本人はクレモナの作者の名前なら知ってるだけ、あちらよりも不要な物知りかも知れません。
また、フランス型が広まったの20世紀以降、流派と呼べるような個性的な楽器を作る作者なんていましたっけ?
強いていえば、日本でも人気の某流派は職人からは素人流派のように言われております(エビデンスとして大家は師に就いて技術を学んだことがなく、今のモダンフレンチを祖とする作りからすればメチャクチャという意味)。いろいろ煩い世の中ですので、あえて名前もヒントも出しません。
ヤフコメなら、いいね0に対してそう思わないが1万超えるような内容は承知ですが、参考になれば。
[55737]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年02月08日 20:41
投稿者:よき(ID:JTV0ciI)
>>通りすがり様
コメントありがとうございます!面白いご意見だなと思いました!
一点気になったのは“モダンフレンチを祖とする”という部分です。
勉強不足なので教えて欲しいのですが、現代はストラドモデルなどが主流ではと思ったのですがフレンチが元になっている何かがあるんでしたっけ?
コメントありがとうございます!面白いご意見だなと思いました!
一点気になったのは“モダンフレンチを祖とする”という部分です。
勉強不足なので教えて欲しいのですが、現代はストラドモデルなどが主流ではと思ったのですがフレンチが元になっている何かがあるんでしたっけ?
[55738]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年02月09日 18:07
投稿者:別の通りすがり(ID:KXAJdgY)
クレモナを弦楽器製作の街として再興するにあたって設立された製作学校で教えてた人間がフランス人に学んだとかそういうことだったような。
確かなことはストラドの楽器製造の手法は受け継がれてないってことです。
確かなことはストラドの楽器製造の手法は受け継がれてないってことです。
[55905]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年05月16日 13:13
投稿者:松毬(ID:QTknMiA)
バイオリン(バロック)はイタリア生まれですが、そもそも話しの起点にあるイタリアオールドは、イタリア人とフランス人のハーフだから、生粋のストラディバリ人ではありません。
ストラディバリのDNAは、つむじと表裏板や横板に健在しますが、それはフレンチシステムの中で共存しています
フレンチモダンは、つむじと表裏板や横板もフランス人のようですが、その後、ミラノ・トリノ辺りで生まれたイタリアモダンは、父はハーフって感じだから、混血が進んだ子ですね。ストラディバリの孫がつむじと表裏板に横板を造る形ですが、母はフランスからの人でしょう。
ストラドバリ人のクォーターあたりか?、悪く言ってもエイス
DNAは復元されますが、未来へ進化を継ぐのは誰か?でしょう
ストラディバリのDNAは、つむじと表裏板や横板に健在しますが、それはフレンチシステムの中で共存しています
フレンチモダンは、つむじと表裏板や横板もフランス人のようですが、その後、ミラノ・トリノ辺りで生まれたイタリアモダンは、父はハーフって感じだから、混血が進んだ子ですね。ストラディバリの孫がつむじと表裏板に横板を造る形ですが、母はフランスからの人でしょう。
ストラドバリ人のクォーターあたりか?、悪く言ってもエイス
DNAは復元されますが、未来へ進化を継ぐのは誰か?でしょう
[55912]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年05月19日 07:49
投稿者:通りすがり(ID:IwCVKFc)
つむじ、ってスクロールの事ですか?
あそこは職人の製作精度やデザイン性を測る場所で音とは関係あんまりないかなって思ってるんですがどう思います?
あそこは職人の製作精度やデザイン性を測る場所で音とは関係あんまりないかなって思ってるんですがどう思います?
[55913]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年05月19日 10:26
投稿者:松毬(ID:JVM5RCU)
そう、頭のぐるぐるのこと。
芸術の都だからか、パリでピタゴラス律、1/2、2/3、、、の視覚デザインも楽器に与えたフランス人が手を出さずに残した部分。音に、全く無関係ではない(ペグ材でも変わる)様ですが、シンボリックな視覚デザイン性が高く、また、とても手が込んだ部分で作家の性格が現れると思います
イタリアでバイオリンが誕生した時、蝸牛ではなかったようですが、耳の構造なのか?蝸牛の糸蔵に換わって定着したよう
蝸牛 https://note.com/artrelay/n/neafdd8ff944b
芸術の都だからか、パリでピタゴラス律、1/2、2/3、、、の視覚デザインも楽器に与えたフランス人が手を出さずに残した部分。音に、全く無関係ではない(ペグ材でも変わる)様ですが、シンボリックな視覚デザイン性が高く、また、とても手が込んだ部分で作家の性格が現れると思います
イタリアでバイオリンが誕生した時、蝸牛ではなかったようですが、耳の構造なのか?蝸牛の糸蔵に換わって定着したよう
蝸牛 https://note.com/artrelay/n/neafdd8ff944b
[55914]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年05月19日 19:22
投稿者:松毬(ID:JVM5RCU)
因みに、
フランス人は機能美から、自然倍音(基音,倍音,3倍音,(5倍音))を元にしたピタゴラス比(律)を楽器に与えましたが、
イタリア人の美的感覚は、造形的に美しい黄金比を、渦巻きだけでなく響胴などバイオリン全体に用いたようです
バイオリンの黄金比
https://www.decagon.it/jhon/jhong.htm
https://violin-fumi-fukuda.com/making/2283/
などなど
但し、黄金比は音との関係とは何でしょうか?ピンとは来ません
もしかすると、失われたストラディバリ原人の製造技術[55738]
とは、この辺り音との関わりを解いた理論から楽器を造くったことならば、この理論を応用できた者が、新しいイタリアのマエストロになるかもしれませんよね??
フランス人は機能美から、自然倍音(基音,倍音,3倍音,(5倍音))を元にしたピタゴラス比(律)を楽器に与えましたが、
イタリア人の美的感覚は、造形的に美しい黄金比を、渦巻きだけでなく響胴などバイオリン全体に用いたようです
バイオリンの黄金比
https://www.decagon.it/jhon/jhong.htm
https://violin-fumi-fukuda.com/making/2283/
などなど
但し、黄金比は音との関係とは何でしょうか?ピンとは来ません
もしかすると、失われたストラディバリ原人の製造技術[55738]
[55738]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年02月09日 18:07
投稿者:別の通りすがり(ID:KXAJdgY)
クレモナを弦楽器製作の街として再興するにあたって設立された製作学校で教えてた人間がフランス人に学んだとかそういうことだったような。
確かなことはストラドの楽器製造の手法は受け継がれてないってことです。
確かなことはストラドの楽器製造の手法は受け継がれてないってことです。
[55916]
Re: イタリアのマエストロについて
投稿日時:2025年05月20日 04:14
投稿者:松毬(ID:OAUFYIA)
お待たせしました。
渦巻きは、音と関係して、ただのシンボルではなく実音に関与するようです
先ず、音のシンボルとして黄金比の渦巻き(蝸牛)があり、周波数特性フーリエ変換、オイラー空間、音律(純正律,ピタゴラス,平均律)と繋がっています
次に、現代楽器の多くは、ネック長にスクロール長さを加えピタゴラス寸法(2/3)を取り、その上で音に作用します
有名な例、2/3=ネック長130mm/ストップ長195mm
同様に、ネック&スクロール237mm/ボディー長356mm
(多くがスクロール長107mm、ボディー長356mm)
ネックの回転は知られており、上の例に加えて、ネック&スクロール/ボディー比も掛かり、渦巻きを替えると音が変わります。ペグ材を変えるのが易しいかも、、です
渦巻きは、どうもカウンターマスの位置にあり、モダンやオールドの様に大きく大胆な方から、現代は渦巻きが小さく端正に変えてパワーよりも回転レスポンスを上げた様に見えます
ネックの回転
http://www.jiyugaoka-violin.com/2015/archives/39777#more-39777
参考、他ピタゴラス比[54883]
[54256]
渦巻きは、音と関係して、ただのシンボルではなく実音に関与するようです
先ず、音のシンボルとして黄金比の渦巻き(蝸牛)があり、周波数特性フーリエ変換、オイラー空間、音律(純正律,ピタゴラス,平均律)と繋がっています
次に、現代楽器の多くは、ネック長にスクロール長さを加えピタゴラス寸法(2/3)を取り、その上で音に作用します
有名な例、2/3=ネック長130mm/ストップ長195mm
同様に、ネック&スクロール237mm/ボディー長356mm
(多くがスクロール長107mm、ボディー長356mm)
ネックの回転は知られており、上の例に加えて、ネック&スクロール/ボディー比も掛かり、渦巻きを替えると音が変わります。ペグ材を変えるのが易しいかも、、です
渦巻きは、どうもカウンターマスの位置にあり、モダンやオールドの様に大きく大胆な方から、現代は渦巻きが小さく端正に変えてパワーよりも回転レスポンスを上げた様に見えます
ネックの回転
http://www.jiyugaoka-violin.com/2015/archives/39777#more-39777
参考、他ピタゴラス比[54883]
[54883]
テールピースと駒の間の間隔
投稿日時:2024年02月04日 21:51
投稿者:TS(ID:YQMGcFA)
質問です。一般的には弦長(約32.5cm)の6分の1(約5.4cm)と言われていますが,それよりも短くした場合、または長くした場合の音や音量、弾いた感覚にどのような影響があるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
宜しくお願いいたします。
[54256]
テールピースと駒の間の距離 6:1について
投稿日時:2021年06月19日 01:24
投稿者:あい(ID:OQEHQAQ)
どなたか、なぜ上ナットから駒までの距離:駒からテールピース
までの距離=6:1の整数比がスタンダード位置なのか教えてくれませんか?
何が根拠になっているのですか?
までの距離=6:1の整数比がスタンダード位置なのか教えてくれませんか?
何が根拠になっているのですか?
ヴァイオリン掲示板に戻る
3 / 4 ページ [ 30コメント ]