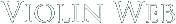不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[56234]
E線について
投稿日時:2025年10月16日 12:15
投稿者:ジュア(ID:OUhThyQ)
スレ汚しでしたらすみません。
素朴な疑問なのですが、E線を他の弦みたくナイロンコアの巻き線で仕上げたらどうなるのでしょうか?
戦時中の巨匠のインタビュー記事を見るとガットのE線は切れやすかったそうですが、当時ナイロン弦という概念が恐らくなかった事もあっていきなり金属の単線が出てきたようで、そのまま定着しています。
しかし現代の道具、技術でナイロンのE線を作ればガットよりは何とかなるものが出来そうな気がするのですが、どうなのでしょうか?
素朴な疑問なのですが、E線を他の弦みたくナイロンコアの巻き線で仕上げたらどうなるのでしょうか?
戦時中の巨匠のインタビュー記事を見るとガットのE線は切れやすかったそうですが、当時ナイロン弦という概念が恐らくなかった事もあっていきなり金属の単線が出てきたようで、そのまま定着しています。
しかし現代の道具、技術でナイロンのE線を作ればガットよりは何とかなるものが出来そうな気がするのですが、どうなのでしょうか?
ヴァイオリン掲示板に戻る
[ 4コメント ]
[56235]
Re: E線について
投稿日時:2025年10月16日 22:19
投稿者:松毬(ID:lBMpAZA)
ジュア様 初めまして、こんばんは
クラシックギターの弦みたいに、それは線径ゲージ0.7mmとあるから少し細いA線のような感じでしょう。
☟
ダダリオ ノーマル J45/EJ45
https://auranet.jp/salon/for-guitar-beginners/introduction-to-strings/string2-n/
太いので弾きにくくなり、音は、柔らかくまた複雑な音なんじゃないかなぁ?
昔からギターの6弦(最も低音) をバイオリンのD線に使う話しがあります[56199]
[56200]
。 バイオリンのE線ならクラシックギターの1弦(最も高音)をバイオリン用弦の長さにして(ざっくりと張力と弦長も合い)そのまま使えると思います。また、スチールコアにナイロン巻きのブラックナイロンもあるので面白いかも
音の予想は、他の弦での先例が参考になるでしょう
・パーペチュアルやワンダートーンのA線には、合成ポリマーとスチールがあるので良い比較になります。 その他ポリマー弦との比較の上でスチール弦のクロムコア スーパーフレックス ヘリコアなどは話題に上がって知るところです
・ギターでは、優しくピュアなクラシックガットギター(ナイロン弦)と明るく複雑なアコースティックフォークギター(金属コア巻弦)の比較で言われます
弦の歴史からは、ガット → 代替金属 → 代替ポリマー、と金属はポリマーよりかなり早いです。 ガットは細いほど切れやすく、その巻線は更に切れやすく、その為にA線E線に金属弦が用いられた結果で、金属も良くてE線はそのまま残りました[56199]
[56200]
[56201]
。 Aが巻線となっても未だにパーペチュアルやワンダートーンには金属コアA線が残ります
また、裸ポリマー(金属巻き無)弦は造れるでしょう。クロロカーボン弦もクラシックギター弦でもあるハズです。 なければ釣り糸で代用も
上のナイロンコアの巻線Eより太くなり、音は、優しくピュアになるんじゃない?
Gは巻きでも、D、Aは裸ガット弦[35834]
に対して裸ポリマーはどうか(天然高分子 Vs 人工高分子)?の点でも興味が沸きますね
クラシックギターの弦みたいに、それは線径ゲージ0.7mmとあるから少し細いA線のような感じでしょう。
☟
ダダリオ ノーマル J45/EJ45
https://auranet.jp/salon/for-guitar-beginners/introduction-to-strings/string2-n/
太いので弾きにくくなり、音は、柔らかくまた複雑な音なんじゃないかなぁ?
昔からギターの6弦(最も低音) をバイオリンのD線に使う話しがあります[56199]
[56199]
弦の歴史
投稿日時:2025年10月01日 06:30
投稿者:松毬(ID:M5gZmFA)
あまり詳しなこと言えないのですが、
弦の歴史に伴う流行に従って、オイドクサからドミナントに世界が変わったからのように見えて、つまりオリーブはドミナントに負けたようです。
因みに、弦のコアは、天然高分子 ➡️ 金属、及び、人工高分子に変わったことは革命的な技術革新です。 ドミナントは、オイドクサ、オリーブの巻きの革新を超えていたと言え、人工高分子弦の原点と言えます
[56189] でみれば、
1). 戦前デビューの巨匠は、ガット(天然高分子)弦のプレーンかオイドクサを使います。
2). 戦前でもスターン辺りからは、オイドクサからナイロン(化学合成による人工高分子)弦に変わっており、戦後はマーク・カプラン辺りまで、オイドクサ、オリーブ、人工高分子弦が混雑します。
3). その後、ケネディ以降は、人工高分子弦、花盛りへと変わります
弦の歴史は、
Ⅰ. キャットガット弦と言ったプレーンガットから、17世紀後半から Gの巻線が始まります。
1730年ごろには豊かな音の G の銀か銅巻線はプレーンに取って変わります。
Dでは巻きは難があったようです。 ギター弦では針金の半巻線が知られ、よく切れて普及しません
Ⅱ. 1900年代初頭 E にスチール弦が登場します。 バイオリンのほかでは14世紀には金属弦がありました。 大戦 Ⅰ 中、羊の腸が入手困難な上、金属加工技術の向上により金属弦に人気が出たようですが、、、
1920年頃はスチール弦はプロも使えるほどの品質でも、大戦 Ⅱ 頃までは「プロはガット弦を使うのが当たり前」という風潮だったそうです。 カール・フレッシュは「ヴァイオリン演奏の技術」(1923)でスチールのE線の利点について、オーケストラの団員にはコストの面でスチールのE線弦を推奨しています。「スチール弦では弦の交換が1週間に1回で使えるようになる」と書いてあり、ガットの耐久性は問題だったようです。 まだ、ピラストロ・コルダのような弦が標準だったようで、上1).のハイフェッツは、この頃の人です。 E にブラカットを、他は上 Ⅰ. のプレーンガット(だがG巻線)を使います。
なお、大戦 Ⅰ 後にDを全巻するためにアルミが使われます
Ⅲ.1951年に、ピラストロが アルミ巻ガットのA を開発して、D も、Gも巻線のガット弦が揃ったようで、この弦等が恐らくオイドクサのことのようです。 標準弦となるには10年近くを要したとも、高分子弦が出るまではピュアガットが標準弦ともあり少し混乱があります
ともあれ上1).2).ではオイドクサが使えました。 なお、オイストラフはAにガットではなく大戦 Ⅱ 前からのスティールで、これに信頼をよせたことに興味が持てます。 人工高分子弦に変わった今もAスティールはオプションで残ります(パーペチュアル, ワンダートーンなど)
Ⅳ. 1970年、トマスティークが「ドミナント」を発売しました。 その後、ピンカス・ズーカーマンとイツァーク・パールマンがこの弦を使ったことをきっかけに、バイオリンの弦はガットからナイロン(人工高分子)へと勢力図が大きく変わることとなります。 湿度の影響を受けずチューニングが高い実用性を重視して(人工高分子)合成弦への移行が進んだと言われています
Ⅴ. オリーブはどうだったか、いつからか不詳。
なのですが、上 2).では時期的にドミナントと被った様子で、すでに流行はオイドクサからドミナントら人工高分子弦の方に大きく舵を切っていて、結果的にオリーブはキョンファ、カプランに限られたと見えます
弦の歴史に伴う流行に従って、オイドクサからドミナントに世界が変わったからのように見えて、つまりオリーブはドミナントに負けたようです。
因みに、弦のコアは、天然高分子 ➡️ 金属、及び、人工高分子に変わったことは革命的な技術革新です。 ドミナントは、オイドクサ、オリーブの巻きの革新を超えていたと言え、人工高分子弦の原点と言えます
[56189] でみれば、
1). 戦前デビューの巨匠は、ガット(天然高分子)弦のプレーンかオイドクサを使います。
2). 戦前でもスターン辺りからは、オイドクサからナイロン(化学合成による人工高分子)弦に変わっており、戦後はマーク・カプラン辺りまで、オイドクサ、オリーブ、人工高分子弦が混雑します。
3). その後、ケネディ以降は、人工高分子弦、花盛りへと変わります
弦の歴史は、
Ⅰ. キャットガット弦と言ったプレーンガットから、17世紀後半から Gの巻線が始まります。
1730年ごろには豊かな音の G の銀か銅巻線はプレーンに取って変わります。
Dでは巻きは難があったようです。 ギター弦では針金の半巻線が知られ、よく切れて普及しません
Ⅱ. 1900年代初頭 E にスチール弦が登場します。 バイオリンのほかでは14世紀には金属弦がありました。 大戦 Ⅰ 中、羊の腸が入手困難な上、金属加工技術の向上により金属弦に人気が出たようですが、、、
1920年頃はスチール弦はプロも使えるほどの品質でも、大戦 Ⅱ 頃までは「プロはガット弦を使うのが当たり前」という風潮だったそうです。 カール・フレッシュは「ヴァイオリン演奏の技術」(1923)でスチールのE線の利点について、オーケストラの団員にはコストの面でスチールのE線弦を推奨しています。「スチール弦では弦の交換が1週間に1回で使えるようになる」と書いてあり、ガットの耐久性は問題だったようです。 まだ、ピラストロ・コルダのような弦が標準だったようで、上1).のハイフェッツは、この頃の人です。 E にブラカットを、他は上 Ⅰ. のプレーンガット(だがG巻線)を使います。
なお、大戦 Ⅰ 後にDを全巻するためにアルミが使われます
Ⅲ.1951年に、ピラストロが アルミ巻ガットのA を開発して、D も、Gも巻線のガット弦が揃ったようで、この弦等が恐らくオイドクサのことのようです。 標準弦となるには10年近くを要したとも、高分子弦が出るまではピュアガットが標準弦ともあり少し混乱があります
ともあれ上1).2).ではオイドクサが使えました。 なお、オイストラフはAにガットではなく大戦 Ⅱ 前からのスティールで、これに信頼をよせたことに興味が持てます。 人工高分子弦に変わった今もAスティールはオプションで残ります(パーペチュアル, ワンダートーンなど)
Ⅳ. 1970年、トマスティークが「ドミナント」を発売しました。 その後、ピンカス・ズーカーマンとイツァーク・パールマンがこの弦を使ったことをきっかけに、バイオリンの弦はガットからナイロン(人工高分子)へと勢力図が大きく変わることとなります。 湿度の影響を受けずチューニングが高い実用性を重視して(人工高分子)合成弦への移行が進んだと言われています
Ⅴ. オリーブはどうだったか、いつからか不詳。
なのですが、上 2).では時期的にドミナントと被った様子で、すでに流行はオイドクサからドミナントら人工高分子弦の方に大きく舵を切っていて、結果的にオリーブはキョンファ、カプランに限られたと見えます
[56200]
Re: オリーブ弦の質問
投稿日時:2025年10月01日 06:43
投稿者:松毬(ID:M5gZmFA)
[56199] 出典
https://www.musictrendz.com/post/what-is-the-history-of-violin-strings
https://amorimfineviolins.com/our-blog/violin-strings-theory-and-history/
https://rearpond.mystrikingly.com/blog/9ea417fb084
https://musicalinstrumenthire.com/violin-strings-differences/
https://www.musictrendz.com/post/what-is-the-history-of-violin-strings
https://amorimfineviolins.com/our-blog/violin-strings-theory-and-history/
https://rearpond.mystrikingly.com/blog/9ea417fb084
https://musicalinstrumenthire.com/violin-strings-differences/
音の予想は、他の弦での先例が参考になるでしょう
・パーペチュアルやワンダートーンのA線には、合成ポリマーとスチールがあるので良い比較になります。 その他ポリマー弦との比較の上でスチール弦のクロムコア スーパーフレックス ヘリコアなどは話題に上がって知るところです
・ギターでは、優しくピュアなクラシックガットギター(ナイロン弦)と明るく複雑なアコースティックフォークギター(金属コア巻弦)の比較で言われます
弦の歴史からは、ガット → 代替金属 → 代替ポリマー、と金属はポリマーよりかなり早いです。 ガットは細いほど切れやすく、その巻線は更に切れやすく、その為にA線E線に金属弦が用いられた結果で、金属も良くてE線はそのまま残りました[56199]
[56199]
弦の歴史
投稿日時:2025年10月01日 06:30
投稿者:松毬(ID:M5gZmFA)
あまり詳しなこと言えないのですが、
弦の歴史に伴う流行に従って、オイドクサからドミナントに世界が変わったからのように見えて、つまりオリーブはドミナントに負けたようです。
因みに、弦のコアは、天然高分子 ➡️ 金属、及び、人工高分子に変わったことは革命的な技術革新です。 ドミナントは、オイドクサ、オリーブの巻きの革新を超えていたと言え、人工高分子弦の原点と言えます
[56189] でみれば、
1). 戦前デビューの巨匠は、ガット(天然高分子)弦のプレーンかオイドクサを使います。
2). 戦前でもスターン辺りからは、オイドクサからナイロン(化学合成による人工高分子)弦に変わっており、戦後はマーク・カプラン辺りまで、オイドクサ、オリーブ、人工高分子弦が混雑します。
3). その後、ケネディ以降は、人工高分子弦、花盛りへと変わります
弦の歴史は、
Ⅰ. キャットガット弦と言ったプレーンガットから、17世紀後半から Gの巻線が始まります。
1730年ごろには豊かな音の G の銀か銅巻線はプレーンに取って変わります。
Dでは巻きは難があったようです。 ギター弦では針金の半巻線が知られ、よく切れて普及しません
Ⅱ. 1900年代初頭 E にスチール弦が登場します。 バイオリンのほかでは14世紀には金属弦がありました。 大戦 Ⅰ 中、羊の腸が入手困難な上、金属加工技術の向上により金属弦に人気が出たようですが、、、
1920年頃はスチール弦はプロも使えるほどの品質でも、大戦 Ⅱ 頃までは「プロはガット弦を使うのが当たり前」という風潮だったそうです。 カール・フレッシュは「ヴァイオリン演奏の技術」(1923)でスチールのE線の利点について、オーケストラの団員にはコストの面でスチールのE線弦を推奨しています。「スチール弦では弦の交換が1週間に1回で使えるようになる」と書いてあり、ガットの耐久性は問題だったようです。 まだ、ピラストロ・コルダのような弦が標準だったようで、上1).のハイフェッツは、この頃の人です。 E にブラカットを、他は上 Ⅰ. のプレーンガット(だがG巻線)を使います。
なお、大戦 Ⅰ 後にDを全巻するためにアルミが使われます
Ⅲ.1951年に、ピラストロが アルミ巻ガットのA を開発して、D も、Gも巻線のガット弦が揃ったようで、この弦等が恐らくオイドクサのことのようです。 標準弦となるには10年近くを要したとも、高分子弦が出るまではピュアガットが標準弦ともあり少し混乱があります
ともあれ上1).2).ではオイドクサが使えました。 なお、オイストラフはAにガットではなく大戦 Ⅱ 前からのスティールで、これに信頼をよせたことに興味が持てます。 人工高分子弦に変わった今もAスティールはオプションで残ります(パーペチュアル, ワンダートーンなど)
Ⅳ. 1970年、トマスティークが「ドミナント」を発売しました。 その後、ピンカス・ズーカーマンとイツァーク・パールマンがこの弦を使ったことをきっかけに、バイオリンの弦はガットからナイロン(人工高分子)へと勢力図が大きく変わることとなります。 湿度の影響を受けずチューニングが高い実用性を重視して(人工高分子)合成弦への移行が進んだと言われています
Ⅴ. オリーブはどうだったか、いつからか不詳。
なのですが、上 2).では時期的にドミナントと被った様子で、すでに流行はオイドクサからドミナントら人工高分子弦の方に大きく舵を切っていて、結果的にオリーブはキョンファ、カプランに限られたと見えます
弦の歴史に伴う流行に従って、オイドクサからドミナントに世界が変わったからのように見えて、つまりオリーブはドミナントに負けたようです。
因みに、弦のコアは、天然高分子 ➡️ 金属、及び、人工高分子に変わったことは革命的な技術革新です。 ドミナントは、オイドクサ、オリーブの巻きの革新を超えていたと言え、人工高分子弦の原点と言えます
[56189] でみれば、
1). 戦前デビューの巨匠は、ガット(天然高分子)弦のプレーンかオイドクサを使います。
2). 戦前でもスターン辺りからは、オイドクサからナイロン(化学合成による人工高分子)弦に変わっており、戦後はマーク・カプラン辺りまで、オイドクサ、オリーブ、人工高分子弦が混雑します。
3). その後、ケネディ以降は、人工高分子弦、花盛りへと変わります
弦の歴史は、
Ⅰ. キャットガット弦と言ったプレーンガットから、17世紀後半から Gの巻線が始まります。
1730年ごろには豊かな音の G の銀か銅巻線はプレーンに取って変わります。
Dでは巻きは難があったようです。 ギター弦では針金の半巻線が知られ、よく切れて普及しません
Ⅱ. 1900年代初頭 E にスチール弦が登場します。 バイオリンのほかでは14世紀には金属弦がありました。 大戦 Ⅰ 中、羊の腸が入手困難な上、金属加工技術の向上により金属弦に人気が出たようですが、、、
1920年頃はスチール弦はプロも使えるほどの品質でも、大戦 Ⅱ 頃までは「プロはガット弦を使うのが当たり前」という風潮だったそうです。 カール・フレッシュは「ヴァイオリン演奏の技術」(1923)でスチールのE線の利点について、オーケストラの団員にはコストの面でスチールのE線弦を推奨しています。「スチール弦では弦の交換が1週間に1回で使えるようになる」と書いてあり、ガットの耐久性は問題だったようです。 まだ、ピラストロ・コルダのような弦が標準だったようで、上1).のハイフェッツは、この頃の人です。 E にブラカットを、他は上 Ⅰ. のプレーンガット(だがG巻線)を使います。
なお、大戦 Ⅰ 後にDを全巻するためにアルミが使われます
Ⅲ.1951年に、ピラストロが アルミ巻ガットのA を開発して、D も、Gも巻線のガット弦が揃ったようで、この弦等が恐らくオイドクサのことのようです。 標準弦となるには10年近くを要したとも、高分子弦が出るまではピュアガットが標準弦ともあり少し混乱があります
ともあれ上1).2).ではオイドクサが使えました。 なお、オイストラフはAにガットではなく大戦 Ⅱ 前からのスティールで、これに信頼をよせたことに興味が持てます。 人工高分子弦に変わった今もAスティールはオプションで残ります(パーペチュアル, ワンダートーンなど)
Ⅳ. 1970年、トマスティークが「ドミナント」を発売しました。 その後、ピンカス・ズーカーマンとイツァーク・パールマンがこの弦を使ったことをきっかけに、バイオリンの弦はガットからナイロン(人工高分子)へと勢力図が大きく変わることとなります。 湿度の影響を受けずチューニングが高い実用性を重視して(人工高分子)合成弦への移行が進んだと言われています
Ⅴ. オリーブはどうだったか、いつからか不詳。
なのですが、上 2).では時期的にドミナントと被った様子で、すでに流行はオイドクサからドミナントら人工高分子弦の方に大きく舵を切っていて、結果的にオリーブはキョンファ、カプランに限られたと見えます
[56200]
Re: オリーブ弦の質問
投稿日時:2025年10月01日 06:43
投稿者:松毬(ID:M5gZmFA)
[56199] 出典
https://www.musictrendz.com/post/what-is-the-history-of-violin-strings
https://amorimfineviolins.com/our-blog/violin-strings-theory-and-history/
https://rearpond.mystrikingly.com/blog/9ea417fb084
https://musicalinstrumenthire.com/violin-strings-differences/
https://www.musictrendz.com/post/what-is-the-history-of-violin-strings
https://amorimfineviolins.com/our-blog/violin-strings-theory-and-history/
https://rearpond.mystrikingly.com/blog/9ea417fb084
https://musicalinstrumenthire.com/violin-strings-differences/
[56201]
弦の歴史 (続きと誤植訂正)
投稿日時:2025年10月02日 03:59
投稿者:松毬(ID:NodwQBE)
Ⅴ. 1965年、どうもこの年オリーブが発売されたようです。この弦は、オイドクサを進化させた弦です。 音量を上げて豊かな音を目指して、重くして張力を上げ、また、金巻きで重くしながらガットコアも細くした弦のようです。 そのガットの新技術開発を要してオイドクサから遅れて発売され、また、とても高価でます。
音は最高との評判ですが、、、その他の問題は残して現在の最新技術のガットは、パッシオーネへと変わりました
オリーブ発売は、オイドクサの時とは異なりドミナント(1970-)がオリーブを追いかける様に被さって競争します。 日本市場では、20世紀末ごろまで、[56199] 2). のようにオイドクサやオリーブなどガットとドミナントらなどが主流と考えられていました。 また、この頃の演奏家にはオリーブを使ったツィンマーマンもいます。 [56189] https://kazukingband.hatenablog.com/entry/20150918/1442559461
競争の結果、21世紀の今はドミナントら主流と軍配が上がりました[56199] 。 万人へドミナントの扱い易さが勝因でしょう。 また、多少のコストや音量、音色よりも、ステージでは演奏中に、頻繁にピッチが狂った切れたは困りますね
以上([56199] 含)は、ざっくりと、先の[56188] [56190]の風潮とも合うと思います
なお、オリーブ弦の情報は、下記にもあるのでご参考に (良し悪しは別として)
[16543] ガット弦
[a17268] オリーブ弦
[28552] オリーヴについて
[29958] オリーブの弦について
[39998] オリーブの寿命
[32906] 新しいピラストロ社の弦 ←パッシオーネ
などなど
音は最高との評判ですが、、、その他の問題は残して現在の最新技術のガットは、パッシオーネへと変わりました
オリーブ発売は、オイドクサの時とは異なりドミナント(1970-)がオリーブを追いかける様に被さって競争します。 日本市場では、20世紀末ごろまで、[56199] 2). のようにオイドクサやオリーブなどガットとドミナントらなどが主流と考えられていました。 また、この頃の演奏家にはオリーブを使ったツィンマーマンもいます。 [56189] https://kazukingband.hatenablog.com/entry/20150918/1442559461
競争の結果、21世紀の今はドミナントら主流と軍配が上がりました[56199] 。 万人へドミナントの扱い易さが勝因でしょう。 また、多少のコストや音量、音色よりも、ステージでは演奏中に、頻繁にピッチが狂った切れたは困りますね
以上([56199] 含)は、ざっくりと、先の[56188] [56190]の風潮とも合うと思います
なお、オリーブ弦の情報は、下記にもあるのでご参考に (良し悪しは別として)
[16543] ガット弦
[a17268] オリーブ弦
[28552] オリーヴについて
[29958] オリーブの弦について
[39998] オリーブの寿命
[32906] 新しいピラストロ社の弦 ←パッシオーネ
などなど
また、裸ポリマー(金属巻き無)弦は造れるでしょう。クロロカーボン弦もクラシックギター弦でもあるハズです。 なければ釣り糸で代用も
上のナイロンコアの巻線Eより太くなり、音は、優しくピュアになるんじゃない?
Gは巻きでも、D、Aは裸ガット弦[35834]
[35834]
裸のガット弦(プレーンガット弦)を試す!
投稿日時:2007年12月08日 11:01
投稿者:ブルーベリー(ID:MlBRJJg)
ピッチの低い古楽器(バロックヴァイオリン)ではなく、A=440~443Hzの現代の普通のヴァイオリンに「裸のガット弦(プレーンガット弦)を試す!」ということでスレッドを立ち上げます。
最近、一部のヴァイオリン奏者の間で、裸のガット弦を使うという現象が見られるので、自分も試してみることにしました。
ttp://fstrings.com/board/index.asp?id=35733&page=1&sort=&t=
今回買ったのは、イタリアのTORO社のシープガット弦です。㈲コースタルトレーディングさんから通販で買うことができます。
ttp://coastaltrading.biz/viole.html
裸のガット弦には、ニスがかけられていないナチュラル仕上げのものと、ニスがかけられているニス仕上げのものがありますが、自分は手に汗をかくのでニス仕上げのものを買いました。
ゲージは下記のとおり、各弦数種類用意されていますが、とりあえず、一番細いゲージから試してみることにしました。
ttp://coastaltrading.biz/HPData/TORO%20PriceList%202007.pdf
自分は、E線はスチール(オリーヴなどなど)、A・D線は裸のガット、G線は銀巻きのガット、という組み合わせを試します。(弦の銘柄は違いますが)ハイフェッツはそういう組み合わせを好んでいたようです。ほんの30年前くらい前までは、そういう組み合わせで弾いている奏者がいたわけですから、それほど昔の話というわけでもありませんね。
自分は今までピラストロのオリーヴを使っていたので、ガット弦の特性はある程度理解しているつもりですが、裸のガットは初体験なので、どんな音が出るのか全く予想がつきません。
それでは、これから張ってみようと思います。
最近、一部のヴァイオリン奏者の間で、裸のガット弦を使うという現象が見られるので、自分も試してみることにしました。
ttp://fstrings.com/board/index.asp?id=35733&page=1&sort=&t=
今回買ったのは、イタリアのTORO社のシープガット弦です。㈲コースタルトレーディングさんから通販で買うことができます。
ttp://coastaltrading.biz/viole.html
裸のガット弦には、ニスがかけられていないナチュラル仕上げのものと、ニスがかけられているニス仕上げのものがありますが、自分は手に汗をかくのでニス仕上げのものを買いました。
ゲージは下記のとおり、各弦数種類用意されていますが、とりあえず、一番細いゲージから試してみることにしました。
ttp://coastaltrading.biz/HPData/TORO%20PriceList%202007.pdf
自分は、E線はスチール(オリーヴなどなど)、A・D線は裸のガット、G線は銀巻きのガット、という組み合わせを試します。(弦の銘柄は違いますが)ハイフェッツはそういう組み合わせを好んでいたようです。ほんの30年前くらい前までは、そういう組み合わせで弾いている奏者がいたわけですから、それほど昔の話というわけでもありませんね。
自分は今までピラストロのオリーヴを使っていたので、ガット弦の特性はある程度理解しているつもりですが、裸のガットは初体験なので、どんな音が出るのか全く予想がつきません。
それでは、これから張ってみようと思います。
[56236]
Re: E線について
投稿日時:2025年10月16日 22:58
投稿者:松毬(ID:lBMpAZA)
訂正:昔からギターの4弦(低音の3番目) をバイオリンのD線に使う
[56246]
Re: E線について
投稿日時:2025年10月19日 19:07
投稿者:pochi(ID:c2JocGA)
私は19歳のジョシダイセイですが40年位前迄は、絹芯金属巻E線がありました。物理的耐久性が低く、音量が小さいから、ガット金属巻ADG(例えばオイドクサ)とは合いませんでした。音の感じは「しーーー」という様な感じでした。
「ナイロン」は絹の代替人工繊維ですよね。ストッキングで実用化されました。
「ナイロン」は絹の代替人工繊維ですよね。ストッキングで実用化されました。
[56248]
Re: E線について
投稿日時:2025年10月20日 01:54
投稿者:調弦苦手(ID:KQh4cpM)
pochiさんは19歳のジョシダイセイかつ、179cmある日本人の大男かつ、天狗のようです。[6396]
[11308]
https://www.fstrings.com/board/topic/5909/?c=6396#6396
https://www.fstrings.com/board/topic/11303/?c=11308#11308
[6396]
ヤッシャから直接聞いた事
投稿日時:2003年11月05日 11:27
投稿者:pochi(ID:NWFSOWM)
管理人さんへこの話はこのスレッドに合わないので、御自由に消去して下さい。
ハイフェッツは晩年自分でも言っていましたが、彼の弓の持ち方は現代的ではないとの事です。右手の人さし指の関節を使っていないのです。その分、手首と肘と脇の関節で辻褄を合わせています。ロシアンボウイングと言います。現代ではハイフェッツの奏法は教科書的とは言えません。
> 最大限の演奏効果を上げるために演奏家はもっとも自分に合うテクニックを開発するのですね。
各人、指の長さ(各指の長さのバランス)も腕の長さも関節の硬さも違いますので、各々に開発します。例えば、私は179cmある日本人としては大男ですが、手が小さくて指先が非常に細くて、肉が少ないのです。指の細さはパールマンの半分位です。見た目ではなく、実際に較べました。左手の指先が細くて肉が少ない場合は、指を寝かせ気味にして弾くと、ヴィブラートの掛かりが良く、重厚な音が出せます。昔、理解のない先生の前でこれをすると叱られました。しかし、指先が細いためにハイポジションの音程は非常に正確に取れ、しかもE線では輝かしい独特の音が出せます。
> むかしメニューインが来日したとき、日本の先生方は「子供にみせると弓がゆがむから教育上良くない」と色めきたったそうです
故アイザック・スターン氏も間近で見ると先弓で腕が手前に引けていました。直角ではありませんでした。色めき立つ事ではありませんね。
最晩年のメニューインに関しても面白いエピソードがあるのですが、今回は止めておきます。
ハイフェッツは晩年自分でも言っていましたが、彼の弓の持ち方は現代的ではないとの事です。右手の人さし指の関節を使っていないのです。その分、手首と肘と脇の関節で辻褄を合わせています。ロシアンボウイングと言います。現代ではハイフェッツの奏法は教科書的とは言えません。
> 最大限の演奏効果を上げるために演奏家はもっとも自分に合うテクニックを開発するのですね。
各人、指の長さ(各指の長さのバランス)も腕の長さも関節の硬さも違いますので、各々に開発します。例えば、私は179cmある日本人としては大男ですが、手が小さくて指先が非常に細くて、肉が少ないのです。指の細さはパールマンの半分位です。見た目ではなく、実際に較べました。左手の指先が細くて肉が少ない場合は、指を寝かせ気味にして弾くと、ヴィブラートの掛かりが良く、重厚な音が出せます。昔、理解のない先生の前でこれをすると叱られました。しかし、指先が細いためにハイポジションの音程は非常に正確に取れ、しかもE線では輝かしい独特の音が出せます。
> むかしメニューインが来日したとき、日本の先生方は「子供にみせると弓がゆがむから教育上良くない」と色めきたったそうです
故アイザック・スターン氏も間近で見ると先弓で腕が手前に引けていました。直角ではありませんでした。色めき立つ事ではありませんね。
最晩年のメニューインに関しても面白いエピソードがあるのですが、今回は止めておきます。
[11308]
Re: 予算100万で一生ものの楽器
投稿日時:2004年03月24日 00:46
投稿者:pochi(ID:FgIDFkI)
Mario Gaddaの真作は、100万円では買えません。
こんな質問に真正面から解答を書けるのは、私だけなので、書き込みます。
あなたが日本に御住まいで、日本に永住する御心算で有るのなら、
鈴木郁子師
〒569-0086 大阪府高槻市松原町6-3 バイオリン工房 クレモナ
Tel.0726-75-9871 Fax.0726-75-9871
e-mail:ikuko-suzuki@kcc.zaq.ne.jp
の最新作を御勧め致します。
見れば見る程、美しい楽器で、弾けば弾く程愛情が湧くと思います。この人は、今日の所、日本では、手を抜いて作品を造る事は絶対に出来無い立場に有ります。値段は、100万円です。御買い得間違い無しです。明日の事は知りません。
私は、ビソロッティ・モラッシ・スコラリ・コニア依りも好きです。非常に繊細で密度感の濃い音が出ます。音量・弾き易さは中位です。ストラディ型に近いオリジナルの作風です。アーチが独特です。非常に良い材料を使って居ます。引きこなすのに2000時間程掛かるでしょう。現在生きている人が死ぬ迄に、弾き潰す事は、略不可能でしょう。
こんな事を書き込んだら、値段が跳ね上がるのでは無いかと恐れて居ります。
清水の舞台から飛び降りた投稿でした。でも私は天狗だから、死な無いのです。
楽器には当たり外れが有る事も忘れずに、、、
こんな質問に真正面から解答を書けるのは、私だけなので、書き込みます。
あなたが日本に御住まいで、日本に永住する御心算で有るのなら、
鈴木郁子師
〒569-0086 大阪府高槻市松原町6-3 バイオリン工房 クレモナ
Tel.0726-75-9871 Fax.0726-75-9871
e-mail:ikuko-suzuki@kcc.zaq.ne.jp
の最新作を御勧め致します。
見れば見る程、美しい楽器で、弾けば弾く程愛情が湧くと思います。この人は、今日の所、日本では、手を抜いて作品を造る事は絶対に出来無い立場に有ります。値段は、100万円です。御買い得間違い無しです。明日の事は知りません。
私は、ビソロッティ・モラッシ・スコラリ・コニア依りも好きです。非常に繊細で密度感の濃い音が出ます。音量・弾き易さは中位です。ストラディ型に近いオリジナルの作風です。アーチが独特です。非常に良い材料を使って居ます。引きこなすのに2000時間程掛かるでしょう。現在生きている人が死ぬ迄に、弾き潰す事は、略不可能でしょう。
こんな事を書き込んだら、値段が跳ね上がるのでは無いかと恐れて居ります。
清水の舞台から飛び降りた投稿でした。でも私は天狗だから、死な無いのです。
楽器には当たり外れが有る事も忘れずに、、、
https://www.fstrings.com/board/topic/5909/?c=6396#6396
https://www.fstrings.com/board/topic/11303/?c=11308#11308
ヴァイオリン掲示板に戻る
[ 4コメント ]