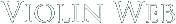不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[55131]
誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2024年06月02日 00:16
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
これからのスズキバイオリン等はどうあるのか??皆さまが思ったように誠に勝手に書いて戴けませんか??
[55125]
、[55130]
のお話しがあり、また、[55126]
もあります。これからは、今までのスズキバイオリンなどは不要なんじゃないかなぁ??と思いがふつふつと沸き、パンパンに膨らみます。
例えば、モラッシーやビソロッティのような誰も欲しがるブランド楽器は作れないし、楽器として10seriesと言っても中国製と同じかもしれないし、中級や初級の学習用楽器でも、高品質で低価格なメーカーが多く存在していてスズキなどの立場がないでしょう。そして、何もスズキだけでなく、ピグマリウスについても同じことが言えるのでは??と思います。
そこで、これからのスズキバイオリンやピグマリスは、どうあるのか??誠に勝手に想像してコメントして頂きたいです。気軽に楽しみながら、よろしくお願いいたします。
[55125]
[55125]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月31日 12:26
投稿者:Woody(ID:FiBFYEA)
今のスズキは経営難でファンドからきた経営者の元で再建すべく奮闘しているようですが、まともな楽器の製作はできない状態です。
過去に分業で作った各パーツの組み立てと塗装を国内で行なっているようですが、新規製作に必要な設備は既に売却もしくは廃棄しております。
中国製のホワイトに日本でニス塗ってスズキのラベルを貼っただけの楽器が既に主流で、今後はブランド名だけで収益を上げる戦略のようです。
川口氏が工場長で#2000を手作りしていた20年前と今では全く別会社です。
過去に分業で作った各パーツの組み立てと塗装を国内で行なっているようですが、新規製作に必要な設備は既に売却もしくは廃棄しております。
中国製のホワイトに日本でニス塗ってスズキのラベルを貼っただけの楽器が既に主流で、今後はブランド名だけで収益を上げる戦略のようです。
川口氏が工場長で#2000を手作りしていた20年前と今では全く別会社です。
[55130]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年06月01日 23:06
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
訂正: 畏(かしこ)くも :です
さて、Woody 様 ありがとうございます。
私の[55083] 〉これを書いていて実はスズキは絶滅危惧種じゃないかなぁ、と思うようになりました。これからは存在意義がないんじゃぁないか
を裏付けたWoody 様のコメントで、裏を返すと今後への期待と20年前を懐かしむようにも思いました。私の本心では、川口氏ら工長らが居ても倒産??の勢いです。
今のスズキは、大正時代、第一次大戦特需後の急減産に加えて、世界恐慌、昭和恐慌、不渡り倒産した時と、市場環境は似ている一方で、求められる楽器が異なる上、政吉に代る川口氏ら工長らも居ないこともあって、小野田社長さんは「やべぇッ」と感じていると分ります。そして、スズキバイオリンの今後を決めるのは、スズキバイオリンしかありません。
以上のことを明らかにした上で、誠に勝手で失敬ながら今後のスズキを勝手に論議することはできます。そこで、改めて板を立てて皆様のご意見を伺ってみたいと存じます。
さて、Woody 様 ありがとうございます。
私の[55083] 〉これを書いていて実はスズキは絶滅危惧種じゃないかなぁ、と思うようになりました。これからは存在意義がないんじゃぁないか
を裏付けたWoody 様のコメントで、裏を返すと今後への期待と20年前を懐かしむようにも思いました。私の本心では、川口氏ら工長らが居ても倒産??の勢いです。
今のスズキは、大正時代、第一次大戦特需後の急減産に加えて、世界恐慌、昭和恐慌、不渡り倒産した時と、市場環境は似ている一方で、求められる楽器が異なる上、政吉に代る川口氏ら工長らも居ないこともあって、小野田社長さんは「やべぇッ」と感じていると分ります。そして、スズキバイオリンの今後を決めるのは、スズキバイオリンしかありません。
以上のことを明らかにした上で、誠に勝手で失敬ながら今後のスズキを勝手に論議することはできます。そこで、改めて板を立てて皆様のご意見を伺ってみたいと存じます。
[55126]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月31日 14:37
投稿者:通りすがり(ID:IVlEZWA)
上のコメントが本当なら悲しいですし、それなら中国ブランドでいいよって自分は思います。
得られる収入のこととか考えたら、日本で製作するのは割に合わないんですかねぇ。
日本人のプロオケの人とかが日本人の職人さんと意見交換しながらオーダーするようなエコシステムが出来てこないと期待できなさそう。
アメリカは作家が育ったんだけどなぁ。
得られる収入のこととか考えたら、日本で製作するのは割に合わないんですかねぇ。
日本人のプロオケの人とかが日本人の職人さんと意見交換しながらオーダーするようなエコシステムが出来てこないと期待できなさそう。
アメリカは作家が育ったんだけどなぁ。
例えば、モラッシーやビソロッティのような誰も欲しがるブランド楽器は作れないし、楽器として10seriesと言っても中国製と同じかもしれないし、中級や初級の学習用楽器でも、高品質で低価格なメーカーが多く存在していてスズキなどの立場がないでしょう。そして、何もスズキだけでなく、ピグマリウスについても同じことが言えるのでは??と思います。
そこで、これからのスズキバイオリンやピグマリスは、どうあるのか??誠に勝手に想像してコメントして頂きたいです。気軽に楽しみながら、よろしくお願いいたします。
ヴァイオリン掲示板に戻る
11 / 13 ページ [ 123コメント ]
【ご参考】
[56287]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月29日 01:54
投稿者:松毬(ID:EBJSSSI)
[56283]
訂正 " No.12~No.21、No.23 " です
メダル情報ありがとうございます。 大正六年は1917年で、やっぱ緑綬褒章ですね。 確認して頂いて助かりました
「やっぱり裏切られた」に追い打ちをかけるようで、酷なようで申し訳ないのですが、このラベルは、素直にそのまま読めば良いものです。 期待が大きすぎたからか先入観からか鼻っからの誤解で、そのまま理解できるよう " FACTORY " と真ん中に大きく書かれているものです。 そもそも取り違えない様に工場生産品と伝えているものなのですよ
しかし、この楽器の造りは、それ迄とは異なりすこし特別です。 この楽器は、政吉作をコピーしたのが梅雄作で、この梅雄作に続いて政吉作をコピーしたスペックダウン品のようです。 この楽器の製作には、政吉が製作ラインに入って手を動かしたのではなく政吉が監修して職人が作った楽器だろうと思います(政吉監修楽器)。 似た様な監修楽器として、秩監修楽器があり、もともとの秩作#700は、'75年以降は秩の監修の下で職人製作楽器に替わります。 知らなければ製作者が変ったと分らない程同じです。
また、政吉のサインは、STANDARD21,23共に同じでラベルにプリントと分ります。 サインの位置付けは、戦後の特シーズの上位品に梅雄サインがある楽器と、やはり同じです(戦後の特シリーズも梅雄の監修楽器でしょうね)
特シリーズのSPECIALに対して普通のシリーズを指してSTADARDと示したでしょう。 従って、この楽器は海外向けで、ラベルは国内向けとは別に改めて1917年以降に新しく作られたラベルです。 1927年に特シリーズが廃止されて、US向けに残るSTANDARDシリーズの内、21、23 は、廃止された特3、特5の代わりを担い継続も改良もしたように見えます。 1941年時、梅雄作のNo.1(約¥200)、No.21(約¥150)を踏まえると、1927年時、梅雄作のNo.1(¥150)、特5(¥120)、特3(¥90)とあるのに対してSTADARD23は¥100ほどで特5の廉価版のように推定します。
私の手元の特2よりかなり良いもので、指板こそ黒檀ではありませんが板はそれなりに良いものを使っていると思います。 表板は1929年梅雄作No.1より劣るものの程よく冬目も通っています。 楓の杢も綺麗で裏板横板ネックと統一感があるのは梅雄作と同じように選ばれた材です。 ニスは色も綺麗なオイルニスで、なかなか乾かず剥がれたりケースの布地アトがついたりしますが、綺麗なまま乾いています
アーチはストラドではなくローハイアーチみたいな感じで少し高くありませんか?
板はちゃんと程よく削った(でも薄目かな?)もので、寸法は、表板357mm/裏板358mm、ネック長130mm/ストップ195mmに嵌ってバシッと出ているでしょう。 音は、マトモで良いのではないかなぁ?
240円の顎あては、値段からして戦後のものです。 んー、'50年代か'60年代初頭かなぁ?オイルニスはかなりずっと柔らかいままで癒着します。
また、弓は、'70年代ごろのものです。 材は割に良いもので虎杢のようなものもあります。
昭和初期からずっと昭和末ごろまで大切に使われた楽器のようで、その後お蔵入りしますが保管状態が良かったと思います。 間もなく良い100年もののアンティーク楽器ですよ
なお、この楽器により、ラインナップシリーズの変遷において、アウトラインが読める大きな価値もありましたよ
[56283]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月28日 00:01
投稿者:松毬(ID:NIlUKWA)
1917年の緑綬褒章とは異なる[56282]と書きましたが、画像ではメダルの紋様が切れているので間違ったかも。 趣味はバイオリン集め様がお持ちのSTANDARD23のラベルで、今一度確認願えないでしょうか??
なお、ご提示のSTANDARD21にある赤いトレードマークは、1941年からのNo.11~No.21、No.23に転用されたように見えます。
No.11~No.21、No.23はスズキ黎明期(1900年ごろ)No.1~7から延長したシリーズで、スズキの標準(STANDARD)と言えるではないかな? つまりSTANDARD21、23、もです
また、STANDARD21、23、シリーズは、1929年時点においてNo.1~13のシリーズ上位機種として、US向け生産されたが、1941年の太平洋戦争勃発に伴い同年国内向けに代えられてNo.11~No.21、No.23として生産されたのではないかな? それに、No.1~13の上のシリーズは戦前の特シリーズですが、当時は特シリーズが廃止はされており、特5や特6辺りに代りをUS向けではSTANDARD23が担っていたのではないかな?
とすると、STANDARD23は梅雄作のNo.1に次ぐ楽器で、当時は結構良い楽器ですね
あと、鎮一氏のピーターの真贋に係り、政吉の製作技術が高いほど、ジャーマンコピーであった可能性が高いでしょう。 ジャーマンコピーを、そのまま政吉がコピーしたから、ジャーマンスタイルで残る訳です。
逆に、政吉が下手糞なら、政吉の癖でジャーマンスタイルになっちゃった、ってことになります (本物をコピーしたつもりでも、ジャーマンコピーをコピーしていたにせよです)
なお、ご提示のSTANDARD21にある赤いトレードマークは、1941年からのNo.11~No.21、No.23に転用されたように見えます。
No.11~No.21、No.23はスズキ黎明期(1900年ごろ)No.1~7から延長したシリーズで、スズキの標準(STANDARD)と言えるではないかな? つまりSTANDARD21、23、もです
また、STANDARD21、23、シリーズは、1929年時点においてNo.1~13のシリーズ上位機種として、US向け生産されたが、1941年の太平洋戦争勃発に伴い同年国内向けに代えられてNo.11~No.21、No.23として生産されたのではないかな? それに、No.1~13の上のシリーズは戦前の特シリーズですが、当時は特シリーズが廃止はされており、特5や特6辺りに代りをUS向けではSTANDARD23が担っていたのではないかな?
とすると、STANDARD23は梅雄作のNo.1に次ぐ楽器で、当時は結構良い楽器ですね
あと、鎮一氏のピーターの真贋に係り、政吉の製作技術が高いほど、ジャーマンコピーであった可能性が高いでしょう。 ジャーマンコピーを、そのまま政吉がコピーしたから、ジャーマンスタイルで残る訳です。
逆に、政吉が下手糞なら、政吉の癖でジャーマンスタイルになっちゃった、ってことになります (本物をコピーしたつもりでも、ジャーマンコピーをコピーしていたにせよです)
メダル情報ありがとうございます。 大正六年は1917年で、やっぱ緑綬褒章ですね。 確認して頂いて助かりました
「やっぱり裏切られた」に追い打ちをかけるようで、酷なようで申し訳ないのですが、このラベルは、素直にそのまま読めば良いものです。 期待が大きすぎたからか先入観からか鼻っからの誤解で、そのまま理解できるよう " FACTORY " と真ん中に大きく書かれているものです。 そもそも取り違えない様に工場生産品と伝えているものなのですよ
しかし、この楽器の造りは、それ迄とは異なりすこし特別です。 この楽器は、政吉作をコピーしたのが梅雄作で、この梅雄作に続いて政吉作をコピーしたスペックダウン品のようです。 この楽器の製作には、政吉が製作ラインに入って手を動かしたのではなく政吉が監修して職人が作った楽器だろうと思います(政吉監修楽器)。 似た様な監修楽器として、秩監修楽器があり、もともとの秩作#700は、'75年以降は秩の監修の下で職人製作楽器に替わります。 知らなければ製作者が変ったと分らない程同じです。
また、政吉のサインは、STANDARD21,23共に同じでラベルにプリントと分ります。 サインの位置付けは、戦後の特シーズの上位品に梅雄サインがある楽器と、やはり同じです(戦後の特シリーズも梅雄の監修楽器でしょうね)
特シリーズのSPECIALに対して普通のシリーズを指してSTADARDと示したでしょう。 従って、この楽器は海外向けで、ラベルは国内向けとは別に改めて1917年以降に新しく作られたラベルです。 1927年に特シリーズが廃止されて、US向けに残るSTANDARDシリーズの内、21、23 は、廃止された特3、特5の代わりを担い継続も改良もしたように見えます。 1941年時、梅雄作のNo.1(約¥200)、No.21(約¥150)を踏まえると、1927年時、梅雄作のNo.1(¥150)、特5(¥120)、特3(¥90)とあるのに対してSTADARD23は¥100ほどで特5の廉価版のように推定します。
私の手元の特2よりかなり良いもので、指板こそ黒檀ではありませんが板はそれなりに良いものを使っていると思います。 表板は1929年梅雄作No.1より劣るものの程よく冬目も通っています。 楓の杢も綺麗で裏板横板ネックと統一感があるのは梅雄作と同じように選ばれた材です。 ニスは色も綺麗なオイルニスで、なかなか乾かず剥がれたりケースの布地アトがついたりしますが、綺麗なまま乾いています
アーチはストラドではなくローハイアーチみたいな感じで少し高くありませんか?
板はちゃんと程よく削った(でも薄目かな?)もので、寸法は、表板357mm/裏板358mm、ネック長130mm/ストップ195mmに嵌ってバシッと出ているでしょう。 音は、マトモで良いのではないかなぁ?
240円の顎あては、値段からして戦後のものです。 んー、'50年代か'60年代初頭かなぁ?オイルニスはかなりずっと柔らかいままで癒着します。
また、弓は、'70年代ごろのものです。 材は割に良いもので虎杢のようなものもあります。
昭和初期からずっと昭和末ごろまで大切に使われた楽器のようで、その後お蔵入りしますが保管状態が良かったと思います。 間もなく良い100年もののアンティーク楽器ですよ
なお、この楽器により、ラインナップシリーズの変遷において、アウトラインが読める大きな価値もありましたよ
[56288]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月29日 12:20
投稿者:趣味はバイオリン集め(ID:KERmNXA)
うらぎられたと言いつつ全然諦めていないと見破られてしまいましたね。
前回の投稿で納得はいかないながらしょうがないなと思ってました、しかし
今回頂いた投稿の考察をよんで幾つかの点において気になる事、矛盾しているのではと
思える事がありその点に関してお答え戴きたいのですが、話が長くなるので面倒くさかったら断って下さい、松毬さんに迷惑かけるつもりは全くないので。
前回の投稿で納得はいかないながらしょうがないなと思ってました、しかし
今回頂いた投稿の考察をよんで幾つかの点において気になる事、矛盾しているのではと
思える事がありその点に関してお答え戴きたいのですが、話が長くなるので面倒くさかったら断って下さい、松毬さんに迷惑かけるつもりは全くないので。
[56290]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月29日 20:03
投稿者:松毬(ID:F3c3gGg)
[56287]
の誤植”STADARD”訂正 ”STANDARD” です
構いませんので、「矛盾しているのでは」? どうぞお話下さいませ
[56287]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月29日 01:54
投稿者:松毬(ID:EBJSSSI)
[56283]訂正 " No.12~No.21、No.23 " です
メダル情報ありがとうございます。 大正六年は1917年で、やっぱ緑綬褒章ですね。 確認して頂いて助かりました
「やっぱり裏切られた」に追い打ちをかけるようで、酷なようで申し訳ないのですが、このラベルは、素直にそのまま読めば良いものです。 期待が大きすぎたからか先入観からか鼻っからの誤解で、そのまま理解できるよう " FACTORY " と真ん中に大きく書かれているものです。 そもそも取り違えない様に工場生産品と伝えているものなのですよ
しかし、この楽器の造りは、それ迄とは異なりすこし特別です。 この楽器は、政吉作をコピーしたのが梅雄作で、この梅雄作に続いて政吉作をコピーしたスペックダウン品のようです。 この楽器の製作には、政吉が製作ラインに入って手を動かしたのではなく政吉が監修して職人が作った楽器だろうと思います(政吉監修楽器)。 似た様な監修楽器として、秩監修楽器があり、もともとの秩作#700は、'75年以降は秩の監修の下で職人製作楽器に替わります。 知らなければ製作者が変ったと分らない程同じです。
また、政吉のサインは、STANDARD21,23共に同じでラベルにプリントと分ります。 サインの位置付けは、戦後の特シーズの上位品に梅雄サインがある楽器と、やはり同じです(戦後の特シリーズも梅雄の監修楽器でしょうね)
特シリーズのSPECIALに対して普通のシリーズを指してSTADARDと示したでしょう。 従って、この楽器は海外向けで、ラベルは国内向けとは別に改めて1917年以降に新しく作られたラベルです。 1927年に特シリーズが廃止されて、US向けに残るSTANDARDシリーズの内、21、23 は、廃止された特3、特5の代わりを担い継続も改良もしたように見えます。 1941年時、梅雄作のNo.1(約¥200)、No.21(約¥150)を踏まえると、1927年時、梅雄作のNo.1(¥150)、特5(¥120)、特3(¥90)とあるのに対してSTADARD23は¥100ほどで特5の廉価版のように推定します。
私の手元の特2よりかなり良いもので、指板こそ黒檀ではありませんが板はそれなりに良いものを使っていると思います。 表板は1929年梅雄作No.1より劣るものの程よく冬目も通っています。 楓の杢も綺麗で裏板横板ネックと統一感があるのは梅雄作と同じように選ばれた材です。 ニスは色も綺麗なオイルニスで、なかなか乾かず剥がれたりケースの布地アトがついたりしますが、綺麗なまま乾いています
アーチはストラドではなくローハイアーチみたいな感じで少し高くありませんか?
板はちゃんと程よく削った(でも薄目かな?)もので、寸法は、表板357mm/裏板358mm、ネック長130mm/ストップ195mmに嵌ってバシッと出ているでしょう。 音は、マトモで良いのではないかなぁ?
240円の顎あては、値段からして戦後のものです。 んー、'50年代か'60年代初頭かなぁ?オイルニスはかなりずっと柔らかいままで癒着します。
また、弓は、'70年代ごろのものです。 材は割に良いもので虎杢のようなものもあります。
昭和初期からずっと昭和末ごろまで大切に使われた楽器のようで、その後お蔵入りしますが保管状態が良かったと思います。 間もなく良い100年もののアンティーク楽器ですよ
なお、この楽器により、ラインナップシリーズの変遷において、アウトラインが読める大きな価値もありましたよ
メダル情報ありがとうございます。 大正六年は1917年で、やっぱ緑綬褒章ですね。 確認して頂いて助かりました
「やっぱり裏切られた」に追い打ちをかけるようで、酷なようで申し訳ないのですが、このラベルは、素直にそのまま読めば良いものです。 期待が大きすぎたからか先入観からか鼻っからの誤解で、そのまま理解できるよう " FACTORY " と真ん中に大きく書かれているものです。 そもそも取り違えない様に工場生産品と伝えているものなのですよ
しかし、この楽器の造りは、それ迄とは異なりすこし特別です。 この楽器は、政吉作をコピーしたのが梅雄作で、この梅雄作に続いて政吉作をコピーしたスペックダウン品のようです。 この楽器の製作には、政吉が製作ラインに入って手を動かしたのではなく政吉が監修して職人が作った楽器だろうと思います(政吉監修楽器)。 似た様な監修楽器として、秩監修楽器があり、もともとの秩作#700は、'75年以降は秩の監修の下で職人製作楽器に替わります。 知らなければ製作者が変ったと分らない程同じです。
また、政吉のサインは、STANDARD21,23共に同じでラベルにプリントと分ります。 サインの位置付けは、戦後の特シーズの上位品に梅雄サインがある楽器と、やはり同じです(戦後の特シリーズも梅雄の監修楽器でしょうね)
特シリーズのSPECIALに対して普通のシリーズを指してSTADARDと示したでしょう。 従って、この楽器は海外向けで、ラベルは国内向けとは別に改めて1917年以降に新しく作られたラベルです。 1927年に特シリーズが廃止されて、US向けに残るSTANDARDシリーズの内、21、23 は、廃止された特3、特5の代わりを担い継続も改良もしたように見えます。 1941年時、梅雄作のNo.1(約¥200)、No.21(約¥150)を踏まえると、1927年時、梅雄作のNo.1(¥150)、特5(¥120)、特3(¥90)とあるのに対してSTADARD23は¥100ほどで特5の廉価版のように推定します。
私の手元の特2よりかなり良いもので、指板こそ黒檀ではありませんが板はそれなりに良いものを使っていると思います。 表板は1929年梅雄作No.1より劣るものの程よく冬目も通っています。 楓の杢も綺麗で裏板横板ネックと統一感があるのは梅雄作と同じように選ばれた材です。 ニスは色も綺麗なオイルニスで、なかなか乾かず剥がれたりケースの布地アトがついたりしますが、綺麗なまま乾いています
アーチはストラドではなくローハイアーチみたいな感じで少し高くありませんか?
板はちゃんと程よく削った(でも薄目かな?)もので、寸法は、表板357mm/裏板358mm、ネック長130mm/ストップ195mmに嵌ってバシッと出ているでしょう。 音は、マトモで良いのではないかなぁ?
240円の顎あては、値段からして戦後のものです。 んー、'50年代か'60年代初頭かなぁ?オイルニスはかなりずっと柔らかいままで癒着します。
また、弓は、'70年代ごろのものです。 材は割に良いもので虎杢のようなものもあります。
昭和初期からずっと昭和末ごろまで大切に使われた楽器のようで、その後お蔵入りしますが保管状態が良かったと思います。 間もなく良い100年もののアンティーク楽器ですよ
なお、この楽器により、ラインナップシリーズの変遷において、アウトラインが読める大きな価値もありましたよ
構いませんので、「矛盾しているのでは」? どうぞお話下さいませ
[56291]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月29日 20:07
投稿者:松毬(ID:F3c3gGg)
「気になる事」も、どうぞお話下さいませ
[56292]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月30日 14:25
投稿者:趣味はバイオリン集め(ID:JFgGYlk)
ご返答有難うございます。幾つかあるので一つずつお聞きします。
まず気になったことなんですが、今回お見せしたバイオリンが海外またはUS向けであると判断した決定的な根拠は何ですか。
まず気になったことなんですが、今回お見せしたバイオリンが海外またはUS向けであると判断した決定的な根拠は何ですか。
[56294]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月30日 19:24
投稿者:松毬(ID:GJA4JTU)
ちょっと詰問的で、怖いなぁ。 優しくしてね
先ず、1929年STANDARD21、23は、スズキ公開ヒストリーにないこと。 この履歴は、海外向けの記述がないこは既知でした
スズキ公開ヒストリー
[55932]
[40588]
http://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls
特シリーズはSPECIALに対して、普通のシリーズにSTANDARD[56287]
と気が付けば、英訳された訳で、英語圏向けと分ります。 最大のマーケットがUSです
[55111]
に置いて、私の特2は(3).-1).、1929年STANDARD21、23 は、(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOの " KOJO "が英訳されて " FACTORY " となったもので同上です。
(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようで、つまり(3).-2).の直後に切り替わったか?平行Variationとして登場します。 これに合わせて、英訳" FACTORY "の登場でしょう
先ず、1929年STANDARD21、23は、スズキ公開ヒストリーにないこと。 この履歴は、海外向けの記述がないこは既知でした
スズキ公開ヒストリー
[55932]
[55932]
Re: 鈴木バイオリンの特製品ラベル表記について
投稿日時:2025年05月31日 22:34
投稿者:松毬(ID:Iid4NzQ)
大したことではございません。
[53472] への調査済みネタで、今回文章化したまでです。これは[55129] 又は[55427]で停まったままで、この後の戦後ネタの予告版にもなりました。また、私が知らないことも学べたので感謝いたします。
戦後の特製は、ざっくりと戦前の特製の復刻と言ってよく、起こりと消える様子も似ています。
戦前、政吉は、3グレードで商売を始め、#1~7の生産型式に増やします。これを後に#1~13販売型式に分けて商売し、この時更に特製を最上位に追加しました。商売の拡大により特製が登場します。
スズキ会社はWW Ⅰ 後に不況となり挽回に特製を廃止して、高級イタリアシリーズを謳って政吉と梅雄自作を売り出します。フラッグシップが変わり特製が消えます。
ただ戦後は、特製の消え方は、梅雄の復活、秩の売り出し、三桁シリーズへの統合と段々と影を薄くしています
朱角印の文字を「品髙」と考えると?もうちょっと近付きませんかね
あとは、本格的に画像解析するとか。
メロンパンさんは、特製の朱角印は幾つも目にされた環境です。これら朱角印を高精細画像に撮り、正規化して重ねると、文字画像は欠けることなく鮮明になります。AI画像検索すると文字が判然とするのでは?
なお、スズキ公開ヒストリー
[40588]
http://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls (今は、リンクが切れています。切れる前のダウンロードデータより先に記載)
済韻:電気バイブレーター➡️[47000] catgut氏
なお、[38498] リンクは[47001]と同じです。この取り直しリンクは https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100183511
他、先[55929]の開けないリンクは、catgut氏からのもので、重要な貴重なソースだったので残念です。(ダウンロードしておくべきでした)
[53472] への調査済みネタで、今回文章化したまでです。これは[55129] 又は[55427]で停まったままで、この後の戦後ネタの予告版にもなりました。また、私が知らないことも学べたので感謝いたします。
戦後の特製は、ざっくりと戦前の特製の復刻と言ってよく、起こりと消える様子も似ています。
戦前、政吉は、3グレードで商売を始め、#1~7の生産型式に増やします。これを後に#1~13販売型式に分けて商売し、この時更に特製を最上位に追加しました。商売の拡大により特製が登場します。
スズキ会社はWW Ⅰ 後に不況となり挽回に特製を廃止して、高級イタリアシリーズを謳って政吉と梅雄自作を売り出します。フラッグシップが変わり特製が消えます。
ただ戦後は、特製の消え方は、梅雄の復活、秩の売り出し、三桁シリーズへの統合と段々と影を薄くしています
朱角印の文字を「品髙」と考えると?もうちょっと近付きませんかね
あとは、本格的に画像解析するとか。
メロンパンさんは、特製の朱角印は幾つも目にされた環境です。これら朱角印を高精細画像に撮り、正規化して重ねると、文字画像は欠けることなく鮮明になります。AI画像検索すると文字が判然とするのでは?
なお、スズキ公開ヒストリー
[40588]
[40588]
Re: 鈴木政吉氏製作のバイオリンについて
投稿日時:2009年07月16日 21:44
投稿者:catgut(ID:F0ZHBnE)
鈴木バイオリンのサイトの情報ではNo.3は1907年-1927年までの間に7円から12円で販売されたものですね。
ttp://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls (Excel形式)
国会図書館の近代デジタルライブラリーに当時の鈴木バイオリンについて興味深い資料が登録されています。
ttp://kindai.ndl.go.jp/
から「主要工業概覧」で検索すると、大正10年の資料がヒットしますが、このうち「第4部 雑工業」に当時の日本の楽器産業の概況が掲載されています。この記述(農商務省工務局作成)によると、当時はドイツ製量産ヴァイオリンより米国市場では鈴木製のほうが高めだったようです。
「米国市場にて邦品(鈴木バイオリン)は独逸品よりも高価を称へ居るがごとき状態なり」
ttp://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls (Excel形式)
国会図書館の近代デジタルライブラリーに当時の鈴木バイオリンについて興味深い資料が登録されています。
ttp://kindai.ndl.go.jp/
から「主要工業概覧」で検索すると、大正10年の資料がヒットしますが、このうち「第4部 雑工業」に当時の日本の楽器産業の概況が掲載されています。この記述(農商務省工務局作成)によると、当時はドイツ製量産ヴァイオリンより米国市場では鈴木製のほうが高めだったようです。
「米国市場にて邦品(鈴木バイオリン)は独逸品よりも高価を称へ居るがごとき状態なり」
済韻:電気バイブレーター➡️[47000] catgut氏
なお、[38498] リンクは[47001]と同じです。この取り直しリンクは https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100183511
他、先[55929]の開けないリンクは、catgut氏からのもので、重要な貴重なソースだったので残念です。(ダウンロードしておくべきでした)
[40588]
Re: 鈴木政吉氏製作のバイオリンについて
投稿日時:2009年07月16日 21:44
投稿者:catgut(ID:F0ZHBnE)
鈴木バイオリンのサイトの情報ではNo.3は1907年-1927年までの間に7円から12円で販売されたものですね。
ttp://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls (Excel形式)
国会図書館の近代デジタルライブラリーに当時の鈴木バイオリンについて興味深い資料が登録されています。
ttp://kindai.ndl.go.jp/
から「主要工業概覧」で検索すると、大正10年の資料がヒットしますが、このうち「第4部 雑工業」に当時の日本の楽器産業の概況が掲載されています。この記述(農商務省工務局作成)によると、当時はドイツ製量産ヴァイオリンより米国市場では鈴木製のほうが高めだったようです。
「米国市場にて邦品(鈴木バイオリン)は独逸品よりも高価を称へ居るがごとき状態なり」
ttp://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls (Excel形式)
国会図書館の近代デジタルライブラリーに当時の鈴木バイオリンについて興味深い資料が登録されています。
ttp://kindai.ndl.go.jp/
から「主要工業概覧」で検索すると、大正10年の資料がヒットしますが、このうち「第4部 雑工業」に当時の日本の楽器産業の概況が掲載されています。この記述(農商務省工務局作成)によると、当時はドイツ製量産ヴァイオリンより米国市場では鈴木製のほうが高めだったようです。
「米国市場にて邦品(鈴木バイオリン)は独逸品よりも高価を称へ居るがごとき状態なり」
特シリーズはSPECIALに対して、普通のシリーズにSTANDARD[56287]
[56287]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月29日 01:54
投稿者:松毬(ID:EBJSSSI)
[56283]訂正 " No.12~No.21、No.23 " です
メダル情報ありがとうございます。 大正六年は1917年で、やっぱ緑綬褒章ですね。 確認して頂いて助かりました
「やっぱり裏切られた」に追い打ちをかけるようで、酷なようで申し訳ないのですが、このラベルは、素直にそのまま読めば良いものです。 期待が大きすぎたからか先入観からか鼻っからの誤解で、そのまま理解できるよう " FACTORY " と真ん中に大きく書かれているものです。 そもそも取り違えない様に工場生産品と伝えているものなのですよ
しかし、この楽器の造りは、それ迄とは異なりすこし特別です。 この楽器は、政吉作をコピーしたのが梅雄作で、この梅雄作に続いて政吉作をコピーしたスペックダウン品のようです。 この楽器の製作には、政吉が製作ラインに入って手を動かしたのではなく政吉が監修して職人が作った楽器だろうと思います(政吉監修楽器)。 似た様な監修楽器として、秩監修楽器があり、もともとの秩作#700は、'75年以降は秩の監修の下で職人製作楽器に替わります。 知らなければ製作者が変ったと分らない程同じです。
また、政吉のサインは、STANDARD21,23共に同じでラベルにプリントと分ります。 サインの位置付けは、戦後の特シーズの上位品に梅雄サインがある楽器と、やはり同じです(戦後の特シリーズも梅雄の監修楽器でしょうね)
特シリーズのSPECIALに対して普通のシリーズを指してSTADARDと示したでしょう。 従って、この楽器は海外向けで、ラベルは国内向けとは別に改めて1917年以降に新しく作られたラベルです。 1927年に特シリーズが廃止されて、US向けに残るSTANDARDシリーズの内、21、23 は、廃止された特3、特5の代わりを担い継続も改良もしたように見えます。 1941年時、梅雄作のNo.1(約¥200)、No.21(約¥150)を踏まえると、1927年時、梅雄作のNo.1(¥150)、特5(¥120)、特3(¥90)とあるのに対してSTADARD23は¥100ほどで特5の廉価版のように推定します。
私の手元の特2よりかなり良いもので、指板こそ黒檀ではありませんが板はそれなりに良いものを使っていると思います。 表板は1929年梅雄作No.1より劣るものの程よく冬目も通っています。 楓の杢も綺麗で裏板横板ネックと統一感があるのは梅雄作と同じように選ばれた材です。 ニスは色も綺麗なオイルニスで、なかなか乾かず剥がれたりケースの布地アトがついたりしますが、綺麗なまま乾いています
アーチはストラドではなくローハイアーチみたいな感じで少し高くありませんか?
板はちゃんと程よく削った(でも薄目かな?)もので、寸法は、表板357mm/裏板358mm、ネック長130mm/ストップ195mmに嵌ってバシッと出ているでしょう。 音は、マトモで良いのではないかなぁ?
240円の顎あては、値段からして戦後のものです。 んー、'50年代か'60年代初頭かなぁ?オイルニスはかなりずっと柔らかいままで癒着します。
また、弓は、'70年代ごろのものです。 材は割に良いもので虎杢のようなものもあります。
昭和初期からずっと昭和末ごろまで大切に使われた楽器のようで、その後お蔵入りしますが保管状態が良かったと思います。 間もなく良い100年もののアンティーク楽器ですよ
なお、この楽器により、ラインナップシリーズの変遷において、アウトラインが読める大きな価値もありましたよ
メダル情報ありがとうございます。 大正六年は1917年で、やっぱ緑綬褒章ですね。 確認して頂いて助かりました
「やっぱり裏切られた」に追い打ちをかけるようで、酷なようで申し訳ないのですが、このラベルは、素直にそのまま読めば良いものです。 期待が大きすぎたからか先入観からか鼻っからの誤解で、そのまま理解できるよう " FACTORY " と真ん中に大きく書かれているものです。 そもそも取り違えない様に工場生産品と伝えているものなのですよ
しかし、この楽器の造りは、それ迄とは異なりすこし特別です。 この楽器は、政吉作をコピーしたのが梅雄作で、この梅雄作に続いて政吉作をコピーしたスペックダウン品のようです。 この楽器の製作には、政吉が製作ラインに入って手を動かしたのではなく政吉が監修して職人が作った楽器だろうと思います(政吉監修楽器)。 似た様な監修楽器として、秩監修楽器があり、もともとの秩作#700は、'75年以降は秩の監修の下で職人製作楽器に替わります。 知らなければ製作者が変ったと分らない程同じです。
また、政吉のサインは、STANDARD21,23共に同じでラベルにプリントと分ります。 サインの位置付けは、戦後の特シーズの上位品に梅雄サインがある楽器と、やはり同じです(戦後の特シリーズも梅雄の監修楽器でしょうね)
特シリーズのSPECIALに対して普通のシリーズを指してSTADARDと示したでしょう。 従って、この楽器は海外向けで、ラベルは国内向けとは別に改めて1917年以降に新しく作られたラベルです。 1927年に特シリーズが廃止されて、US向けに残るSTANDARDシリーズの内、21、23 は、廃止された特3、特5の代わりを担い継続も改良もしたように見えます。 1941年時、梅雄作のNo.1(約¥200)、No.21(約¥150)を踏まえると、1927年時、梅雄作のNo.1(¥150)、特5(¥120)、特3(¥90)とあるのに対してSTADARD23は¥100ほどで特5の廉価版のように推定します。
私の手元の特2よりかなり良いもので、指板こそ黒檀ではありませんが板はそれなりに良いものを使っていると思います。 表板は1929年梅雄作No.1より劣るものの程よく冬目も通っています。 楓の杢も綺麗で裏板横板ネックと統一感があるのは梅雄作と同じように選ばれた材です。 ニスは色も綺麗なオイルニスで、なかなか乾かず剥がれたりケースの布地アトがついたりしますが、綺麗なまま乾いています
アーチはストラドではなくローハイアーチみたいな感じで少し高くありませんか?
板はちゃんと程よく削った(でも薄目かな?)もので、寸法は、表板357mm/裏板358mm、ネック長130mm/ストップ195mmに嵌ってバシッと出ているでしょう。 音は、マトモで良いのではないかなぁ?
240円の顎あては、値段からして戦後のものです。 んー、'50年代か'60年代初頭かなぁ?オイルニスはかなりずっと柔らかいままで癒着します。
また、弓は、'70年代ごろのものです。 材は割に良いもので虎杢のようなものもあります。
昭和初期からずっと昭和末ごろまで大切に使われた楽器のようで、その後お蔵入りしますが保管状態が良かったと思います。 間もなく良い100年もののアンティーク楽器ですよ
なお、この楽器により、ラインナップシリーズの変遷において、アウトラインが読める大きな価値もありましたよ
[55111]
[55111]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月27日 20:55
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
>[55104]
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようで、つまり(3).-2).の直後に切り替わったか?平行Variationとして登場します。 これに合わせて、英訳" FACTORY "の登場でしょう
[56296]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月31日 15:24
投稿者:趣味はバイオリン集め(ID:OAdpYhE)
確かに取り調べみたいな感じで、いい感じしないですよね。申し訳ありませんでした。
そのような意図はありません。ディベートのようなものとご理解下さい。ですのでこちらの意見にも遠慮なく反論して下さい。
頂いた返答にかんして、SPECIALに対してSTANDARDだから海外向けということは鈴木バイオリンにおいてラベルにSPECIALと記入してあるものは全て海外向けなのでしょうか。自分が見た幾つかのものは明らかに国内向けの商品でしたが。また FACTORY はKOJOからの派生と言われますが、他の鈴木バイオリンの過去のラインナップにおいてFACTORYの文字をみたことが有りません、もしFACTORYと言うことに決めたのなら他の製品のラベルに存在するのではと思うのですが。ちなみにFACTORYの意味には工場、だけでなく製作所、工房があります。
次の質問に行く前にオークションにラベルがちょっと変な特5が出ていました見て下さい。https://auctions.yahoo.co.jp/auction/c1205437503
64年製なのに911番これどいうい事ですかね。
次の質問です。
STANDARD23からNo.23へと移行したとお考えのようですが、No.23という商品はそもそも存在しているのですか、少なくとも自分の資料では21までで、22,23は確認出来ません。存在を示すなにか資料をお持ちですか。
そのような意図はありません。ディベートのようなものとご理解下さい。ですのでこちらの意見にも遠慮なく反論して下さい。
頂いた返答にかんして、SPECIALに対してSTANDARDだから海外向けということは鈴木バイオリンにおいてラベルにSPECIALと記入してあるものは全て海外向けなのでしょうか。自分が見た幾つかのものは明らかに国内向けの商品でしたが。また FACTORY はKOJOからの派生と言われますが、他の鈴木バイオリンの過去のラインナップにおいてFACTORYの文字をみたことが有りません、もしFACTORYと言うことに決めたのなら他の製品のラベルに存在するのではと思うのですが。ちなみにFACTORYの意味には工場、だけでなく製作所、工房があります。
次の質問に行く前にオークションにラベルがちょっと変な特5が出ていました見て下さい。https://auctions.yahoo.co.jp/auction/c1205437503
64年製なのに911番これどいうい事ですかね。
次の質問です。
STANDARD23からNo.23へと移行したとお考えのようですが、No.23という商品はそもそも存在しているのですか、少なくとも自分の資料では21までで、22,23は確認出来ません。存在を示すなにか資料をお持ちですか。
[56297]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月31日 15:40
投稿者:趣味はバイオリン集め(ID:OAdpYhE)
追加です。[55111]
でKOJOは1930年後と書かれています。
今回はSUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようでとの事ですが
何か資料で確認されたのですか。
[55111]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月27日 20:55
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
>[55104]
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
今回はSUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようでとの事ですが
何か資料で確認されたのですか。
[56298]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月31日 19:10
投稿者:松毬(ID:kVBpgFA)
駄目だしと批判を経て論が育っていくのですが、それにしても話し方があること、ご理解があることに感謝いたします
次のリンクから、特4のラベルをご覧ください
http://www.piyoyonet.com/piyoyo_gakki/used/masakichi_s4/index.html
NAGOYA JAPAN の記述があることから、1920以降のラベルです。 また、メダルのセンター位置にはトレードマークが来ており、[55111]
(3).-2).より少し古いものです。 スズキ公開ヒストリー[56294]
から、特4は1920~1923年の楽器で、この頃のラベルと分ります。 (なお、楽器本体が1890年ごろとあるが、ラベルと一致するかは不詳です)
”KOJO ”と使われるのは、この頃からです。
1930年は、株式会社化した年で社名が「スズキバイオリン製造株式会社」となり、以降はこの社名がラベルに記載されます。 [55111]
(5).-1).の1930年は、このことが表に出ているもので、また、ソースのHttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]
でコレクトされたラベルが1930年ものだったと思います
ポイントは、国内の”KOJO ”→ 海外へ”FACTORY ”と ”英訳された点”です。 そして普通のシリーズに対して、STANDARD と英訳が当てられたことを見抜くことです。
また、海外向けでは国内向けとラベルデザインが異なるものがあること既知でした
SPECIALと記入してあるものは全て海外向けと限定するものではありません。
特に、戦後の特シリーズは、国内向けでも SPECIAL の記述があります。 また、1964年の特5の911番は、個体識別(ID)番号でモデル番号ではありません。 このIDは製作証明書にも記載されます。 シリアルの様ですが、どの様な順で付けたかは不詳
No.23という商品は見たことがあり存在しています[56267]
。 スズキ公開ヒストリーには抜けがあり、私が初めて抜けに気が付いたのがこのNo.23です。 また、No.22は見たことありませんので、存在したかはNo.23があるならNo.22もあるのでは?となりますが不明です
No.23 および No.19 [56267]
のラベルは、SUZUKI VIOLIN Co.LTD.と ”Co.LTD ”が登場し、センターメダルの位置に上同様にトレードマークが来ます。 そしてトレードマークは、赤丸の上に書かれます。 この No.12~No.21、No.23 シリーズのラベルは、上の”KOJO ”及び STANDARD21 、23の ”FACTORY ”ラベルの後継の意匠です。
スズキ公開ヒストリーに記載しない1929年STANDARD21 、23 があり、1941年12月から記載されるNo.12~No.21があり、そして記載にないNo.23が存在することは、STANDARD21 、23 の後継に、No.21、No.23に来ると考えることは自然です。 逆に、もっと言えばSTANDARD 12~20 の存在の可能性を示すでしょう。 パールハーバーで有名な1941年12月は特別な月ですから、USのSTANDARDシリーズが国内に振り替えたと考えれば合点が通ります
次のリンクから、特4のラベルをご覧ください
http://www.piyoyonet.com/piyoyo_gakki/used/masakichi_s4/index.html
NAGOYA JAPAN の記述があることから、1920以降のラベルです。 また、メダルのセンター位置にはトレードマークが来ており、[55111]
[55111]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月27日 20:55
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
>[55104]
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]
では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]
[47023]
Re: 皇太子殿下のヴァイオリンは政吉自作
投稿日時:2013年07月24日 09:18
投稿者:catgut(ID:I3EwGWk)
戦前の鈴木のラベルについての考察が以下にありました。マンドリンが対象ですがヴァイオリンも準じているのではないかと思います。
ttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html
ttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
[56294]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月30日 19:24
投稿者:松毬(ID:GJA4JTU)
ちょっと詰問的で、怖いなぁ。 優しくしてね
先ず、1929年STANDARD21、23は、スズキ公開ヒストリーにないこと。 この履歴は、海外向けの記述がないこは既知でした
スズキ公開ヒストリー
[55932][40588] http://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls
特シリーズはSPECIALに対して、普通のシリーズにSTANDARD[56287]と気が付けば、英訳された訳で、英語圏向けと分ります。 最大のマーケットがUSです
[55111]に置いて、私の特2は(3).-1).、1929年STANDARD21、23 は、(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOの " KOJO "が英訳されて " FACTORY " となったもので同上です。
(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようで、つまり(3).-2).の直後に切り替わったか?平行Variationとして登場します。 これに合わせて、英訳" FACTORY "の登場でしょう
先ず、1929年STANDARD21、23は、スズキ公開ヒストリーにないこと。 この履歴は、海外向けの記述がないこは既知でした
スズキ公開ヒストリー
[55932][40588] http://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls
特シリーズはSPECIALに対して、普通のシリーズにSTANDARD[56287]と気が付けば、英訳された訳で、英語圏向けと分ります。 最大のマーケットがUSです
[55111]に置いて、私の特2は(3).-1).、1929年STANDARD21、23 は、(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOの " KOJO "が英訳されて " FACTORY " となったもので同上です。
(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようで、つまり(3).-2).の直後に切り替わったか?平行Variationとして登場します。 これに合わせて、英訳" FACTORY "の登場でしょう
”KOJO ”と使われるのは、この頃からです。
1930年は、株式会社化した年で社名が「スズキバイオリン製造株式会社」となり、以降はこの社名がラベルに記載されます。 [55111]
[55111]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月27日 20:55
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
>[55104]
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]
では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]
[47023]
Re: 皇太子殿下のヴァイオリンは政吉自作
投稿日時:2013年07月24日 09:18
投稿者:catgut(ID:I3EwGWk)
戦前の鈴木のラベルについての考察が以下にありました。マンドリンが対象ですがヴァイオリンも準じているのではないかと思います。
ttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html
ttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
[47023]
Re: 皇太子殿下のヴァイオリンは政吉自作
投稿日時:2013年07月24日 09:18
投稿者:catgut(ID:I3EwGWk)
戦前の鈴木のラベルについての考察が以下にありました。マンドリンが対象ですがヴァイオリンも準じているのではないかと思います。
ttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html
ttp://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html
ポイントは、国内の”KOJO ”→ 海外へ”FACTORY ”と ”英訳された点”です。 そして普通のシリーズに対して、STANDARD と英訳が当てられたことを見抜くことです。
また、海外向けでは国内向けとラベルデザインが異なるものがあること既知でした
SPECIALと記入してあるものは全て海外向けと限定するものではありません。
特に、戦後の特シリーズは、国内向けでも SPECIAL の記述があります。 また、1964年の特5の911番は、個体識別(ID)番号でモデル番号ではありません。 このIDは製作証明書にも記載されます。 シリアルの様ですが、どの様な順で付けたかは不詳
No.23という商品は見たことがあり存在しています[56267]
[56267]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月24日 16:55
投稿者:松毬(ID:WUIUAWA)
アハハハぁ、ひな壇5段かざりができますよ。
スズキの機種は多岐にわたり一人で集めて完全制覇はできないでしょう。 トレーディングできるといいですね。 No.36は珍しいし、No.103には戦前と戦後があり、その何れかですかね。 戦前のNo.19はいわく付きで私は保存しており、また、No.23は知っていますが、Standard23とは初めてです。
6コインの302は、政吉が初めてバイオリン商売ができたころの政吉工房の楽器じゃぁないかなぁ。 ちょっと興味が沸きます
鈴木鎮一氏がゲットしたのはガルネリ・ピーターと云う話で、政吉氏がコピーしているのでしょう。 →https://violino45.exblog.jp/iv/detail/?s=26125199&i=201711%2F10%2F61%2Fd0047461_21001993.jpg
これ少しアーチを下げたローハイアーチと思います。 eX.安藤幸のハズで6月3日のお披露目会に出た楽器じゃないかな? この直後の同年楽器が伝説となったアインシュタインが弾いた楽器と思います。 この製作に多分に梅雄も関わったと思われ、翌'27年からの梅雄ブランドの販売では、更にアーチを下げたストラドアーチで始まる様です。 このパーフリングから展開されたものを見てるのではないかなぁ?
もしも、eX.安藤幸、売りに出たら買いますぅ??
ただ、この頃から鎮一氏はニスの悪さを指摘しているのだけど、鎮一氏自身がゲットした楽器はピーターのジャーマンコピーじゃあ?って勘繰りたくなるほどだよねぇ
スズキの機種は多岐にわたり一人で集めて完全制覇はできないでしょう。 トレーディングできるといいですね。 No.36は珍しいし、No.103には戦前と戦後があり、その何れかですかね。 戦前のNo.19はいわく付きで私は保存しており、また、No.23は知っていますが、Standard23とは初めてです。
6コインの302は、政吉が初めてバイオリン商売ができたころの政吉工房の楽器じゃぁないかなぁ。 ちょっと興味が沸きます
鈴木鎮一氏がゲットしたのはガルネリ・ピーターと云う話で、政吉氏がコピーしているのでしょう。 →https://violino45.exblog.jp/iv/detail/?s=26125199&i=201711%2F10%2F61%2Fd0047461_21001993.jpg
これ少しアーチを下げたローハイアーチと思います。 eX.安藤幸のハズで6月3日のお披露目会に出た楽器じゃないかな? この直後の同年楽器が伝説となったアインシュタインが弾いた楽器と思います。 この製作に多分に梅雄も関わったと思われ、翌'27年からの梅雄ブランドの販売では、更にアーチを下げたストラドアーチで始まる様です。 このパーフリングから展開されたものを見てるのではないかなぁ?
もしも、eX.安藤幸、売りに出たら買いますぅ??
ただ、この頃から鎮一氏はニスの悪さを指摘しているのだけど、鎮一氏自身がゲットした楽器はピーターのジャーマンコピーじゃあ?って勘繰りたくなるほどだよねぇ
No.23 および No.19 [56267]
[56267]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月24日 16:55
投稿者:松毬(ID:WUIUAWA)
アハハハぁ、ひな壇5段かざりができますよ。
スズキの機種は多岐にわたり一人で集めて完全制覇はできないでしょう。 トレーディングできるといいですね。 No.36は珍しいし、No.103には戦前と戦後があり、その何れかですかね。 戦前のNo.19はいわく付きで私は保存しており、また、No.23は知っていますが、Standard23とは初めてです。
6コインの302は、政吉が初めてバイオリン商売ができたころの政吉工房の楽器じゃぁないかなぁ。 ちょっと興味が沸きます
鈴木鎮一氏がゲットしたのはガルネリ・ピーターと云う話で、政吉氏がコピーしているのでしょう。 →https://violino45.exblog.jp/iv/detail/?s=26125199&i=201711%2F10%2F61%2Fd0047461_21001993.jpg
これ少しアーチを下げたローハイアーチと思います。 eX.安藤幸のハズで6月3日のお披露目会に出た楽器じゃないかな? この直後の同年楽器が伝説となったアインシュタインが弾いた楽器と思います。 この製作に多分に梅雄も関わったと思われ、翌'27年からの梅雄ブランドの販売では、更にアーチを下げたストラドアーチで始まる様です。 このパーフリングから展開されたものを見てるのではないかなぁ?
もしも、eX.安藤幸、売りに出たら買いますぅ??
ただ、この頃から鎮一氏はニスの悪さを指摘しているのだけど、鎮一氏自身がゲットした楽器はピーターのジャーマンコピーじゃあ?って勘繰りたくなるほどだよねぇ
スズキの機種は多岐にわたり一人で集めて完全制覇はできないでしょう。 トレーディングできるといいですね。 No.36は珍しいし、No.103には戦前と戦後があり、その何れかですかね。 戦前のNo.19はいわく付きで私は保存しており、また、No.23は知っていますが、Standard23とは初めてです。
6コインの302は、政吉が初めてバイオリン商売ができたころの政吉工房の楽器じゃぁないかなぁ。 ちょっと興味が沸きます
鈴木鎮一氏がゲットしたのはガルネリ・ピーターと云う話で、政吉氏がコピーしているのでしょう。 →https://violino45.exblog.jp/iv/detail/?s=26125199&i=201711%2F10%2F61%2Fd0047461_21001993.jpg
これ少しアーチを下げたローハイアーチと思います。 eX.安藤幸のハズで6月3日のお披露目会に出た楽器じゃないかな? この直後の同年楽器が伝説となったアインシュタインが弾いた楽器と思います。 この製作に多分に梅雄も関わったと思われ、翌'27年からの梅雄ブランドの販売では、更にアーチを下げたストラドアーチで始まる様です。 このパーフリングから展開されたものを見てるのではないかなぁ?
もしも、eX.安藤幸、売りに出たら買いますぅ??
ただ、この頃から鎮一氏はニスの悪さを指摘しているのだけど、鎮一氏自身がゲットした楽器はピーターのジャーマンコピーじゃあ?って勘繰りたくなるほどだよねぇ
スズキ公開ヒストリーに記載しない1929年STANDARD21 、23 があり、1941年12月から記載されるNo.12~No.21があり、そして記載にないNo.23が存在することは、STANDARD21 、23 の後継に、No.21、No.23に来ると考えることは自然です。 逆に、もっと言えばSTANDARD 12~20 の存在の可能性を示すでしょう。 パールハーバーで有名な1941年12月は特別な月ですから、USのSTANDARDシリーズが国内に振り替えたと考えれば合点が通ります
[56299]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年11月01日 04:00
投稿者:松毬(ID:kVBpgFA)
誤植訂正:
1).スズキ公開ヒストリー[56294]
に照らすと、特4は~1923年までの楽器ですから1920~1923年ごろのラベルと分ります。
この頃には、”KOJO ”と使われていた訳です (もしかすると、もっと早いかも知れません)
2).他にも助詞の誤植をまだ残すものの、訂正が煩雑になるのでご容赦下さい。 お詫び申し上げます
なお、戦前のラベルはM.SUZUKI系[55111]
から徐々に離れ、SUZUKI VIOLIN系 3系列あるのでしょう
SUZUKI VIOLIN KOJO
SUZUKI VIOLIN FACTORY
SUZUKI VIOLIN Co.LTD.
1).スズキ公開ヒストリー[56294]
[56294]
Re: 誠に勝手に話すスズキバイオリン等の今後
投稿日時:2025年10月30日 19:24
投稿者:松毬(ID:GJA4JTU)
ちょっと詰問的で、怖いなぁ。 優しくしてね
先ず、1929年STANDARD21、23は、スズキ公開ヒストリーにないこと。 この履歴は、海外向けの記述がないこは既知でした
スズキ公開ヒストリー
[55932][40588] http://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls
特シリーズはSPECIALに対して、普通のシリーズにSTANDARD[56287]と気が付けば、英訳された訳で、英語圏向けと分ります。 最大のマーケットがUSです
[55111]
に置いて、私の特2は(3).-1).、1929年STANDARD21、23 は、(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOの " KOJO "が英訳されて " FACTORY " となったもので同上です。
(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようで、つまり(3).-2).の直後に切り替わったか?平行Variationとして登場します。 これに合わせて、英訳" FACTORY "の登場でしょう
先ず、1929年STANDARD21、23は、スズキ公開ヒストリーにないこと。 この履歴は、海外向けの記述がないこは既知でした
スズキ公開ヒストリー
[55932][40588] http://www.suzukiviolin.co.jp/data.xls
特シリーズはSPECIALに対して、普通のシリーズにSTANDARD[56287]と気が付けば、英訳された訳で、英語圏向けと分ります。 最大のマーケットがUSです
[55111]
[55111]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月27日 20:55
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
>[55104]
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
(5).-1).SUZUKI VIOLIN KOJOは、実は1920年ごろから使われたようで、つまり(3).-2).の直後に切り替わったか?平行Variationとして登場します。 これに合わせて、英訳" FACTORY "の登場でしょう
この頃には、”KOJO ”と使われていた訳です (もしかすると、もっと早いかも知れません)
2).他にも助詞の誤植をまだ残すものの、訂正が煩雑になるのでご容赦下さい。 お詫び申し上げます
なお、戦前のラベルはM.SUZUKI系[55111]
[55111]
Re: スズキの高級バイオリン 1000番台について教えて下さい。
投稿日時:2024年05月27日 20:55
投稿者:松毬(ID:VpKIRzA)
>[55104]
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
>なお、1915年前後ごろのラベル、(16メダル)
>https://oshiete.chunichi.co.jp/pro/372/column/1283/index.img/column1_l.jpg
→ 注) 楽器No.35は、1920年以降のもの
☞ Http://www5.plala.or.jp/mandolin-cafe/20-masakichi.html [47023]では、
ハッキリと分かる日英博(1910(明43))の名誉大賞メダルが写されている。
[MASAKICHI SUZUKI]と書かれたラベルは数が多く、不詳も含め11種以上ある。
(1).1888年後、共益商社に納めた3機種のラベルは不明 ・・・・1種以上
(2).コロンブス大博のメダルがセンターのもの・・・・・・・・・3種以上
-1).1897年前後の[ 3メダル M.SUZUKI NIHON ]2種
a): 生産の型式、A3010など
b): 販売の品番、No.6 など、表されたもの
-2).1910年前後の[14メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
(11メダルなど、その他、Variation不詳 )
(3).日英博の大賞メダルがセンターのもの ・・・・・・・・・・・2種以上
-1).1915年前後の[16メダル MASAKICHI.SUZUKI. NIPPON ]
-2).1920年の後の[ 同上に JAPAN ]
(その他、Variation不詳 )
(※.上記の様に常にセンターは重要なメダルが置かれている。
特製は、No.1~13と同ラベルに、No.特1など表記。
米国独立記念万博(1926)の金賞メダル以降その他不詳。)
(4).1926(昭 1)年後、[ Masakichi Suzuki ]のもの・・・・・・・・4種
-1).1926年のプロモーション・展示楽器に用いたもの
-2).上の販売(1927年以降)に用いたラベル3種
(5).1930(昭 5)年後、鈴木バイオリン製造株式会社のもの ・・・・1種以上
-1).[ SUZUKI VIOLIN KOJO 筆記体Masakichi Suzuki ]
(その他、Variation不詳 )
(6).1933(昭8)年後[ SUZUKI MASAKICHI SAIINSHO ]のもの・・1種以上
((7).その他・・・ ? 種、不詳)
SUZUKI VIOLIN KOJO
SUZUKI VIOLIN FACTORY
SUZUKI VIOLIN Co.LTD.
ヴァイオリン掲示板に戻る
11 / 13 ページ [ 123コメント ]