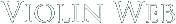不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[55785]
バイオリンと物理について
投稿日時:2025年03月19日 07:30
投稿者:ロイヤルジャック(ID:dghVh5A)
有識者の方に聞いてみたいので質問立てをさせていただきました。
バイオリン製作者の中で、音響工学等の物理理論を全面的に押し出してくる方が著名とされてる職人にも何名かいらっしゃいます。
そういう方々の論文みたいなブログやホームページは読み物としては面白いのですが、その根拠を基に作られたであろう本人の作品や、その店で購入やガチの調整をした楽器は、??と感じる事の方が多いです。
ある知り合いは、そういう理論を展開されてる職人から安いとは言えない金額の楽器を購入しましたが、論文結果のような効果は分からず、知人も仲間内も音の鋭い耳障りな楽器という結論にしか至らず、結局は短期間で手放しておりました。
物理を根拠に説得力ある説明をされる職人さんが販売した楽器でしたので、私も少なからずショックを受けたのを覚えてます。
例えば国内外の複数の職人が、物理学でいうところの音が優れた楽器は弾いてると良さが分からないが、聴衆の側に回ると音が遠くまで飛び、レスポンスがよくダイナミクスに優れる。んで、自分は物理研究をしてそういう楽器を作ってる。
等と書いていますが、どうなのでしょうね。
近鳴り、遠鳴りは間違いなくあるとは思いますし、その説明通りの性能の楽器なら新作価格で良いものが買えるのですから多くの人が使いたがるでしょう。
そういった職人が良いとか悪いとか、そういう事を論じたいわけではなく(私は、自身の研究結果を惜しみなく公開してくださる姿勢は尊敬に値するとも思ってます)、バイオリン製作と音響について、エビデンスが確立されてる技術というのはどういうものがあるのでしょうか?
めちゃめちゃ単純に砕いてしまうと、こう作ればどういう音になる、というものがあるのかという事です。
近鳴り、遠鳴りにしても、近くでも音が大きく、遠くでも音が大きいもの、上記にあげたようなもの、いろんなパターンがあるかと思います。
楽器の構造で、そういう事象が説明出来るようなエビデンスがあれば興味があります。
有識者の方、教えてください。
バイオリン製作者の中で、音響工学等の物理理論を全面的に押し出してくる方が著名とされてる職人にも何名かいらっしゃいます。
そういう方々の論文みたいなブログやホームページは読み物としては面白いのですが、その根拠を基に作られたであろう本人の作品や、その店で購入やガチの調整をした楽器は、??と感じる事の方が多いです。
ある知り合いは、そういう理論を展開されてる職人から安いとは言えない金額の楽器を購入しましたが、論文結果のような効果は分からず、知人も仲間内も音の鋭い耳障りな楽器という結論にしか至らず、結局は短期間で手放しておりました。
物理を根拠に説得力ある説明をされる職人さんが販売した楽器でしたので、私も少なからずショックを受けたのを覚えてます。
例えば国内外の複数の職人が、物理学でいうところの音が優れた楽器は弾いてると良さが分からないが、聴衆の側に回ると音が遠くまで飛び、レスポンスがよくダイナミクスに優れる。んで、自分は物理研究をしてそういう楽器を作ってる。
等と書いていますが、どうなのでしょうね。
近鳴り、遠鳴りは間違いなくあるとは思いますし、その説明通りの性能の楽器なら新作価格で良いものが買えるのですから多くの人が使いたがるでしょう。
そういった職人が良いとか悪いとか、そういう事を論じたいわけではなく(私は、自身の研究結果を惜しみなく公開してくださる姿勢は尊敬に値するとも思ってます)、バイオリン製作と音響について、エビデンスが確立されてる技術というのはどういうものがあるのでしょうか?
めちゃめちゃ単純に砕いてしまうと、こう作ればどういう音になる、というものがあるのかという事です。
近鳴り、遠鳴りにしても、近くでも音が大きく、遠くでも音が大きいもの、上記にあげたようなもの、いろんなパターンがあるかと思います。
楽器の構造で、そういう事象が説明出来るようなエビデンスがあれば興味があります。
有識者の方、教えてください。
ヴァイオリン掲示板に戻る
[ 4コメント ]
[55786]
Re: バイオリンと物理について
投稿日時:2025年03月21日 20:49
投稿者:QB(ID:EJOSJXM)
ロイヤルジャック氏、
はじめまして。
私もあれやこれやWebで蘊蓄垂れている御仁のところで調整してもらった楽器が、ブリッジの直下に魂柱立ててあるのを見て、びっくりした記憶があります。イワシの頭だったのでしょうか。
実用的な研究と、その成果に基づく楽器が非常に高い評価を得ている例はあります。
直接的に遠なりのエビデンスではないかもしれませんが、物理的な構造と発振される音について、昔から結構ガチで研究していて信奉者も多いのは、現代においてはZyg一択なのではないかと思います。基本的に私も記事はWorkshopの内容など、目は通すようにしています。
ハンディにまとまっているものとしては;https://strad3d.org/articles.html ご参考にどうぞ。
はじめまして。
私もあれやこれやWebで蘊蓄垂れている御仁のところで調整してもらった楽器が、ブリッジの直下に魂柱立ててあるのを見て、びっくりした記憶があります。イワシの頭だったのでしょうか。
実用的な研究と、その成果に基づく楽器が非常に高い評価を得ている例はあります。
直接的に遠なりのエビデンスではないかもしれませんが、物理的な構造と発振される音について、昔から結構ガチで研究していて信奉者も多いのは、現代においてはZyg一択なのではないかと思います。基本的に私も記事はWorkshopの内容など、目は通すようにしています。
ハンディにまとまっているものとしては;https://strad3d.org/articles.html ご参考にどうぞ。
[55791]
Re: バイオリンと物理について
投稿日時:2025年03月31日 10:04
投稿者:通りすがり(ID:NVJxc5I)
ただの素人が世の中の情報を眺めていて感じた事を書きます。
○ストラドやガルネリを目指す、超えると標榜していてもオリジナル通りの寸法、アーチ、板厚で作れる職人が少なく、研究の出発地点が既に目標から遠い状態にある。
○物理/工学者は楽器制作の経験に乏しく、且つかなり単純化したモデルで音の良し悪しを図ろうとするのでこれまた目指すところから遠い。(バスバーがあるならハイバーも必要だろうとかいう乱暴な人が昔いました。。)
○楽器制作はマーケットが小さいので研究資金に恵まれないし、知見もたまらない。
○そもそも音の良し悪しは個人の好みによるので判断が難しい。
○ストラドやガルネリを目指す、超えると標榜していてもオリジナル通りの寸法、アーチ、板厚で作れる職人が少なく、研究の出発地点が既に目標から遠い状態にある。
○物理/工学者は楽器制作の経験に乏しく、且つかなり単純化したモデルで音の良し悪しを図ろうとするのでこれまた目指すところから遠い。(バスバーがあるならハイバーも必要だろうとかいう乱暴な人が昔いました。。)
○楽器制作はマーケットが小さいので研究資金に恵まれないし、知見もたまらない。
○そもそも音の良し悪しは個人の好みによるので判断が難しい。
[55800]
Re: バイオリンと物理について
投稿日時:2025年04月06日 02:21
投稿者:松毬(ID:VwJ1UlA)
〉聴衆の側に回ると音が遠くまで飛び、レスポンスがよくダイナミクスに優れる。んで、自分は物理研究をしてそういう楽器を作ってる。
〉等と書いていますが、どうなのでしょうね。
書いてあるから取り敢えず本当で、嘘は書いてはないでしょう。しかし、これをどの様に理解するか?の問題のように思います。
恐らく、この作者の実験ではこの通りでも、他の者では再現しないことは頻繁にあることではないか、と思います。中でも環境やホール、調整、奏者、聴者が変わって、全く評価が変わるのではないか?と思いますが、、、
〉エビデンスが確立されてる技術というのはどういうものがある ?
検証されたエビデンスって、あんまないんじゃぁないかなぁ、、、次らは、十分に検証はされてないが頑張って公表した方で、此れからまだまだって感じではないでしょうか。とは言え参考になると思います。[55786]
https://strad3d.org/articles.html
そもそも科学技術会などによる論文の査読とF.B.する機能も殆どない界隈で、検証方法が未熟だったりと遅れています。
また、今後発表されるネタは、まだ何も未公開でしょうし、製作者は得た知見で論文作成より楽器作成を優先するでしょうから、ネタも隠れ勝ちと思います
現実は、見たい人がネタを探し、また、公開ネタを見る人側が、妥当性を勘案しながらネタを使うことが専らでしょう
バイオリンらは、音響工学だけでは視野が足らず音響学の視点から考えます。音響学では、哲学的や心理学的、生物学的な視点が加わります。音大も共同研究を進めています。中でも知覚認知と脳の情報処理は新しい分野で、音の評価に関わり良い音の秘密が解かれつつあります
物理的な音、つまり振動としては、科学技術的にはバイオリンはそう難しいものでは無くなりつつあると思います。しかし、検証されたエビデンス化は極端に遅れていると思います。お金も研究者も極端に少なく、産業ベースにのらず国の補助も殆どないためで、[55791]
と同じです。
AIとは、全く正反対な状況といえば、理解が早いのでは、と思います
〉等と書いていますが、どうなのでしょうね。
書いてあるから取り敢えず本当で、嘘は書いてはないでしょう。しかし、これをどの様に理解するか?の問題のように思います。
恐らく、この作者の実験ではこの通りでも、他の者では再現しないことは頻繁にあることではないか、と思います。中でも環境やホール、調整、奏者、聴者が変わって、全く評価が変わるのではないか?と思いますが、、、
〉エビデンスが確立されてる技術というのはどういうものがある ?
検証されたエビデンスって、あんまないんじゃぁないかなぁ、、、次らは、十分に検証はされてないが頑張って公表した方で、此れからまだまだって感じではないでしょうか。とは言え参考になると思います。[55786]
[55786]
Re: バイオリンと物理について
投稿日時:2025年03月21日 20:49
投稿者:QB(ID:EJOSJXM)
ロイヤルジャック氏、
はじめまして。
私もあれやこれやWebで蘊蓄垂れている御仁のところで調整してもらった楽器が、ブリッジの直下に魂柱立ててあるのを見て、びっくりした記憶があります。イワシの頭だったのでしょうか。
実用的な研究と、その成果に基づく楽器が非常に高い評価を得ている例はあります。
直接的に遠なりのエビデンスではないかもしれませんが、物理的な構造と発振される音について、昔から結構ガチで研究していて信奉者も多いのは、現代においてはZyg一択なのではないかと思います。基本的に私も記事はWorkshopの内容など、目は通すようにしています。
ハンディにまとまっているものとしては;https://strad3d.org/articles.html ご参考にどうぞ。
はじめまして。
私もあれやこれやWebで蘊蓄垂れている御仁のところで調整してもらった楽器が、ブリッジの直下に魂柱立ててあるのを見て、びっくりした記憶があります。イワシの頭だったのでしょうか。
実用的な研究と、その成果に基づく楽器が非常に高い評価を得ている例はあります。
直接的に遠なりのエビデンスではないかもしれませんが、物理的な構造と発振される音について、昔から結構ガチで研究していて信奉者も多いのは、現代においてはZyg一択なのではないかと思います。基本的に私も記事はWorkshopの内容など、目は通すようにしています。
ハンディにまとまっているものとしては;https://strad3d.org/articles.html ご参考にどうぞ。
そもそも科学技術会などによる論文の査読とF.B.する機能も殆どない界隈で、検証方法が未熟だったりと遅れています。
また、今後発表されるネタは、まだ何も未公開でしょうし、製作者は得た知見で論文作成より楽器作成を優先するでしょうから、ネタも隠れ勝ちと思います
現実は、見たい人がネタを探し、また、公開ネタを見る人側が、妥当性を勘案しながらネタを使うことが専らでしょう
バイオリンらは、音響工学だけでは視野が足らず音響学の視点から考えます。音響学では、哲学的や心理学的、生物学的な視点が加わります。音大も共同研究を進めています。中でも知覚認知と脳の情報処理は新しい分野で、音の評価に関わり良い音の秘密が解かれつつあります
物理的な音、つまり振動としては、科学技術的にはバイオリンはそう難しいものでは無くなりつつあると思います。しかし、検証されたエビデンス化は極端に遅れていると思います。お金も研究者も極端に少なく、産業ベースにのらず国の補助も殆どないためで、[55791]
[55791]
Re: バイオリンと物理について
投稿日時:2025年03月31日 10:04
投稿者:通りすがり(ID:NVJxc5I)
ただの素人が世の中の情報を眺めていて感じた事を書きます。
○ストラドやガルネリを目指す、超えると標榜していてもオリジナル通りの寸法、アーチ、板厚で作れる職人が少なく、研究の出発地点が既に目標から遠い状態にある。
○物理/工学者は楽器制作の経験に乏しく、且つかなり単純化したモデルで音の良し悪しを図ろうとするのでこれまた目指すところから遠い。(バスバーがあるならハイバーも必要だろうとかいう乱暴な人が昔いました。。)
○楽器制作はマーケットが小さいので研究資金に恵まれないし、知見もたまらない。
○そもそも音の良し悪しは個人の好みによるので判断が難しい。
○ストラドやガルネリを目指す、超えると標榜していてもオリジナル通りの寸法、アーチ、板厚で作れる職人が少なく、研究の出発地点が既に目標から遠い状態にある。
○物理/工学者は楽器制作の経験に乏しく、且つかなり単純化したモデルで音の良し悪しを図ろうとするのでこれまた目指すところから遠い。(バスバーがあるならハイバーも必要だろうとかいう乱暴な人が昔いました。。)
○楽器制作はマーケットが小さいので研究資金に恵まれないし、知見もたまらない。
○そもそも音の良し悪しは個人の好みによるので判断が難しい。
AIとは、全く正反対な状況といえば、理解が早いのでは、と思います
[55815]
Re: バイオリンと物理について
投稿日時:2025年04月20日 22:22
投稿者:成金(ID:QmVGBHE)
そうですねー、ある意味法学者と裁判官等といった学者と実務家で導きだす結論が違うようなレベルの話だと思いますよ。
理論家が数値や機械ベースのデータで何かを結論付けただけで済むなら、もはや今後の開発の必要がないくらいに理論だけは完璧に説明出来るものはいくらでもありますね。
料理だって、栄養だけに目を向ければとんでもないレベルで成分を抽出出来る機械はもう出来てるわけですね。
でも、それだけじゃ駄目なわけですよね? 食事するからには味わいを求めるわけでしょう? その味わいがバイオリンでいうところの音に相当するわけです。
物理をあてはめた楽器で、理論と実体で差が出にくいのなんて、せいぜい物理的な加工の狂いにくさ程度のものでしょう。
調べればいくらでも出てきますが、紙の空箱でバイオリンを再現しようが、平らにバイオリンを作ろうが、バイオリンの音は出るものです。
なので、作者毎の音の違いなんかも科学で説明出来るものでもないと思いますし、崇められてるストラディバリウスと同じ年代に作られた楽器をレッテル隠してダーッと並べて試弾きすればストラドやガルネリが優位立つなんて事もないと思います。
あのー、一人の母親から複数人の子供が生まれたとしてその子達の声に共通点なんてあると思います?
20歳前後の人間1000人集めたら、9割共通点のない若者の声がしてごく一部声楽家としてやってけるような声の持ち主や5、60代で通用する声の持ち主等の例外がいるでしょう。
還暦迎える年の人間1000人集めてもまた同じような事です。
私が知るバイオリンで物理的に間違いないといえる点は、アーチを高くした方が木材の強度が上がる、というものくらいです。(アーチが全くない楽器が存在しないのは、強度が保てないからです)
少なくとも私は、音の共通性や指向性を確立するような事をしたいのであれば、バイオリンの世界だけで完結するような話ではないと考えてますよ。
理論家が数値や機械ベースのデータで何かを結論付けただけで済むなら、もはや今後の開発の必要がないくらいに理論だけは完璧に説明出来るものはいくらでもありますね。
料理だって、栄養だけに目を向ければとんでもないレベルで成分を抽出出来る機械はもう出来てるわけですね。
でも、それだけじゃ駄目なわけですよね? 食事するからには味わいを求めるわけでしょう? その味わいがバイオリンでいうところの音に相当するわけです。
物理をあてはめた楽器で、理論と実体で差が出にくいのなんて、せいぜい物理的な加工の狂いにくさ程度のものでしょう。
調べればいくらでも出てきますが、紙の空箱でバイオリンを再現しようが、平らにバイオリンを作ろうが、バイオリンの音は出るものです。
なので、作者毎の音の違いなんかも科学で説明出来るものでもないと思いますし、崇められてるストラディバリウスと同じ年代に作られた楽器をレッテル隠してダーッと並べて試弾きすればストラドやガルネリが優位立つなんて事もないと思います。
あのー、一人の母親から複数人の子供が生まれたとしてその子達の声に共通点なんてあると思います?
20歳前後の人間1000人集めたら、9割共通点のない若者の声がしてごく一部声楽家としてやってけるような声の持ち主や5、60代で通用する声の持ち主等の例外がいるでしょう。
還暦迎える年の人間1000人集めてもまた同じような事です。
私が知るバイオリンで物理的に間違いないといえる点は、アーチを高くした方が木材の強度が上がる、というものくらいです。(アーチが全くない楽器が存在しないのは、強度が保てないからです)
少なくとも私は、音の共通性や指向性を確立するような事をしたいのであれば、バイオリンの世界だけで完結するような話ではないと考えてますよ。
ヴァイオリン掲示板に戻る
[ 4コメント ]