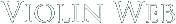不適切な書き込みがあった場合は「管理人に通知」ボタンからお知らせください
[56005]
小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月09日 21:59
投稿者:詩野(ID:IWciiDU)
表題の通りなのですが、卓上型ではない小型音叉での調弦はどのようにやるのでしょうか?
昔からピアノや卓上音叉を叩いて、ラの音を合わせるやり方をやってるのですが、平成初期とかの昔はそんなものは日本では出回っておらず、皆小型音叉で調弦をしていたと聞きます。
素朴な疑問ですが、百歩譲って肩当てつけてあれば顎で楽器を締め付ける事で、左手で音叉を叩いて、右手で弓を動かす動きが出来なくもないと思います。
が、昔は肩当てなしが主流だったようですし、肩当の種類もほとんどなかったと聞きます。
どうやって、左手で音叉を叩いて右手で弓を動かす動きをやっていたのでしょうか?
三本目の手を生やす以外のやり方があるようでしたら、叩いた音叉を耳の近くで聞くのが調弦はやりやすいと思うのです。
経験ある方いらっしゃいましたら教えてください。
昔からピアノや卓上音叉を叩いて、ラの音を合わせるやり方をやってるのですが、平成初期とかの昔はそんなものは日本では出回っておらず、皆小型音叉で調弦をしていたと聞きます。
素朴な疑問ですが、百歩譲って肩当てつけてあれば顎で楽器を締め付ける事で、左手で音叉を叩いて、右手で弓を動かす動きが出来なくもないと思います。
が、昔は肩当てなしが主流だったようですし、肩当の種類もほとんどなかったと聞きます。
どうやって、左手で音叉を叩いて右手で弓を動かす動きをやっていたのでしょうか?
三本目の手を生やす以外のやり方があるようでしたら、叩いた音叉を耳の近くで聞くのが調弦はやりやすいと思うのです。
経験ある方いらっしゃいましたら教えてください。
ヴァイオリン掲示板に戻る
1 / 2 ページ [ 12コメント ]
【ご参考】
[56007]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月11日 01:33
投稿者:rio(ID:GBclBCU)
私は、音叉でA(442)の音を聞き
その音を覚えて、調弦をします。
周囲がうるさい時は、音叉の柄の部分を歯で嚙み
音を取ります
昭和の時代は、松脂と一緒に音叉またはピッチパイプを
バヨリンケースに入れていた人は
そこそこいたと思います。
その音を覚えて、調弦をします。
周囲がうるさい時は、音叉の柄の部分を歯で嚙み
音を取ります
昭和の時代は、松脂と一緒に音叉またはピッチパイプを
バヨリンケースに入れていた人は
そこそこいたと思います。
[56008]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月11日 11:40
投稿者:詩野(ID:NWcnkJM)
rioさん、お久しぶりです!
そして回答いただきありがとうございます。
私の名前みてお心辺りありますでしょうか? 世田谷の某工房に行く時は、毎回お会い出来たらいいなーなんて思いながら早数年(以上?)です。
本題ですが、なるほど音を重ねてうねりで調弦をするのではなく、初めから音を覚えてしまうわけですね。
そうしたら、手が3本なんて変な発想はしなくても良さそうですね。
根本的な事ですが、その発想が頭から抜けておりました。
最後になりますが、風の噂でいろいろ耳にする事がありお身体くれぐれも大切になさってくださいね。
久しぶりにお名前拝見できて嬉しかったです!
そして回答いただきありがとうございます。
私の名前みてお心辺りありますでしょうか? 世田谷の某工房に行く時は、毎回お会い出来たらいいなーなんて思いながら早数年(以上?)です。
本題ですが、なるほど音を重ねてうねりで調弦をするのではなく、初めから音を覚えてしまうわけですね。
そうしたら、手が3本なんて変な発想はしなくても良さそうですね。
根本的な事ですが、その発想が頭から抜けておりました。
最後になりますが、風の噂でいろいろ耳にする事がありお身体くれぐれも大切になさってくださいね。
久しぶりにお名前拝見できて嬉しかったです!
[56009]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月12日 07:33
投稿者:pochi(ID:MkNJZiU)
詩野氏、はじめまして、こんばんは。
通常の調弦はピアノにAとDFAを貰って行います。
音叉では、膝て叩いて机等で共鳴させ、音程を(短期的に)覚えて調弦します。
ヴァイオリンの胴は都合の良い共鳴体なので胴に押し当てた音を覚えて調弦するのも一般的です。
駒に押し当ててピッタリなら共鳴したA線の振動が見えます。弓で弾かなくても調弦出来ますが、この方法だと何故か低めになる傾向が有ります。特に弦が古いと低くなる傾向が強くなります。
基準のAだけですから少々違っていても、完全五度調弦が狂っていなければ何の問題もありません。
音は耳で聴く物理現象であって、目で見ていても上手くはなりません。
但し、チューナーを使って開放弦の全弓運弓を行うのは、少しでも失敗すると針がブレるので、運弓の良し悪しを可視化出来る便利な道具になっています。針が真ん中に来る必要はありません。
通常の調弦はピアノにAとDFAを貰って行います。
音叉では、膝て叩いて机等で共鳴させ、音程を(短期的に)覚えて調弦します。
ヴァイオリンの胴は都合の良い共鳴体なので胴に押し当てた音を覚えて調弦するのも一般的です。
駒に押し当ててピッタリなら共鳴したA線の振動が見えます。弓で弾かなくても調弦出来ますが、この方法だと何故か低めになる傾向が有ります。特に弦が古いと低くなる傾向が強くなります。
基準のAだけですから少々違っていても、完全五度調弦が狂っていなければ何の問題もありません。
音は耳で聴く物理現象であって、目で見ていても上手くはなりません。
但し、チューナーを使って開放弦の全弓運弓を行うのは、少しでも失敗すると針がブレるので、運弓の良し悪しを可視化出来る便利な道具になっています。針が真ん中に来る必要はありません。
[56010]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月14日 07:25
投稿者:rio(ID:OJNoeSM)
(思い出したこと)
そういえば、ギターの調弦は
A(440)の音叉で、5弦5フレットのハーモニクスで基音をとり
ハーモニクスで残りの5弦を一旦合わせた後
もう一度、A(440)の音叉で、5弦5フレットのハーモニクスで基音をとり
再度残りの5弦を合わせていました。
その時は、「うねり云々」ということをよく聞きましたが
バヨリンのレッスンで調弦をする際に、
私は「うねり云々」という話は 聞いた覚えがありません。
バヨリンを習っていたとき(幼稚園のとき)
ソルフェージュの時間があり
ハミング(口を閉じて「んー」と鼻に音を当てるように発声する方法)で
Aの音だと思う音を出した後、音叉で調整して
覚えるようにしていました。
また、その時は2本音叉を所有し
A(440)とA(442)をそれぞれ 「ん~~」と
音を取る練習をしており
「これで、音がとれるようになりなさい」と言われていました
そのように教わったので、
音叉を楽器にあてるとか
うねりとかの考えは生まれませんでした。
ちなみに、音叉2本使いについては
先生から、
「バヨリンのレッスンは442、園や学校では440
と使い分けます」という説明で、私も深く考えず
そんなもんだと思っていました。
そういえば、ギターの調弦は
A(440)の音叉で、5弦5フレットのハーモニクスで基音をとり
ハーモニクスで残りの5弦を一旦合わせた後
もう一度、A(440)の音叉で、5弦5フレットのハーモニクスで基音をとり
再度残りの5弦を合わせていました。
その時は、「うねり云々」ということをよく聞きましたが
バヨリンのレッスンで調弦をする際に、
私は「うねり云々」という話は 聞いた覚えがありません。
バヨリンを習っていたとき(幼稚園のとき)
ソルフェージュの時間があり
ハミング(口を閉じて「んー」と鼻に音を当てるように発声する方法)で
Aの音だと思う音を出した後、音叉で調整して
覚えるようにしていました。
また、その時は2本音叉を所有し
A(440)とA(442)をそれぞれ 「ん~~」と
音を取る練習をしており
「これで、音がとれるようになりなさい」と言われていました
そのように教わったので、
音叉を楽器にあてるとか
うねりとかの考えは生まれませんでした。
ちなみに、音叉2本使いについては
先生から、
「バヨリンのレッスンは442、園や学校では440
と使い分けます」という説明で、私も深く考えず
そんなもんだと思っていました。
[56011]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月14日 19:22
投稿者:詩野(ID:JWJDgQ)
pochi先生
稚拙な質問にお答えいただき、恐縮でございます!
rioさんもおっしゃるように、音叉の音(?)と重ねるのではなく、短期的に覚えるのですね。
凄く恥ずかしいのですが、音叉を叩いて楽器にあてるとそこそこ大きい音が出る事を初めて知りました(笑)
この年になって新しい発見があるのは楽しいですね!
稚拙な質問にお答えいただき、恐縮でございます!
rioさんもおっしゃるように、音叉の音(?)と重ねるのではなく、短期的に覚えるのですね。
凄く恥ずかしいのですが、音叉を叩いて楽器にあてるとそこそこ大きい音が出る事を初めて知りました(笑)
この年になって新しい発見があるのは楽しいですね!
[56012]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月14日 19:49
投稿者:詩野(ID:JWJDgQ)
rioさん
またまた詳しくありがとうございます!
少なくとも私の周りだと音大生やプロといった上級者程、絶対音感がない事を自覚して唸りを聞き取って調弦をされていますね。
最近は音叉アプリを使われる方も増えてきた気がします。
ピアノだったら、rioさん流のはソルフェージュで絶対音感と言われるような音当て能力を身に付ける事は出来ると思うんですけど、バイオリンでそんないい加減な調弦(失礼!)をやったらオケやアンサンブルで嫌われてしまいそうですが、どうなのでしょう?
完全五度はある意味正確に「これ!」って正解が導き出せますので、興味が尽きません!
またまた詳しくありがとうございます!
少なくとも私の周りだと音大生やプロといった上級者程、絶対音感がない事を自覚して唸りを聞き取って調弦をされていますね。
最近は音叉アプリを使われる方も増えてきた気がします。
ピアノだったら、rioさん流のはソルフェージュで絶対音感と言われるような音当て能力を身に付ける事は出来ると思うんですけど、バイオリンでそんないい加減な調弦(失礼!)をやったらオケやアンサンブルで嫌われてしまいそうですが、どうなのでしょう?
完全五度はある意味正確に「これ!」って正解が導き出せますので、興味が尽きません!
[56014]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月15日 03:05
投稿者:松毬(ID:eRdxMBA)
詩野さん 初めまして
あるある誤解なく、あやうい所は明白にして残しておきます。小難しくなる点ご容赦下さい
小型音叉(金属)単体は、あまり空気を振動させず殆んど音として聞こえません。そのままでは耳の鼓膜を通さず、音叉を噛んで骨伝導を使って耳の蝸牛に振動を伝えます。両手フリーなので、普通に調弦へです。楽器の振動はあご当てなどからも骨に伝わり、共鳴するとあご骨から共鳴した音が聞こえます
一方 [56007]
[56009]
通り、耳の鼓膜を通す場合は、スピーカー(板や箱など共鳴体)により空気振動を増幅して普通に聞こえるレベルにして使います(卓上型はスピーカー付きなので、んなこと気にしません)。
バイオリンに音叉をくっつけると音叉の音がします。これはネックに付けるでも良く、ネックから箱に伝わり箱であるスピーカーが鳴ります(例えば、この振動に人の話し声を使うと、バイオリンからその話し声が拡声しますよ)。Aが合っていれば、弦も共振します。これは二台のバイオリン間でも起きることで、1台を弾くと、もう一台の弦が共振します
また、物理的に耳の機能は振動は感じ取りますが、耳自体で音程の理解をしている訳ではありません。音の理解は耳からの神経信号により脳で行われます。脳で振動ではなく概念的な音として理解され、その記憶が行われます。短期記憶で覚えた音と合わせるのが[56007]
[56009]
の話です。これら一連を丸めて音は耳で聞くと俗に言います。(最近は耳を使わず音が聞こえることは○秘ではなく公に知られます)
音の記憶は、脳の神経回路の繋がりパターンによる音の記録で、幼少より人によって様々な記録、記述の形態があります。その脳の成長により絶対音感と言っても、そのレベル、精度など色々あります。
一方、特に最近は、Aに440Hzを使わず442Hzでもないことがしばしばです。444Hz越えくらいまで結構使われるようで、で、私ですら既に442Hzをあまり使いません。コンマスが442Hzを使った場合、それに強いて合わせるくらい。そこで、例えば、精度が高く絶対音感でA442Hzベースで記録(記憶)が出来ている方なら、A444Hzのアンサンブルでは、えぇっ!てな違和感は消えないままでしょう
Aに音叉を使う場合、その音叉の周波数と精度、気温湿度を確認しておかなければなりません。そもそも音叉が440Hz(又は442Hz)ピッタリではないことはよくあり1centくらいは平気で変わります。さらに、昭和のピッチパイプ(G,D,A,E)なんて、とりあえず五度ってなもんで滅茶苦茶、今更役立たずです。でもこれでも「完全五度」のピッチパイプと言えます
「完全五度」とは音階のインターバル、音5つ分の音程五度なら、「何でも完全五度」と言います。これは裏返すと完全五度の音とは無数にあることを意味します。ピアノの五度(700cent)も純正五度(702cent)も、これに似た五度も、全て完全五度と言います。正確な表現でもあり、片や、非常にあいまいなことも表しています。完全五度ピッタリに調弦しますって、どれぇー!って。例えば、思いは「純正五度」ピッタリのことを言いたいのでは?としても、、
純正5度には、純正5度固有の唸りがあり、この唸りを基準に唸りの変化を調整するのが一般的に言われます。これよりも純正5度のハーモニクスの他、音全体(音スペクトル)で、この音この音って記憶の音と合わせる方も居ます(でも絶対音感とは異なる)。
調弦では必ずしも「純正五度」ピッタリにしないこともあり、しかし、それで「完全五度」ピッタリに調弦したと都合よく言えちゃいます。そこに色んなアンサンブルがあり、そのノウハウ?や考え方が色々あって調弦五度のインターバルは色々。そして、それはあまり外には公にならないようで、体験して実践的に学ぶしかないような感じです
また、「完全五度」ピッタリと言えても周りとずれた五度の場合は非常によくあり、ずれて居ても気が付かないアンサンブルでは何事もありません。気付かれると指摘に上がり健全に話し合いますよ。その際は、実力が上の方に合わせることもあれば、合わせられない方により添って(平均律などに)合わせることもあります
因みに、嫌いな方とは、そもそも音が合いませんので、一緒に弾きません
あるある誤解なく、あやうい所は明白にして残しておきます。小難しくなる点ご容赦下さい
小型音叉(金属)単体は、あまり空気を振動させず殆んど音として聞こえません。そのままでは耳の鼓膜を通さず、音叉を噛んで骨伝導を使って耳の蝸牛に振動を伝えます。両手フリーなので、普通に調弦へです。楽器の振動はあご当てなどからも骨に伝わり、共鳴するとあご骨から共鳴した音が聞こえます
一方 [56007]
[56007]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月11日 01:33
投稿者:rio(ID:GBclBCU)
私は、音叉でA(442)の音を聞き
その音を覚えて、調弦をします。
周囲がうるさい時は、音叉の柄の部分を歯で嚙み
音を取ります
昭和の時代は、松脂と一緒に音叉またはピッチパイプを
バヨリンケースに入れていた人は
そこそこいたと思います。
その音を覚えて、調弦をします。
周囲がうるさい時は、音叉の柄の部分を歯で嚙み
音を取ります
昭和の時代は、松脂と一緒に音叉またはピッチパイプを
バヨリンケースに入れていた人は
そこそこいたと思います。
[56009]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月12日 07:33
投稿者:pochi(ID:MkNJZiU)
詩野氏、はじめまして、こんばんは。
通常の調弦はピアノにAとDFAを貰って行います。
音叉では、膝て叩いて机等で共鳴させ、音程を(短期的に)覚えて調弦します。
ヴァイオリンの胴は都合の良い共鳴体なので胴に押し当てた音を覚えて調弦するのも一般的です。
駒に押し当ててピッタリなら共鳴したA線の振動が見えます。弓で弾かなくても調弦出来ますが、この方法だと何故か低めになる傾向が有ります。特に弦が古いと低くなる傾向が強くなります。
基準のAだけですから少々違っていても、完全五度調弦が狂っていなければ何の問題もありません。
音は耳で聴く物理現象であって、目で見ていても上手くはなりません。
但し、チューナーを使って開放弦の全弓運弓を行うのは、少しでも失敗すると針がブレるので、運弓の良し悪しを可視化出来る便利な道具になっています。針が真ん中に来る必要はありません。
通常の調弦はピアノにAとDFAを貰って行います。
音叉では、膝て叩いて机等で共鳴させ、音程を(短期的に)覚えて調弦します。
ヴァイオリンの胴は都合の良い共鳴体なので胴に押し当てた音を覚えて調弦するのも一般的です。
駒に押し当ててピッタリなら共鳴したA線の振動が見えます。弓で弾かなくても調弦出来ますが、この方法だと何故か低めになる傾向が有ります。特に弦が古いと低くなる傾向が強くなります。
基準のAだけですから少々違っていても、完全五度調弦が狂っていなければ何の問題もありません。
音は耳で聴く物理現象であって、目で見ていても上手くはなりません。
但し、チューナーを使って開放弦の全弓運弓を行うのは、少しでも失敗すると針がブレるので、運弓の良し悪しを可視化出来る便利な道具になっています。針が真ん中に来る必要はありません。
バイオリンに音叉をくっつけると音叉の音がします。これはネックに付けるでも良く、ネックから箱に伝わり箱であるスピーカーが鳴ります(例えば、この振動に人の話し声を使うと、バイオリンからその話し声が拡声しますよ)。Aが合っていれば、弦も共振します。これは二台のバイオリン間でも起きることで、1台を弾くと、もう一台の弦が共振します
また、物理的に耳の機能は振動は感じ取りますが、耳自体で音程の理解をしている訳ではありません。音の理解は耳からの神経信号により脳で行われます。脳で振動ではなく概念的な音として理解され、その記憶が行われます。短期記憶で覚えた音と合わせるのが[56007]
[56007]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月11日 01:33
投稿者:rio(ID:GBclBCU)
私は、音叉でA(442)の音を聞き
その音を覚えて、調弦をします。
周囲がうるさい時は、音叉の柄の部分を歯で嚙み
音を取ります
昭和の時代は、松脂と一緒に音叉またはピッチパイプを
バヨリンケースに入れていた人は
そこそこいたと思います。
その音を覚えて、調弦をします。
周囲がうるさい時は、音叉の柄の部分を歯で嚙み
音を取ります
昭和の時代は、松脂と一緒に音叉またはピッチパイプを
バヨリンケースに入れていた人は
そこそこいたと思います。
[56009]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月12日 07:33
投稿者:pochi(ID:MkNJZiU)
詩野氏、はじめまして、こんばんは。
通常の調弦はピアノにAとDFAを貰って行います。
音叉では、膝て叩いて机等で共鳴させ、音程を(短期的に)覚えて調弦します。
ヴァイオリンの胴は都合の良い共鳴体なので胴に押し当てた音を覚えて調弦するのも一般的です。
駒に押し当ててピッタリなら共鳴したA線の振動が見えます。弓で弾かなくても調弦出来ますが、この方法だと何故か低めになる傾向が有ります。特に弦が古いと低くなる傾向が強くなります。
基準のAだけですから少々違っていても、完全五度調弦が狂っていなければ何の問題もありません。
音は耳で聴く物理現象であって、目で見ていても上手くはなりません。
但し、チューナーを使って開放弦の全弓運弓を行うのは、少しでも失敗すると針がブレるので、運弓の良し悪しを可視化出来る便利な道具になっています。針が真ん中に来る必要はありません。
通常の調弦はピアノにAとDFAを貰って行います。
音叉では、膝て叩いて机等で共鳴させ、音程を(短期的に)覚えて調弦します。
ヴァイオリンの胴は都合の良い共鳴体なので胴に押し当てた音を覚えて調弦するのも一般的です。
駒に押し当ててピッタリなら共鳴したA線の振動が見えます。弓で弾かなくても調弦出来ますが、この方法だと何故か低めになる傾向が有ります。特に弦が古いと低くなる傾向が強くなります。
基準のAだけですから少々違っていても、完全五度調弦が狂っていなければ何の問題もありません。
音は耳で聴く物理現象であって、目で見ていても上手くはなりません。
但し、チューナーを使って開放弦の全弓運弓を行うのは、少しでも失敗すると針がブレるので、運弓の良し悪しを可視化出来る便利な道具になっています。針が真ん中に来る必要はありません。
音の記憶は、脳の神経回路の繋がりパターンによる音の記録で、幼少より人によって様々な記録、記述の形態があります。その脳の成長により絶対音感と言っても、そのレベル、精度など色々あります。
一方、特に最近は、Aに440Hzを使わず442Hzでもないことがしばしばです。444Hz越えくらいまで結構使われるようで、で、私ですら既に442Hzをあまり使いません。コンマスが442Hzを使った場合、それに強いて合わせるくらい。そこで、例えば、精度が高く絶対音感でA442Hzベースで記録(記憶)が出来ている方なら、A444Hzのアンサンブルでは、えぇっ!てな違和感は消えないままでしょう
Aに音叉を使う場合、その音叉の周波数と精度、気温湿度を確認しておかなければなりません。そもそも音叉が440Hz(又は442Hz)ピッタリではないことはよくあり1centくらいは平気で変わります。さらに、昭和のピッチパイプ(G,D,A,E)なんて、とりあえず五度ってなもんで滅茶苦茶、今更役立たずです。でもこれでも「完全五度」のピッチパイプと言えます
「完全五度」とは音階のインターバル、音5つ分の音程五度なら、「何でも完全五度」と言います。これは裏返すと完全五度の音とは無数にあることを意味します。ピアノの五度(700cent)も純正五度(702cent)も、これに似た五度も、全て完全五度と言います。正確な表現でもあり、片や、非常にあいまいなことも表しています。完全五度ピッタリに調弦しますって、どれぇー!って。例えば、思いは「純正五度」ピッタリのことを言いたいのでは?としても、、
純正5度には、純正5度固有の唸りがあり、この唸りを基準に唸りの変化を調整するのが一般的に言われます。これよりも純正5度のハーモニクスの他、音全体(音スペクトル)で、この音この音って記憶の音と合わせる方も居ます(でも絶対音感とは異なる)。
調弦では必ずしも「純正五度」ピッタリにしないこともあり、しかし、それで「完全五度」ピッタリに調弦したと都合よく言えちゃいます。そこに色んなアンサンブルがあり、そのノウハウ?や考え方が色々あって調弦五度のインターバルは色々。そして、それはあまり外には公にならないようで、体験して実践的に学ぶしかないような感じです
また、「完全五度」ピッタリと言えても周りとずれた五度の場合は非常によくあり、ずれて居ても気が付かないアンサンブルでは何事もありません。気付かれると指摘に上がり健全に話し合いますよ。その際は、実力が上の方に合わせることもあれば、合わせられない方により添って(平均律などに)合わせることもあります
因みに、嫌いな方とは、そもそも音が合いませんので、一緒に弾きません
[56015]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月15日 07:10
投稿者:詩野(ID:UDE4iJA)
松毬さん
度々勉強になる回答拝見してますよ!
私の質問に対しても大変詳しくありがとうございます!
私は言うまでもなく、万年初心者に毛が生えたレベルですので、他の方の回答に書いた嫌われるというのはそこまでの高度な話ではなく、相対音感のない人といった意味になります。
テンポがいい加減な人の方が更に嫌われるように思われますけどね!
度々勉強になる回答拝見してますよ!
私の質問に対しても大変詳しくありがとうございます!
私は言うまでもなく、万年初心者に毛が生えたレベルですので、他の方の回答に書いた嫌われるというのはそこまでの高度な話ではなく、相対音感のない人といった意味になります。
テンポがいい加減な人の方が更に嫌われるように思われますけどね!
[56016]
Re: 小型音叉の使い方について
投稿日時:2025年07月15日 17:20
投稿者:rio(ID:JWkIQQQ)
詩野さま
私の場合は、詩野さまとは、まったく逆で
私の周りだとプロ(職業演奏家)や音大生のばよりん弾きが
楽器のA線の音が音叉とぴったり合うように(唸りが出ないように)
音合わせをする姿を見たことがありません。
私自身、アマオケの経験は2年足らずしかありませんが
現場の音合わせは、コンマス・コンミスの出す音に合わせてました。
また、ピッチの傾向は松毬さまがコメントしておられるように
(意識的に下げている場合を除き)
442よりもやや高めになっていることが多いと感じてました。
ただ、高い精度の絶対音感をお持ちで、
A442Hzベースで記録(記憶)が出来ている方が
A444~5Hzのアンサンブルに参加しても
「へー、このぐらいのピッチでやるんだ」という
感想だけで、違和感を持ったり
否定的な感じにはならないと思います。
私も、いろいろコメントしておりますが
音の感じ取り方に自信はなく
調弦のために
A線D線、D線G線、A線E線 という2弦を
開放弦で弾いた時の音については
私は先生に「合ってます?」「高い?」「低い?」と訊いて正答を求め、
「2つの絃が同時に鳴る音が こう聞こえたら合っている」
というのを、今も時々確認しています。
フォークギターやエレキギターをする人達が
チューナーを用いたり
5弦5フレットの場所のハーモニクス音とA440 の音叉で
基音を合わせてから、ハーモニクスで6弦全てを調弦することは
書きましたが、開放弦があっているだけで
大なり小なり、フレット音痴は発生しますので、
高い精度の音程の正確さを求めているわけではないと思っています。
(というか無理があるように思います)
音叉の唸りにこだわりすぎるよりも
音律や 調性のニュアンス を
感じ取れた方が、楽曲のアナリーゼが楽しいのでは?
等とおもってます。
私の場合は、詩野さまとは、まったく逆で
私の周りだとプロ(職業演奏家)や音大生のばよりん弾きが
楽器のA線の音が音叉とぴったり合うように(唸りが出ないように)
音合わせをする姿を見たことがありません。
私自身、アマオケの経験は2年足らずしかありませんが
現場の音合わせは、コンマス・コンミスの出す音に合わせてました。
また、ピッチの傾向は松毬さまがコメントしておられるように
(意識的に下げている場合を除き)
442よりもやや高めになっていることが多いと感じてました。
ただ、高い精度の絶対音感をお持ちで、
A442Hzベースで記録(記憶)が出来ている方が
A444~5Hzのアンサンブルに参加しても
「へー、このぐらいのピッチでやるんだ」という
感想だけで、違和感を持ったり
否定的な感じにはならないと思います。
私も、いろいろコメントしておりますが
音の感じ取り方に自信はなく
調弦のために
A線D線、D線G線、A線E線 という2弦を
開放弦で弾いた時の音については
私は先生に「合ってます?」「高い?」「低い?」と訊いて正答を求め、
「2つの絃が同時に鳴る音が こう聞こえたら合っている」
というのを、今も時々確認しています。
フォークギターやエレキギターをする人達が
チューナーを用いたり
5弦5フレットの場所のハーモニクス音とA440 の音叉で
基音を合わせてから、ハーモニクスで6弦全てを調弦することは
書きましたが、開放弦があっているだけで
大なり小なり、フレット音痴は発生しますので、
高い精度の音程の正確さを求めているわけではないと思っています。
(というか無理があるように思います)
音叉の唸りにこだわりすぎるよりも
音律や 調性のニュアンス を
感じ取れた方が、楽曲のアナリーゼが楽しいのでは?
等とおもってます。
ヴァイオリン掲示板に戻る
1 / 2 ページ [ 12コメント ]